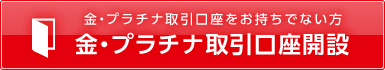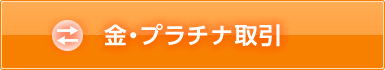金・プラチナ取引 > 金・プラチナ取引とは(金・プラチナ・銀の特徴) > 金・プラチナについてもっと知ろう!「マーケットレポート・コラム」 > 新村直弘氏が解説! 貴金属・コモディティレポート > 資源インフレ発生の可能性〜鉱物資源価格の上昇
資源インフレ発生の可能性〜鉱物資源価格の上昇
2021/12/15
提供:株式会社マーケット・リスク・アドバイザリー(MRA)
市場の関心がいつの間にかインフレにシフトしている。米国も雇用者数の増加はあっても物価が上昇しない、新常態に達したとの認識が一部であったが、足下は失業率の低下と共に物価が上昇する状態になっている。政権からすればインフレは物価上昇を通じて国民の不満が高まるため、政治家はどこの国でも基本的にはインフレを忌避する傾向が強い。
比較的順調に船出したと思われた米バイデン政権だが、コロナ対策やアフガニスタン撤退が拙速だったとして支持率が低下した。しかし、より支持率を低下させたのはインフレが進んだことだ。物価上昇の背景はコロナ対策による景気の回復と、コロナの影響による、1.供給やロジスティクスの制限、2.ライフスタイルの変化、3.雇用のミスマッチが要因である。そのため足下のデフレからインフレへの「ゲームチェンジャー」は、リーマンショック以降、先進諸国で加速した金融緩和ももちろんだが、その下地がある中でコロナショックが発生したためといっても言い過ぎではないだろう。
この状況において恐らく今後10年程度は積極的な投資が起きて、資源価格、特に鉱物資源価格が上昇する展開が予想される。インフラ投資の増加に繋がる要因が複数重なるためだ。具体的には中国・インドの同時人口ボーナス期入りによる投資増加、脱炭素・有炭素の二重投資、親米・親中経済圏の二重投資、といった二重・重複が発生する可能性が高い。
人口ボーナス期入りした国は、過去の経験則的に近代化投資(電気・ガス・水道整備、道路整備など)の増加で資源需要が増加することが確認されている。このときの投資規模は、国民の数と国土によるが、2020年から2030年頃まで、世界の1位・2位の人口を抱える中国・インドが「同時に」人口ボーナス期入りしている影響は小さくない。政治的な失敗がなければ、インフラ投資に用いる資源の需要は比較的堅い需要となるが、恐らく鉄鋼製品や銅、亜鉛、アルミ、ニッケル、コンクリートといった建材向けの需要が増加することになる。
脱炭素も恐らく投資を加速させることになるだろう。脱炭素は欧州が主導して進めている政策の1つであるが、この政策は気温上昇を1.5度に抑制するために、経済合理性がなかったとしても(他に割安なエネルギー源があったとしても)そちらにシフトをさせることを意味している。結果、新しく用いられる商品の需要は増加するため、需給バランスの変化を通じて価格が上昇することが予想される。対象となる資源は、代表的なものがEV(電気自動車)のバッテリー向けに用いられるニッケルやコバルト、リチウム、モーターに用いるレア・アースなどだ。ここで重要なのは、脱炭素達成後の世界がどのような世界になるか現時点では分からないが、脱炭素後の世界が「全く化石燃料を使わない世界」になったとしても「それが達成されるまでは化石燃料は使用される」ことである。今回欧州で起きたガスパニックは良い例だろう。自然エネルギーの場合、「同時に」供給が停止する可能性があるため、そのときに化石燃料や原子力といった従来型の熱源に頼らざるを得ないのは明らかである。また、中国やインドは石炭火力の増加ペースを抑制はするが、あと数十年といった期間、石炭やガスを使用し続ける計画であり、一定の需要が見込まれる。上流部門投資が抑制されるならばこれらの資源の価格も上昇すると考えるのが妥当で、季節によって価格が大きく変動する可能性が高まる。この他、米中対立による「サプライチェーンの見直し」「デカップリングによる製造拠点の見直し」投資が起きると予想される。日本が中国から製造拠点を国内に回帰させたり、他の国に再配置したりするということも十分に考えられる。
しかし、脱炭素と米中対立は政治的な対立でもあるため、米中間選挙や大統領選挙のタイミングでこの流れが逆回転する可能性はある。既に米国民は現在の物価上昇に不満を持っている状態である。もし仮に来年の米中間選挙で共和党が勝利すれば「脱炭素を止める」あるいは「米国の基準で行う」と米議会が言い出しかねない。この場合、これまでの脱炭素の流れが逆転することも十分に有り得る。また、選挙まで待たずともインフレを警戒してFRBが拙速な利上げを行い、景気がクラッシュして資源価格が急落、ということも有り得る状況だ。つまり現在の世界経済や資源市場は1つの転換点にさしかかっている、と考えられるのだ。
こうした脱炭素を巡り、資源の期待需要が政策動向で変化するため、価格の変動性が増すことが予想される(化石燃料生産が削減→気候の変化で価格急騰→急落、など)。そうなってくると、コスト削減(数量の見直し)などを主体に価格リスクを制御してきた企業のリスクへの対処方法も変化する可能性が出てくる
(資源価格への影響が大きな業種一覧はこちらをご参照下さい→「資源価格上昇の企業業績への影響」)。
古くて新しい課題であるが、今後の企業業績ひいては株価動向に、調達先の多様化や価格変動性制御の巧拙が大きく影響してくる時代が来ると予想される。

株式会社マーケット・リスク・アドバイザリー(MRA) 新村 直弘
1994年東京大学工学部精密機械工学科卒。日本興業銀行入行、本店金融市場営業部でコモディティ・デリバティブ開発を担当。国内製造業、金融機関をはじめ幅広い業種に対する価格リスクマネジメントの提案業務に従事。
バークレイズ・キャピタル証券、ドイツ証券を経て2010年5月、企業向け価格リスク制御のアドバイスを専業とする株式会社マーケット・リスク・アドバイザリーを設立、代表取締役に就任。テレビ東京やNHK、日経CNBC等でコメンテーターを務める。
また日経新聞、週刊ダイヤモンド、東洋経済、エコノミスト等のメディアにも多数寄稿。
日本アナリスト協会検定会員、資源エネルギー学会会員
著書:
『調達・購買・財務担当者のための原材料の市場分析入門』(ダイヤモンド社)
『コモディティ・デリバティブのすべて』(きんざい)
『天候デリバティブのすべて―金融工学の応用と実践』(東京電機大学出版)
金・プラチナについてもっと知ろう!
当コラムに関してご留意頂きたい事項
- 当コラムは投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 当資料に示す意見等は、特に断りのない限り当資料作成日現在の(株)SBI証券の見解です。当資料に示されたコメント等は、当資料作成日現在の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- 本資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証・約束するものではありません。
ご注意事項
- 買付時の手数料は、売買代金の1.65%(税込)、売却時の手数料は無料です。
- 本取引は金・銀・プラチナの価格変動により、投資元本を割り込むことがあります。
- 本取引は、政治・経済情勢の変化および各国政府の貴金属地金取引への規制等による影響を受けるリスクがあります。
また、かかるリスクが顕在化した場合、当社の提供するサービスの全部、または一部が変更、停止されるリスクがあります。 - 本取引は為替相場の変動により損失を被ることがあります。
- 本取引は、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあります。
- 本取引は売値(Bid:お客さまが売ることの出来る値段)と買値(Ask:お客さまの買うことのできる値段)の差(スプレッド)があります。
- スプレッドは固定されるものではなく、需給バランスや、政治・経済情勢の変化にともない、当社の任意で変更いたします。