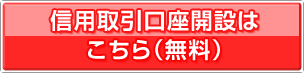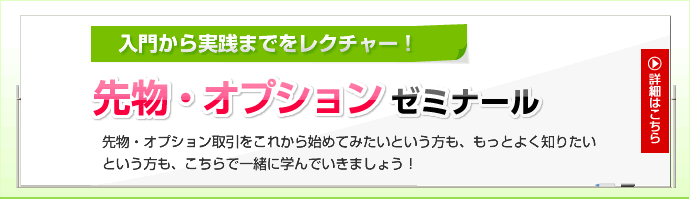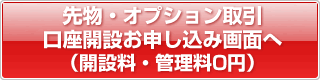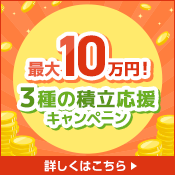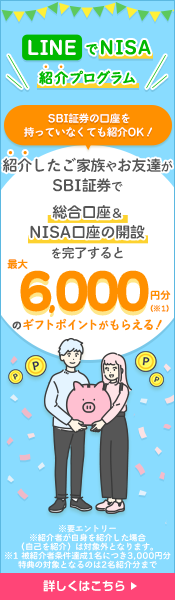10月に入り、10/3(月)および10/4(火)の日経平均株価は連騰となり、2016年度下半期は幸先の良いスタートになっています。ドイツ銀行への懸念が後退したことが要因です。ただ、10/7(金)に米雇用統計(9月)を控え、様子見を決め込む投資家も多いようで、売買代金は低迷し、株価も三角保ち合いの状態が続いています。
米雇用統計が終了した後も、10月は重要日程が目白押しで、「保ち合い放れ」のタイミングが近づいている可能性は十分あると考えられます。「脱デフレ」の可能性や中国経済回復の兆し等、新しい追い風を想定すれば、日経平均株価は「上放れ」する可能性の方が大きいとみられます。「上放れ」直前の日経平均から目を離すことはできないと考えられます。
<今週のココがPOINT!>
「保ち合い」継続も、その均衡が破れる兆しが見える? |
9月の日経平均株価は買い先行となり、9/5(月)には一時17,156円の高値を付けました。米雇用統計(8月)で非農業部門雇用者数の増加が月20万人ペースを維持し、年内利上げ観測が維持されたことで、円安・ドル高となったことが要因です。
しかしその後は、ECB(欧州中銀)理事会が追加緩和に後ろ向きの姿勢を示したこともあり、欧米金利が上昇する中、米国株安につられる形で日経平均株価も下落に転じました。9/21(水)の日銀金融政策決定会合後には上昇する場面もありましたが、同日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げが見送られた後は円高・ドル安気味となり、日経平均株価も再び軟調となりました。結局、9月末の日経平均株価は16,449円84銭と、前月末終値から2.6%の下落となりました。
10月に入り、10/3(月)および10/4(火)の日経平均株価は連騰となり、2016年度下半期は幸先の良いスタートになっています。ここもと世界のマーケットに動揺を与えてきたドイツ銀行問題への懸念が後退したことが要因です。ただ、10/7(金)に米雇用統計(9月)の発表を控え、様子見を決め込む投資家も多いようで、売買代金は2営業日ともに2兆円を大きく割り込んでおり、低迷が続いています。
図1は最近の日経平均株価の動きを示しています。上値については200日移動平均や25日移動平均が上値抵抗ラインとなっており、高値も切り下がる傾向となっています。反面、8月以降は75日移動平均が強固な下値支持ラインになっており、株価が下げてもその水準は維持する形になっています。チャート上は典型的な「三角保ち合い」の形になっています。
ちなみに、10/4(火)現在の25日移動平均は16,737円、200日移動平均は16,745円です。時価(10/4終値は16,735円)はこれに絡んだ微妙な水準で、もう少し大きく上昇すると、上放れが鮮明になってくる可能性があります。日経平均株価が「上放れ」となり、上昇加速となる可能性もあり、目が離せないのが現状です。
図1:日経平均株価(日足)〜「こう着感」が一層強まる中で2016年度下半期相場に突入
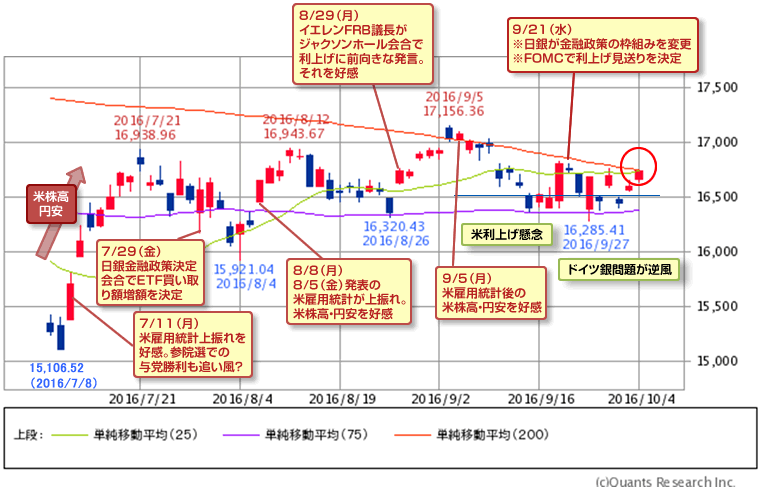
- ※当社チャートツールもとにSBI証券が作成。データは2016/10/4終値現在
日経平均株価の動きに強い影響を与えているのが為替相場、中でもドル・円相場で、日本株が上昇するためには円安・ドル高という援軍がほしい所です。また、ドル・円相場に強い影響を与えているのが米10年国債利回りで、それが上昇するほど、円安・ドル高になりやすいと考えられます。このように、日経平均株価への影響が大きいドル・円相場、米10年国債利回りですが、図2および図3のように、これらについても「三角保ち合い」の様相を呈しています。
ここで少々気になるのは、ドル・円相場の動きです。10/4(火)の東京市場の取引時間中、為替相場はおおむね1ドル102円台前半という三角保ち合いをやや円安・ドル高方向に上放れた水準で推移していました。年度上半期末に輸出企業による円買い需要が増えていたとすれば、10月に入って需給に変化が生じている可能性があります。今後年末にかけ、米国の年内利上げ論議が再燃しやすいことも加味すると、為替相場からまず均衡が崩れていく可能性もありそうです。
10月相場に円安・ドル高、株高が同時進行する可能性は意外に大きいかもしれません。
図2:ドル・円相場(日足)・過去3ヵ月
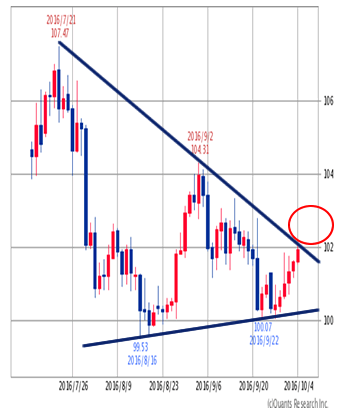
図3:米10年国債利回り・過去6ヵ月
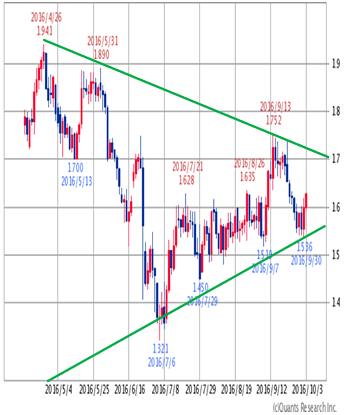
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2016/10/4(日本時間)取引時間中
当面のタイムスケジュール〜重要日程が目白押しの10月相場 |
表1は、当面の重要なタイムスケジュールをご紹介したものです。10/7(金)には米雇用統計(9月)の発表を控えており、当面はそれが最も重要なスケジュールになりそうです。10/11(火)には米国で非鉄大手アルコアの決算発表が予定されていますが、同社の決算発表は、米株式市場が決算発表シーズンを迎えるという「号砲」の役割を果たしています。10/14(金)には米国で大手金融機関の決算発表が早くもヤマ場を迎えることになります。
米雇用統計については、(1)非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回っているのか、(2)過去2ヵ月の非農業部門雇用者数の修正はどうなるのか、(3)労働参加率の上昇を伴った状態で失業率は低下したか、(4)労働時間や残業時間、賃金等に過熱の兆しは見られないのか、等がチェックポイントになります。
ちなみに、米雇用統計(9月)では非農業部門雇用者数が前月比17.4万人増え、増加数が8月の12.6万人増から加速するというのが市場コンセンサス(10/4現在)になっています。また、失業率は4.9%と依然低水準を続け、平均時給は前年同月比2.6%増と予想されています。FRB(米連邦準備制度理事会)等が指摘するように、もし米国経済が「完全雇用状態」に近いのであれば、失業率のさらなる低下は期待しにくいので、労働需給の逼迫(労働時間や残業の増加)や賃金の増加が生じているかどうかがチェック項目となります。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜重要日程が目白押しの10月相場
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 10/3(月) | 中国 | 国慶節(〜7日) | 日本のゴールデンウィークのように海外旅行へ出かける人が多い |
| 10/4(火) | 日本 | 投資の日 | |
| 米国 | 米副大統領候補・討論会 | (民主)ケイン元バージニア州知事、(共和)マイク・ペンス現インディアナ州知事 | |
| - | ノーベル物理学賞発表 | ||
| 10/5(水) | 米国 | 9月ADP雇用統計 | 雇用統計(10/5)の前哨戦 |
| 米国 | 9月ISM非製造業景況指数 | 雇用指数の増減などにも注目 | |
| - | ノーベル化学賞発表 | カーボンナノチューブ、リチウムイオン電池原型等が有力候補に | |
| 10/6(木) | 米国 | G20財務相・中銀総裁会議(ワシントン) | |
| 10/7(金) | 米国 | 9月雇用統計 | 非農業部門雇用者数の市場コンセンサス前月比17.5万人増 |
| 米国 | IMF・世銀年次総会(ワシントン) | ||
| - | ノーベル平和賞発表 | ||
| 10/9(日) | 米国 | 米大統領テレビ討論会(第2回) | |
| 10/10(月) | 日本 | 東京市場は休場(体育の日) | |
| 欧州 | ユーロ圏財務相会合 | ||
| - | ノーベル経済学賞発表 | ||
| 10/11(火) | 日本 | 景気ウォッチャー調査 | 地域の景気変動を感じ取れる仕事に就いている2,050人が調査客体 |
| 独 | 10月ZEW景況感指数 | アナリスト、機関投資家、市場関係者350人に聞く今後6ヵ月の景気見通し | |
| 米国 | ◎決算発表〜アルコア | 米国の2016/7〜9月期決算が発表シーズンに突入 | |
| 10/12(水) | 日本 | 8月機械受注 | 民間設備投資の先行指標 |
| 米国 | FOMC(9/20〜21)議事録 | 年内利上げ観測は強まるのか、後退するのか? | |
| 10/13(木) | 日本 | 9月都心オフィス空室率 | |
| 日本 | ソニーからPlayStation VRが発売 | VR(仮想現実)関連市場発展の起爆剤として期待 | |
| 中国 | 9月貿易収支 | ||
| 10/14(金) | 日本 | オプションSQ | |
| 中国 | 9月生産者物価/消費者物価 | ||
| 米国 | 9月小売売上高 | 消費者信頼感指数とともに、米個人消費の先行きを示唆? | |
| 米国 | 10月ミシガン大学消費者信頼感指数 | ||
| 米国 | イエレンFRB議長講演 | 年内利上げ観測は強まるのか、弱まるのか? | |
| 米国 | ◎決算発表〜JPMチェース、シティGなど | ||
| 10/15(土) | 印 | BRICS首脳会議 |
表2:日米中央銀行会議の結果発表予定日
| 2016年 | 2017年 | |
|---|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 11/1(火)、12/20(火) | 1/31(火)、3/16(木)、4/27(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 11/2(水)、12/14(水) | 2/1(水)、3/15(水) |
※各種報道等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは2016/10/4現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。
【ココがPOINT!】デフレ進行に歯止めがかかり、株価が上昇するシナリオも |
10/3(月)に発表された日銀短観(9月)では、大企業・製造業の業況判断指数が6月調査と同じ「+6」と横ばいになりました。また、大企業・全産業の経常利益は2016年度に前年度比9.2%減益の見通し(前回調査では7.2%の減益見通し)、当期純利益は同8.3%の増益見通し(前回調査では8.5%の増益見通し)となりました。
円高が逆風になっている2016年度は、上場企業についても業績予想下方修正は避けられないとみられます。ただ、ドル・円相場でさらなる円高・ドル安が加速しない限り、業績悪も相当織り込みが進んだと考えられます。
前年同期のドル・円相場(期中平均レート)は4〜6月が1ドル121円台半ば、7〜9月が122円台、10〜12月が121円台半ばでした。前年同期比で円高の厳しい影響が出やすい状態は年内一杯がピークとみられ、年明け以降は緩和しやすくなってきます。したがって、円高の影響を嫌気する局面も最終ステージに入っているかもしれません。
一方、原油先物相場の平均レートは昨年10〜12月が1バレル42ドル台であり、現在の1バレル48台ドル台であれば、前年同期比で上昇に転じる計算になります。このことは、資源・エネルギー関連や商社に追い風になるのみならず、物価にとっても上昇要因になってくると考えられます。脱デフレを目指す日銀にとっては「援軍」になるかもしれません。仮に原油価格の安定が続けば、米国のみならず資源国経済の回復も鮮明になってくるとみられます。
中国経済に明るい兆しが出てきたことも過小評価は禁物だと思います。同国の製造業PMI(財新・マークイット)は昨年9月の47.2を底に2016年は7〜9月に50超となってきました。輸出にも回復の兆しが出ています。また「経済の体温計」としての役割がある生産者物価は2015年の後半に前年比5.9%下落の水準まで下げていましたが、2016年は8月に前年比0.8%下落まで改善しています。
円高の悪影響がおおむね織り込まれ、物価の下げ止まりや中国経済の落ち着き等が鮮明化してくれば、日本の景気・企業業績も改善に向かうとの期待が高まりそうです。
図4は「日経平均株価」と「予想PER13倍相当水準〜予想PER16倍相当水準」をグラフ(※)にしたものです。2016/4〜9月の間、日経平均の予想PERは一日当たり平均で14倍で推移していた計算です。昨年まで、日経平均は予想PER15倍前後で推移してきましたが、円高を背景とする業績不安で下がった格好です。予想PERの高低は市場心理の強弱を示すとみられ、その意味では、株式市場のマインドが低下したと考えられます。
ただ、上記したように、投資環境の改善が鮮明になってくれば、日経平均株価の予想PERが再び上昇し、少なくとも15倍程度を回復しても不思議ではありません。日経平均株価の「上放れ」はその意味でも、近いと考えられます。
※1例をあげると、10/3(月)に「予想PER14倍水準」は16,504円でしたが、これは同日現在の予想EPS(一株利益)1,178.9円に14倍を掛けた水準として計算されます。
図4:日経平均株価と予想PER
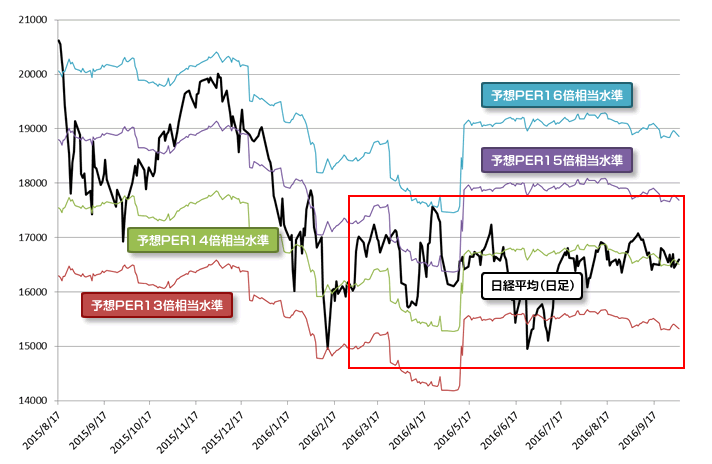
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
ドイツ銀の信用不安で乱高下
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |