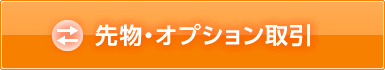世界的な貿易戦争への懸念や、米ハイテク企業への逆風が続く中、東京株式市場も辛抱の時期が続いているようです。日経平均株価は2万1千円を少し上回る水準で低迷が続いています。
こうした中、4/2(月)に発表された日銀短観(3月調査)は、企業業績が曲がり角を迎えていることを示唆する内容でした。ただ、そうした懸念は円高進行とともにすでに株価に織り込まれてきたと考えられます。今後、業績予想の修正や決算発表を経て、アク抜けが進めば、株価は上昇に転じる可能性がありそうです。
<今週のココがPOINT!>
年初来安値から反発も、25日移動平均線が上値抵抗ラインに |
日経平均株価(図1)は、米トランプ大統領が中国からの輸入に対して関税を課すとの表明を受け、3/23(金)に974円13銭安となり、終値は20,617円86銭と年初来安値を示現しました。週末の休みをはさんだ3/26(月)も売り優勢の展開が続き、この日の取引時間中には一時20,347円49銭と、昨年9/29(金)以来の安値を付けました。
しかし、中国が外資系金融機関の資本規制緩和や半導体購入額の増額を検討しているとの報道もあり、「貿易戦争」への懸念が後退し、3/26(月)の米国市場では、NYダウ(図2)が前週末比669.40ドル高と急反発に転じました。この上昇幅は9年5ヵ月ぶりの大きさとなります。これを受け、翌日の3/27(火)には、日経平均株価が前日比551円22銭の上昇となり、終値も3営業日ぶりに2万1千円台を回復しました。この日行われた「森友問題」に関する佐川前国税庁長官に対する証人喚問で、安倍首相を含む政治の関与が否定されたことで、政治不安が後退したことも株価上昇に拍車をかけました。
しかし、3/27(火)のNY市場では、個人情報利用問題で揺れるフェイスブックのザッカーバーグCEOが議会証言に呼び出されるとの観測や、当局による事故調査が伝えられたテスラなどハイテク株が売り込まれ、NYダウは344.89ドル安と急反落。これを受けた3/28(水)の日経平均株価は286円01銭安と反落してしまいました。しかし、3/29(木)には、北朝鮮と韓国による南北首脳会談が4/27(金)に開催されるとの報道があり、地政学的リスクの後退が好感され、日経平均株価は127円77銭高と反発しました。続く3/30(金)も前日のNY株高(フェイスブックが個人情報問題で対策発表を好感)を好感し、日経平均株価は295円22銭高と続伸しました。
結局、3/30(金)の日経平均終値は21,454円30銭となり、月次ベースでは2.8%の下落となり、2ヵ月連続の値下がりとなりました。反面、年度ベースでは13.5%の上昇となり、2年連続での値上がりとなりました。
新年度明けとなった4/2(月)の東京市場では、新規資金流入を期待する買いが先行し、日経平均株価は前週末比143円17銭高となる場面もありましたが、25日移動平均線で頭を押さえられ、上値が重くなり、終値は65円72銭安と反落してしまいました。一方、この日のNY市場では、トランプ大統領によるアマゾンへの「口撃」や、中国による報復関税発動を受け、NYダウは連休前終値に対し、458.92ドルと急反落してしまいました。これを受け、4/3(火)の日経平均株価は前日比96円29銭安と続落になりました。
図1:日経平均株価(日足)〜25日移動平均線が上値抵抗ラインに
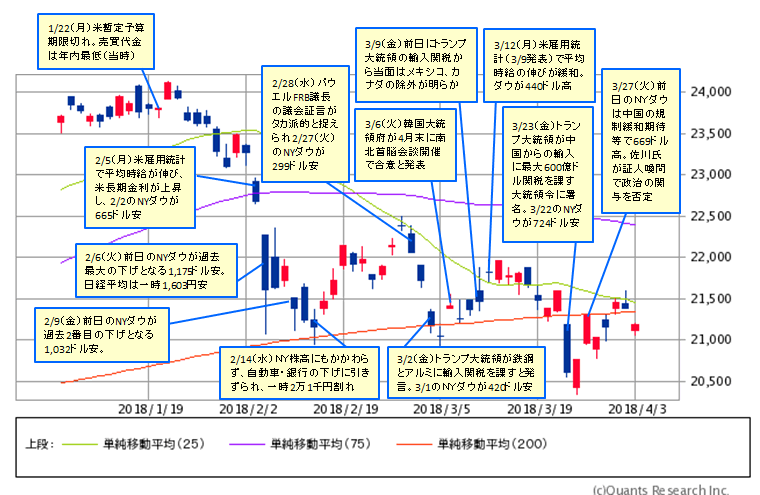
- ※当社チャートツールをもとにSBI証券が作成。データは2018/04/03現在
図2:NYダウ(日足)
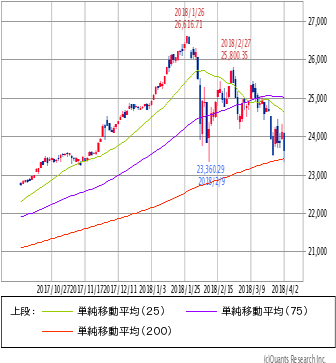
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは米国時間2018/04/02現在
図3:ドル・円相場(日足)
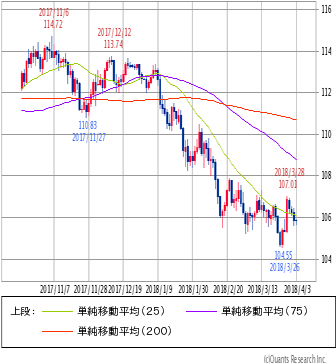
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2018/04/03取引時間中
当面のタイムスケジュール〜米雇用統計(3月)の発表に注目 |
4月第1週の重要日程では、米雇用統計(3月)の発表がもっとも注目されるスケジュールとなりそうです。非農業部門雇用者数(前月比の増減数)は2月の31.3万人増から、3月は18.5万人増になると予想(市場コンセンサス)されています。また、失業率は2月の4.1%から3月は4.0%へと改善が続くとの予想(同)です。平均時給については、2月には前年同月比2.6%増でしたが、3月には2.7%になると予想(同)されています。
2/2(金)に発表された米雇用統計(1月)において、平均時給が前年同月比2.9%増(その後2.8%に修正)と発表され、米長期金利の急上昇および米株価急落をもたらし、それが世界株安につながった経緯があるため、市場の関心は平均時給の増減に集まりそうです。平均時給の伸びが市場予想を大幅に上回ったり、それによって金利が大幅に上昇した場合、株価が大きく下がる可能性があるため注意が必要です。逆に、非農業部門雇用者数については、伸びが数万人にとどまるなど、極端に低い数字にならない限り、多少弱くても悪材料にはならない可能性があるとみられます。
3/29(木)に米国で発表された週次の新規失業保険申請件数(数字が低いほど労働市場が強いことを示す)では、申請件数が21.5万件と1973年以来の低水準となりました。労働市場は現在も強い状態が続いています。4/4(水)にはADP雇用統計の発表が予定されており、労働省から発表される「本番」の雇用統計のヒントになりそうです。また、同じ日にはISM非製造業景況指数が発表されますが、その内訳としての「雇用指数」にも注目したい所です。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜米雇用統計(3月)の発表に注目
月日 |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 4/3(火) | 米国 | 3月新車販売債数 | |
| 4/4(水) | 米国 | 3月ADP雇用統計 | コンセンサスでは+21万人 |
| 米国 | 2月製造業受注 | コンセンサスは前月比+1.7% | |
| 米国 | 3月ISM非製造業景況指数 | 雇用や新規受注などの個別指標にも注意 | |
| 4/5(木) | 中国 | ★中国市場等が休場 | 清明節(〜6日) |
| 4/6(金) | 米国 | 3月雇用統計 | コンセンサスは平均時給(前年同月比)+2.7% |
| 4/9(月) | 日本 | 3月景気ウォッチャー調査 | |
| 4/11(水) | 日本 | 2月機械受注 | |
| 日本 | ☆決算発表 | イオン、良品計画、吉野家HD他 | |
| 中国 | 3月消費者物価 | コンセンサスは前年同月比+2.7% | |
| 4/12(木) | 日本 | 2月機械受注 | |
| 日本 | ☆決算発表 | 安川電(決算期変更)、ファーストリテ | |
| 日本 | 3月都心オフィス空室率 | ||
| 4/13(金) | 米国 | ★決算発表 | JPモルガン・チェース、シティグループ |
表2:日米欧中央銀行会議の結果発表予定日(月日は現地時間)
| 2018年 | |
|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 4/27(金)、6/15(金)、7/31(火)、9/19(水)、10/31(水)、12/20(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 5/2(水)、6/13(水)、8/1(水)、9/26(水)、11/8(木)、12/19(水) |
| ECB(欧州中銀)理事会・金融政策会合 | 4/26(木)、6/14(木)、7/26(木)、9/13(木)、10/25(木)、12/13(木) |
- ※各種報道、日米欧中銀Webサイト等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは当レポート作成日現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。なお、ECB理事会は金融政策の議論・決定を行う会合の日程のみ掲載しました。日付は日本時間(ただし、表2の中央銀行会議の結果発表日程は現地時間)を基準に記載しています。
【ココがPOINT!】「企業業績の踊り場」を織り込む東京株式市場 |
4/2(月)に日銀短観(3月調査)の結果が発表されました。最も代表的な指標である大企業・製造業の業況判断指数(表3)は+24でした。この数字は市場の予想(+25)を下回るものでしたが、前回(12月調査)時点での「先行き」見通し(+21)に対しては上回る数字でした。3ヵ月前に企業が想定していた状況よりは良かったということになります。大企業・非製造業も同様の傾向でした。
企業の事業計画の前提になっているドル・円相場は、2017年度が1ドル110円67銭でした。2018年3月まで1年間の平均為替レートを計算すると同110円80銭前後であり、これとほぼ近い数字です。2018年度の前提為替レートは1ドル109円66銭であり、企業の多くで前提レートがあまり円高方向に修正されていない現状が浮かび上がっています。
さらに、大企業.・全産業の「売上・収益計画」(表5)について、2017年度の売上高は前年度比4.7%増、経常利益が同12.0%増、純利益が24.3%増となったようです。2018年度は売上高が前年度比1.0%増、経常利益が同2.2%減、純利益が1.5%減の見通しです。また、大企業・全産業の設備投資は2017年度5.2%増から、2018年度は2.3%増の見通しです。
ここまでで今回の日銀短観が示す企業業績の現状をまとめれば「今までは想定した以上に好調だったものの、円高の影響が顕在化してくる今後は慎重に見た方が良いかもしれない」ということでしょう。企業は2017年4月から12月まで、前年同期比で4%強の円安・ドル高メリットを享受できましたが、2018年1〜3月期には逆に4%強の円高・ドル安圧力になっています。今後、1ドル106円程度の水準が続いた場合、同様の円高・ドル安圧力がかかり続けるとみられるため、特に輸出企業の業績にはブレーキがかかってくるとみられます。
大企業・全産業の「雇用人員判断」(表6:マイナスが大きいほど人手不足感が強い)は12月調査の-19から今回は-22となりました。人手不足感はさらに強まっていると考えられます。また、「価格判断」(表4)では製造業を中心に仕入価格の上昇が予想以上に進んでおり、それに比べると、販売価格への転嫁があまり進んでいないことを示しています。円高のみならず、原材料費や仕入価格、人件費等、収益を圧迫する要因も増えているようです。総じて、企業業績は曲がり角を迎えていると考えられます。
もっとも、発表が本格化しつつある小売業など、2月決算銘柄の決算発表と、その後の株価動向は、現状では比較的落ち着いているように思われます。日銀短観および上場企業の決算発表を通じ、円高や人手不足、原材料費の値上がり等を背景とする企業業績の減速は一旦織り込まれ、「悪材料出尽くし」となる可能性もあります。それまで日経平均株価は21,000円前後を下値支持ラインとする「値固め」の時期が続く可能性がありそうです。
表3:「日銀短観」における「業況判断指数」
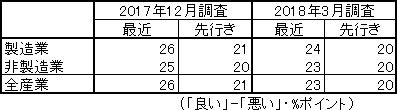
表4:「日銀短観」における大企業「価格判断」
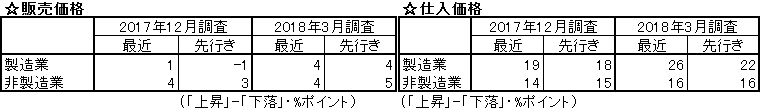
表5:「日銀短観」における大企業「売上・収益計画」
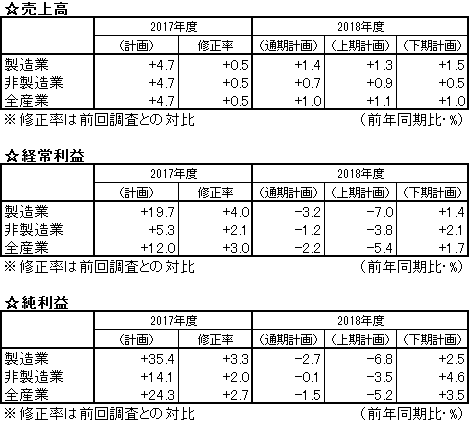
表6:「日銀短観」における大企業「雇用人員判断」
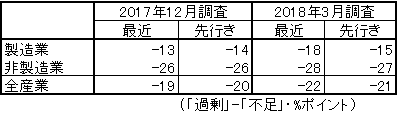
- 表3〜表6は「日銀短観」(2018年3月調査)をもとにSBI証券が作成。「最近」は調査時点、「先行き」は3ヵ月後の状態を示しています。
- 今回の「日銀短観」は全国企業10,020社を対象に実施され、回答期限は2/26(月)〜3/30(金)となっていました。回答率は99.3%でした。
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
海外投資家が9週ぶりに先物買い越し!売りは一巡したか