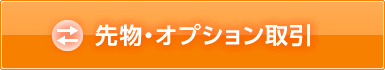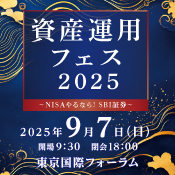5月の東京株式市場は前半に上昇した後、後半はこう着状態となりました。前半は欧州の政治リスクや北朝鮮との緊張状態が後退する中、買い安心感が強まりました。ただ、米国の「ロシアゲート」問題もあり、後半は上値の重い展開を余儀なくされました。
6月相場はどうなるのでしょうか。米国の政治問題によっては波乱になる可能性もありそうです。ただ、日経平均株価の予想EPS(一株利益)が過去最高水準を更新し、株価には割安感が強まっており、基本的には堅調な展開が予想されます。
<今週のココがPOINT!>
5月は前半高も後半は上値の重い展開に |
5月の東京株式市場では、日経平均株価が買い先行になりました。4月末終値は19,196円74銭でしたが、5/16(火)には一時2万円の大台まであと1円51銭に迫る19,998円49銭となりました。
フランス大統領選挙で親EU派のマクロン氏が勝利したことに加え、北朝鮮と米国の間で高まっていた緊張状態も4月下旬には峠を越えた形となり、連休をはさんだ5月最初の3営業日で日経平均株価は700円近くも上昇しました。5/5(金)に発表された米雇用統計(4月)では非農業部門雇用者数が市場予想(19万人増)を上回る21.1万人増となり、米国経済の強さが改めて認識される形になりました。外為市場でドル・円相場が一時114円台まで円安・ドル高となり、冒頭に述べた通り、日経平均株価は2万円まであと一歩の水準に迫りました。
しかし米国で5/17(水)に、ロシアとの関係を疑われていたフリン前大統領補佐官への捜査について、トランプ大統領がコミー前FBI長官に捜査終結を求めたと伝わり、NYダウが前日比372.82ドル安と波乱になりました。これを受けて5/18(木)の東京市場でも株価が急落し、日経平均株価は261円02銭安となり、終値は19,553円86銭となりました。その後は少し落ち着く展開となりましたが、5月上旬の高値水準が抵抗ラインとなり、上値の重い展開となりました。
なお、我が国では5月中旬まで決算発表が続きました。日経新聞の集計では、上場企業・全産業(金融を除く)の2017年3月期における経常利益は前期比7.2%増、純利益は18.3%増となりました。また、2018年3月期は経常利益が同3.8%増、純利益が9.2%増となる見込みです。これを受けて、日経平均採用企業の業績を示唆する同平均株価の予想EPS(一株利益)は4月末に1,203円でしたのが、5/29(月)には1,400円と過去最高水準を超えてきました。株価の上昇にもかかわらず、日経平均株価の予想PERは4月末15.95倍から5/29には14.05倍と逆に大きく低下しており、割安感が強まる形になっています。
米国でも2017年1〜3月期における主要企業の純利益は前年同期比15%程度増えた模様です。日米とも好調な企業業績が株価上昇の追い風になったとみられます。
図1:日経平均株価(日足)〜5月後半は上値の重い展開に
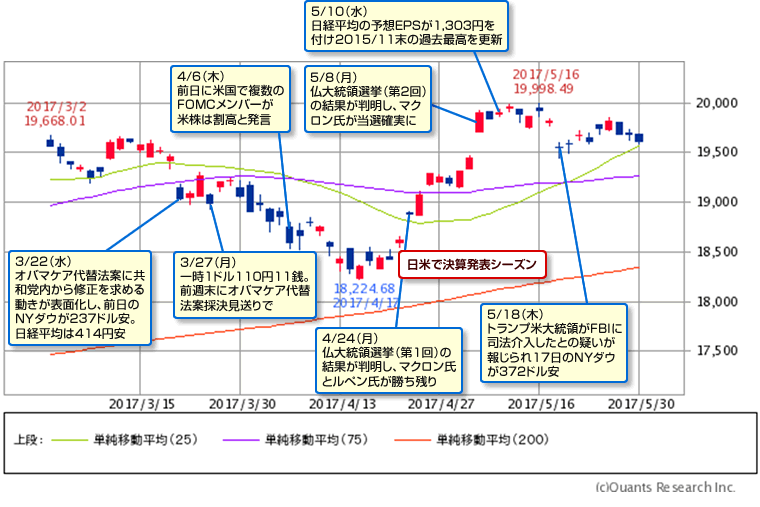
- ※当社チャートツールをもとにSBI証券が作成。データは2017/5/30取引時間中
図2:ドル・円相場(日足)

- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2017/5/30取引時間中
図3:S&P500(日足)

- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2017/5/26(現地時間)現在
当面のタイムスケジュール〜6/2(金)発表の米雇用統計(5月)に注目 |
当面のタイムスケジュールの中では、6/2(金)に米労働省から発表される米雇用統計(5月)が最も注目されます。非農業部門雇用者数は4月の21.1万人増から、5月は17.5万人増になると市場では予想されています。また、失業率は前月と同じ4.4%になると予想されています。
5月に発表された米経済指標については、住宅着工件数(4月)、中古住宅販売件数(同)等の住宅関連指標に加え、企業マインドを反映するISM製造業景況指数(同)、設備投資の先行きを占う耐久財受注(同)等、市場予想を下回る指標が目立ちました。さらに自動車販売も踊り場を迎えたと考えられ、米経済の先行きは必ずしも楽観できない状態です。ただ、5/26(金)に発表された1〜3月期のGDP改定値は前期比(年率)+1.2%となり、速報値の+0.7%から上方修正されました。税の還付の遅れが一時的減速の背景にあるとも言われており、今後の経済指標は再び強い数字が目立ってくる可能性があります。市場では今の所、米経済の減速は一時的との見方が多いようです。
6/14(水)に結果が発表される米FOMC(連邦公開市場委員会)では、政策金利が現在の1.0%から1.25%に引き上げられるとの見方がコンセンサスになっています。ただ、年内にさらにあと1回0.25%引き上げられるとの見方については、金利先物市場から見た「確率」で38%に過ぎず、コンセンサスとは言えないようです。今度の雇用統計は6月のFOMCの直前だけにもともと注目度は高いとみられますが、万が一数字が悪いと米金融政策に与える影響は大きいとみられ、注意が必要だと考えられます。
なお、週次で発表される米新規失業保険申請件数については、4月に比べ5月はこれまでの所、総じて低水準になっています。それを見る限り、雇用統計での「波乱」は想定しにくいと考えられます。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜6/2(金)発表の米雇用統計(5月)に注目
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 5/30(火) | 日本 | 4月有効求人倍率他 | 前回は1.45倍 |
| 米国 | 3月S&PコアロジックCS住宅価格指数 | コンセンサスは前月比(季調済)+0.9% | |
| 米国 | 5月CB消費者信頼感指数 | ※CB=カンファレンスボード | |
| 5/31(水) | 日本 | 4月鉱工業生産 | コンセンサスは前月比+4.3% |
| 中国 | 5月製造業PMI | 4月は51.2 | |
| 米国 | 4月中古住宅販売仮契約 | コンセンサスは前月比+1.0% | |
| 米国 | ベージュブック | 米金融政策に影響 | |
| 6/1(木) | 日本 | 1〜3月法人企業統計 | |
| 日本 | 5月新車販売台数 | ||
| 米国 | 5月ADP雇用統計 | 雇用者数のコンセンサスは+175千人 | |
| 米国 | 5月ISM製造業景況指数 | コンセンサスは55.2 | |
| 米国 | 5月新車販売台数 | ||
| 6/2(金) | 米国 | 5月雇用統計 | 非農業部門雇用者数のコンセンサスは+175千人 |
| 米国 | 4月貿易収支 | ||
| 6/5(月) | 米国 | 4月製造業受注 | |
| 米国 | 5月ISM非製造業景況指数 | コンセンサスは57 | |
| 米国 | アップル世界開発者会議(〜9日) | ||
| 6/7(水) | - | OECD経済見通し | |
| 6/8(木) | 日本 | 1〜3月GDP改定値 | 速報値は前期比・年率+2.2% |
| 日本 | 4月国際収支 | ||
| 日本 | 4月オフィス空室率(都心5区) | 3月3.6%、4月3.39% | |
| 日本 | 5月景気ウォッチャー調査 | ||
| 中国 | 5月貿易収支 | ドル建てで4月(前年同月比)の輸出は+8.0%、輸入は+11.9% | |
| 英国 | 総選挙 | EU離脱に向けた保守党の基盤固めの様相 | |
| 欧州 | ECB定例理事会(ドラギ総裁会見) | 量的緩和の解除に向け文言の変更も | |
| 6/9(金) | 日本 | メジャーSQ | |
| 中国 | 5月消費者物価 | 4月は前年同月比+1.2% | |
| 中国 | 5月生産者物価 | 4月は前年同月比+6.4% |
表2:日米欧中央銀行会議の結果発表予定日
| 2017年 | |
|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 6/16(金)、7/20(木)、9/21(木)、10/31(火)、12/21(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 6/14(水)、7/26(水)、9/20(水)、11/1(水)、12/13(水) |
| ECB(欧州中銀)理事会・金融政策会合 | 6/8(木)、7/20(木)、9/7(木)、10/26(木)、12/14(木) |
※各種報道、日米欧中銀Webサイト等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは当レポート作成日現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。なお、ECB理事会は金融政策の議論・決定を行う会合の日程のみ掲載しました。日付は現地時間を基準に記載しています。
【ココがPOINT!】20,000円を上回る可能性、ただし後半は注意も? |
6月の日経平均株価は20,000円を超えて上昇する可能性が十分ありそうです。好調な企業業績に対する評価が不十分とみられるからです。過去2年間の日経平均株価の予想PERの平均は15倍で、現在の予想EPS1,400円にそれを掛けると21,000円と計算されます。予想PERは市場心理を反映すると考えられます。市場心理が「平均並み」に回復すれば、20,000円を超えて上昇する可能性は十分ありそうです。
企業業績を支えているのは、一時に比べて安定した外為相場であることは確かですが、製造業の円高耐久力は相当強まったと考えられます。外為相場が現状の水準近辺で推移する程度であれば、株式市場への悪影響は小さいとみられます。冒頭の図1でもご理解頂けるように、日経平均株価は25日移動平均線とタッチが近い状態となっており、一時の過熱感が後退しています。きっかけさえあれば、上昇に弾みが付く可能性がありそうです。
リスク要因としては、前項でご説明した米国経済の他、同国の「ロシアゲート」疑惑があげられます。ただ、予算教書をすでに提出したこともあり、今後の経済政策の主導権はその相当部分が議会共和党に移るとみられます。もともと、トランプ大統領の経済対策には米経済にとってプラスの面もマイナスの面も拮抗しているだけに、同疑惑で株価が下げる場面があれば、買い場になる可能性もありそうです。
なお、日経平均株価の騰落レシオの動きについても一応の注意が必要です。日経平均株価採用銘柄について
(25日間の値上がり銘柄数を合計した数値)÷(同値下がり銘柄数を合計した数値)×100(%)
という式で計算された比率が「騰落レシオ」で、120%を超えると「過熱圏」と考えられています。足元では5/24(水)・5/25(木)に142.7%まで上昇し、その後低下に転じています。一般的には株価のピークアウトを示すパターンと理解されます。
ただし、図4〜図6を見てご理解頂けるように、騰落レシオのピークアウトが即、株価の下落につながっている訳ではありません。特に騰落レシオが140%を超えるくらいの上昇相場では、ピークアウトから株価下落まで「時差」があったり、その後も株価が高原状態になるケースがあります。図6のケースでは、騰落レシオのピークアウト後1ヵ月で日経平均株価は1,300円近く上昇しています。現在も、上記したように、移動平均線とのかい離がほぼ解消し、もともと過熱感が少ないため、短期的に株価が下落に転じる可能性は後退しているように思われます。
とはいえ、騰落レシオのピークアウト後は市場で選別色が強まり、日経平均株価の上昇にその分ブレーキがかかりやすくなります。特に月の後半にかけては要注意となる可能性もありそうです。
図4:日経平均株価(日足)とその騰落レシオ(25日)
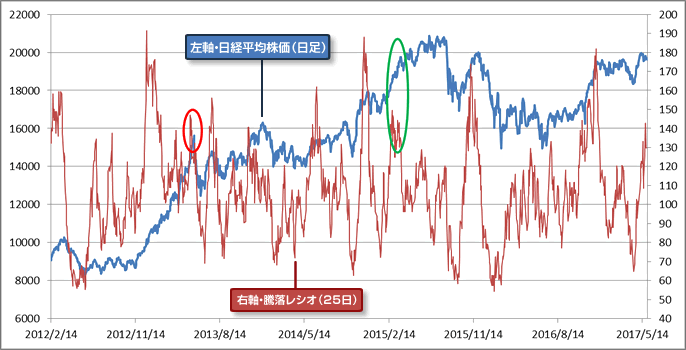
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
図5:騰落レシオ「過熱圏」の例1
(図4内の赤枠を拡大)
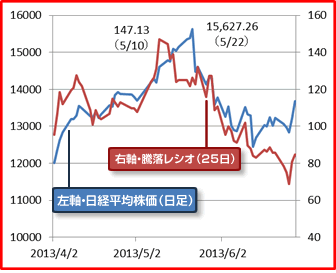
図6:騰落レシオ「過熱圏」の例2
(図4内の緑枠を拡大)
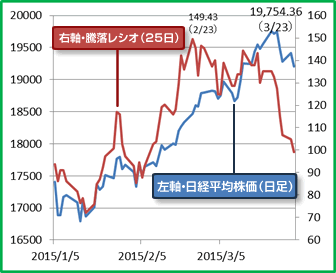
- ※日経平均株価データをもとにSBI証券が作成
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
20,000円上放れは6/2米雇用統計次第か