東京市場では、日経平均株価が下落基調となっています。米自動車販売の下振れ等があり、米金利低下や円高圧力が続いているためです。地政学的なリスクも高まっており、今週いっぱいは要注意の状況が続きそうです。
しかし、「4月」は過去の成績をみた場合、「冴えないことが普通」という月ではありません。日経平均株価の「4月」は過去10年で平均2.5%上昇し、「12月」(上昇率3.3%)に次ぐ年間第2位の成績になっています。今週いっぱいを乗り切ることができれば、来週以降は次第に、市場のムードが変わってくる可能性もありそうです。
下落基調 |
東京株式市場は下落基調となっています。日経平均株価は3/31(金)に18,909円26銭でしたが、翌週末である4/7(金)の終値は18,664円63銭となり、週間で1.3%下落しました。翌週も4/10(月)こそ上昇したものの、4/11(火)は売り先行となりました。
日経平均株価は3/30(木)に「一目均衡表」のクモの下限を下回って「三役逆転」となり、「弱気相場」入りが確認された形になっていました。そうした中、4/3(月)に米国で発表された同国新車販売台数(3月)が予想を下回る弱い数字となり、米国経済の先行きに不透明感を与えました。また、4/5(水)に公表されたFOMC議事録では、参加メンバーが米国株の割高感を指摘していたことが明らかになりました。これらを受けて、米10年国債利回りは一時2.3%台を割り込むなど、低下圧力の強い動きが続き、外為市場ではドル・円相場が1ドル110円台の円高・ドル安水準が定着するかのような動きとなりました。
こうした中、4/6(木)〜4/7(金)には米国で米中首脳会談が実施されました。両国は貿易不均衡是正に向けた「100日計画」に合意した模様で、当面この問題は棚上げの形になりました。むしろ、首脳会談中に米国がシリアに向けミサイル攻撃を実施したことや、共同声明の発信がなかったことで、世界的な緊張の高まりが意識されるようになり、投資家のリスク回避姿勢が強まる形となりました。
なお、4/7(金)に発表された米雇用統計(3月)では、非農業部門雇用者数が前月比9.8万人の増加にとどまり、事前予想である18万人を大きく下回りました。過去2ヵ月分の雇用者数も計3.8万人下方修正されるなど、弱さの目立つ内容になりました。しかし、雇用者数の伸び悩みについては悪天候の影響が指摘され、一時的との見方が多かったようです。失業率が4.5%と10年ぶりの低水準を記録したこともあり、労働市場の好調は維持されていると考えられたようです。雇用統計が市場に与えた影響は限定的であったように思われます。
図1:日経平均株価(日足)〜下落基調
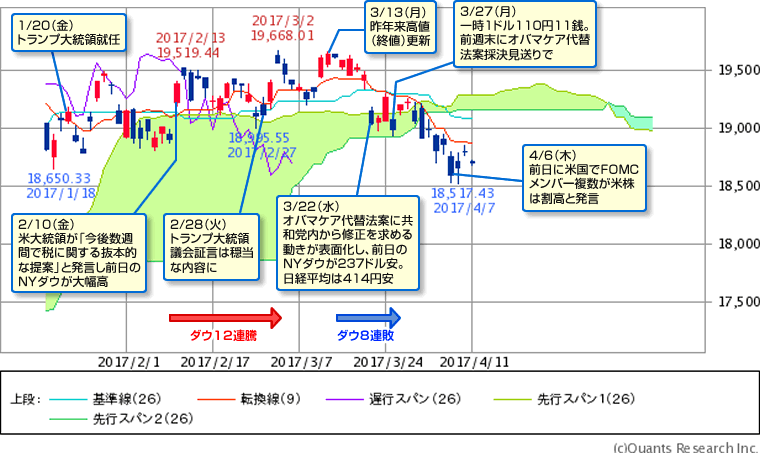
- ※当社チャートツールをもとにSBI証券が作成。データは2017/4/11現在
図2:米10年国債利回り(日足)・一目均衡表
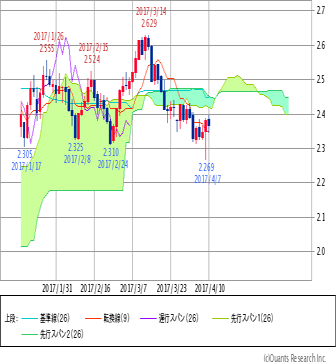
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2017/4/10(現地時間)現在
図3:ドル・円相場(日足)・一目均衡表
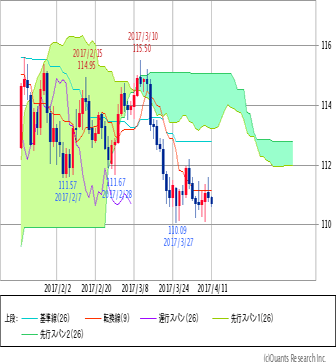
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2017/4/11現在
当面のタイムスケジュール〜今週いっぱいが転換点になるか? |
経済面でも、地政学的見地からも今週いっぱいが転換点になる可能性があります。
米国では4/13(木)から、2017年1〜3月期の決算発表が本格的に始まります。一般的に米国株は、決算発表直前の時期は警戒感もあって下押し圧力が強いものの、決算発表では事前予想を上回る収益をあげる企業が多くなる傾向にあり、株価も上向きやすいと考えられています。米主要企業の純利益は2017年1〜3月期に前年同月比10%増と、前四半期の8%増から増益率が加速する見込みです。特に時価総額上位企業の発表が多い4月後半は、米国株式市場に追い風が吹く可能性が大きくなってくるとみられます。
そうした米決算発表シーズンの本格化を控え、4/15(土)頃までは市場が波乱となる可能性もあり、注意が必要になりそうです。米国市場が3連休となるため、直前に様子見気分が強まりやすい面もあります。さらに、北朝鮮で「建国の父」である金日成主席の生誕105周年記念日もあり、地政学的なリスクの高まりにも一応の注意が必要です。しかし逆に、今週を無事に乗り切れば、来週以降は株価が切り返すチャンスも広がりそうです。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜今週いっぱいが転換点になるか?
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 4/11(火) | 北朝鮮 | 最高人民会議 | |
| ドイツ | 4月ZEW景況感指数 | 機関投資家やアナリストなど350人を対象としたアンケート | |
| 4/12(水) | 日本 | 2月機械受注 | 民間設備投資の先行指標 |
| 日本 | ★決算発表 | ローソン、良品計画、イオン他 | |
| 中国 | 3月消費者物価 | 市場コンセンサスは前年同月比+1.1% | |
| 米国 | NY国際自動車ショー(〜23日) | ||
| 4/13(木) | 日本 | 3月都心オフィス空室率 | 2月は3.7% |
| 日本 | ★決算発表 | ファーストリテイリング他 | |
| 中国 | 3月貿易収支 | 輸出の市場コンセンサスは前年同月比3.2%増 | |
| 米国 | 4月ミシガン大学消費者マインド指数 | 3月の先行指数のコンセンサスは86.5 | |
| 米国 | ☆決算発表 | JPモルガン・チェース、シティ他。米決算発表シーズン開始 | |
| 4/14(金) | 日本 | オプションSQ | |
| 米国 | 3月消費者物価 | 食品・エネルギーを除く部分のコンセンサスは前年比+2.3% | |
| 米国 | 3月小売売上高 | 自動車・ガソリンを除く部分のコンセンサスは前月比0.3% | |
| 米国 | 休場 | 聖金曜日 | |
| 4/15(土) | 米国 | 財務省為替報告書提出期限 | |
| 北朝鮮 | 金日成主席生誕105周年 | ||
| 4/17(月) | 日本 | 3月首都圏新規マンション発売 | 2月は前年同月比3.3%増 |
| 中国 | 1〜3月期GDP | 市場コンセンサスは前年同期比+6.8% | |
| 中国 | 3月小売売上高 | 市場コンセンサスは前年同月比+9.7% | |
| 中国 | 3月鉱工業生産 | 市場コンセンサスは前年同月比+6.3% | |
| 4/18(火) | 日本/米国 | 経済対話初開催 | |
| 米国 | 3月住宅着工件数 | 市場コンセンサスは前月比-2.2% | |
| 米国 | 3月鉱工業生産 | 市場コンセンサスは前月比+0.5% | |
| 米国 | ☆決算発表 | J&J、バンカメ、GS、IBM他 | |
| 4/19(水) | 日本 | 3月日本製半導体製造装置BBレシオ | 2月は1.36。受注額は前年同月比47.3%増 |
| 日本 | 訪日外客数 | 2月は前年同月比7.6%増 | |
| 中国 | 上海モーターショー | ||
| 米国 | ベージュブック | 米金融政策の重要な判断材料 | |
| 米国 | ☆決算発表 | モルガン・スタンレー、クアルコム、アメックス他 | |
| 4/20(木) | 日本 | 3月貿易統計 | |
| 米国 | 4月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数 | 市場コンセンサスは25 | |
| 米国 | ☆決算発表 | D.R.ホートン、ベライゾン他 | |
| 4/21(金) | 米国 | 3月中古住宅販売件数 | 市場コンセンサスは前月比+1.3% |
| 米国 | ☆決算発表 | GE他 |
表2:日米欧中央銀行会議の結果発表予定日(2017年以降)
| 2017年 | |
|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 4/27(木)、6/16(金)、7/20(木)、9/21(木)、10/31(火)、12/21(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 5/3(水)、6/14(水)、7/26(水)、9/20(水)、11/1(水)、12/13(水) |
| ECB(欧州中銀)理事会・金融政策会合 | 4/27(木)、6/8(木)、7/20(木)、9/7(木)、10/26(木)、12/14(木) |
※各種報道、日米欧中銀Webサイト等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは当レポート作成日現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。なお、ECB理事会は金融政策の議論・決定を行う会合の日程のみ掲載しました。日付は現地時間を基準に記載しています。
【ココがPOINT!】海外投資家のスタンスに変化は生じるか? |
下落基調が続く東京株式市場ですが、「4月」は、過去の成績をみた場合、「冴えないことが普通」という月ではありません。図4は日経平均株価の過去10年間の月別平均騰落率ですが、「4月」は過去10年で平均2.5%の上昇という結果になっています。年間でのトップは「12月」(上昇率3.3%)で、それに次ぐ第2位の成績で、むしろ好成績を期待してもよい月と言えそうです。
「4月」の日経平均株価が上昇しやすい背景には、海外投資家の動向がありそうです。図5は東証の主体者別売買動向のうち「海外投資家」の動向を過去10年についてみたものです。「4月」の買い越し額は12ヵ月の中でも最大になっていることがお分かり頂けると思います。4月は機関投資家等に新規資金の配分があり、買いスタンスが強まってくる月として知られていますが、海外投資家もそれに乗じて買い越しになりやすいことがわかります。
東京市場では20日頃から3月決算の発表が本格化してくる予定ですが、米国同様、東証上場の銘柄についても17年度は利益の拡大が期待されています。決算発表シーズンは5月中旬にかけて続く予定ですが、好業績の株価への織り込みは次第に進捗すると予想されます。
図4:日経平均株価の月別騰落率(過去10年)
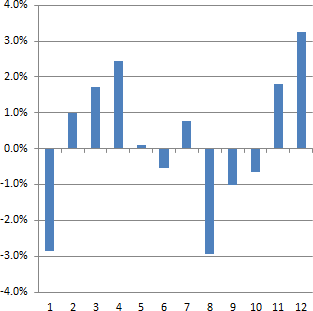
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。日経平均の月間騰落率の平均を過去10年間でみたもの
図5:海外投資家の月別売買動向(東証・過去10年)
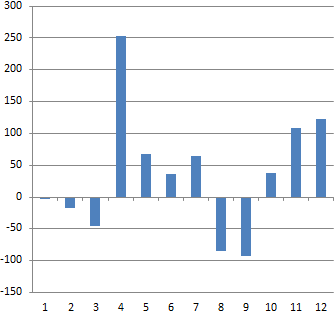
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。東証の海外投資家の売買動向(週次)について、月ごとに1週間当たりの平均をみたもの。単位は10億円
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
シリア、北朝鮮問題での急落に注意!







