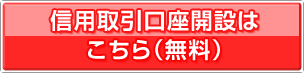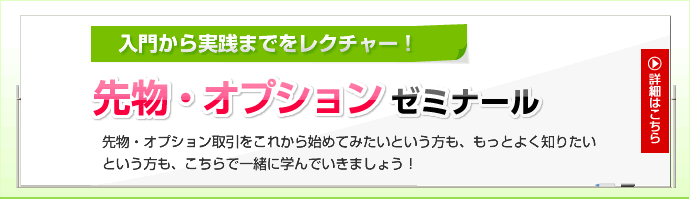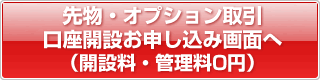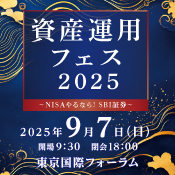11/21(月)に日経平均株価は18,000円台で大引けを迎えました。同平均株価が終値でこの水準を回復してきたのは1/6(水)以来のことになります。米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、その後米国の株価・金利が上昇し、ドル高・円安が進んだことなどが背景です。続く11/22(火)も朝方の地震でヒヤリとしたものの、株価は底堅く推移しました。
2017年にかけ、トランプ次期大統領の米経済成長戦略が次々と明らかになってくると考えられ、米長期金利やドル・円相場はレンジを切り上げたと考えられることから、日本株も中長期的な上昇トレンドを描ける可能性が出てきました。しかし、現段階の株高や金利上昇、ドル高などは「理想買い」の域を出ないとみられ、短期的には株価の反落に注意が必要かと思います。
相場上昇の本質は資金シフトか |
11/21(月)に日経平均株価は18,000円台で大引けを迎えました。同平均株価が終値でこの水準を回復してきたのは1/6(水)以来のことになります。米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、その後に米国の株価・金利が上昇し、ドル高・円安が進んだことなどが背景です。
トランプ氏は大統領選挙において、移民の排斥や保護主義的な貿易政策を主張する一方で、大規模な減税や財政出動を伴ったインフラ投資および金融規制緩和等も主張してきました。トランプ氏が大統領選挙で勝利した後は、米国経済や株式市場にとって前向きな部分にスポットが当たり始め、金融株やインフラ関連が主導する形で株価が上昇に転じました。ただ、米国経済の現状はおおむね好調と考えられ、そこからさらに減税や財政出動が打ち出されたことで市場の期待インフレ率が高まり、金利は上昇し、ドルも上昇するという展開になりました。
すなわち、大統領選挙の投票日である11/8(火)から11/21(月)まで、NYダウは3%上昇し、米10年国債利回りは1.86%から2.32%へと上昇、ドル・円相場では5円超もドルが上昇して1ドル111円台となりました。日経平均株価はこうした米国の諸指標の動きを好感する形でこの間に5%も上昇しました。
なお、市場では現在の上昇相場を「トランプ相場」(あるいは「トランプ・ラリー」)と呼び、それが「いつまで続くのか」、あるいは「どこまで上がるのか」ということが多くの人々の関心事になっているようです。後述するように「トランプ相場」の先行きを読む上でのポイントは米長期金利の動きであり、為替相場であると考えられます。現在、それらの動きにやや過熱感が強まっているのが現状であり、その意味ではそろそろ株価の反落に気を付けるべきであるとみられます。
ただ、今回の上昇相場を「トランプ相場」とだけ考えると本質を見誤る可能性があります。なぜならば、米長期金利の上昇や円安・ドル高はトランプ氏が大統領選挙に当選した11/9(水)に始まったことではなく、その前から進行していたためです。トランプ氏の当選は米金利上昇やドル高の原因ではなく、加速要因であると「225の『ココがPOINT!』」では考えています。
好調な米国経済を受けてFRB(米連邦準備制度理事会)が再利上げの方向に舵を取る一方で、日本銀行やECB(欧州中銀)もマイナス金利の限界を示唆し始め、先進国の債券相場は天井(金利面ではボトム)が確認された形だと見受けられます。世界的な資金フローは新興国から米国(先進国)に、債券から株式へと動きを強める可能性が出てきました。米10年国債利回りは7月に1.36%まで低下していましたが、大統領選挙当日の11/8(火)にはすでに1.86%まで戻っていましたし、ドルの対円相場は8/18(木)の1ドル99円87銭を底に11/8には同105円10銭まで回復しました。
このように大きな資金フローの変化が背景にある以上、米国をリード役とする先進国の株高は中長期的に継続する可能性が出てきたとみられ、そのことに対する過小評価は禁物であるとみられます。
図1:日経平均株価(日足)〜米大統領選の後に上昇が加速
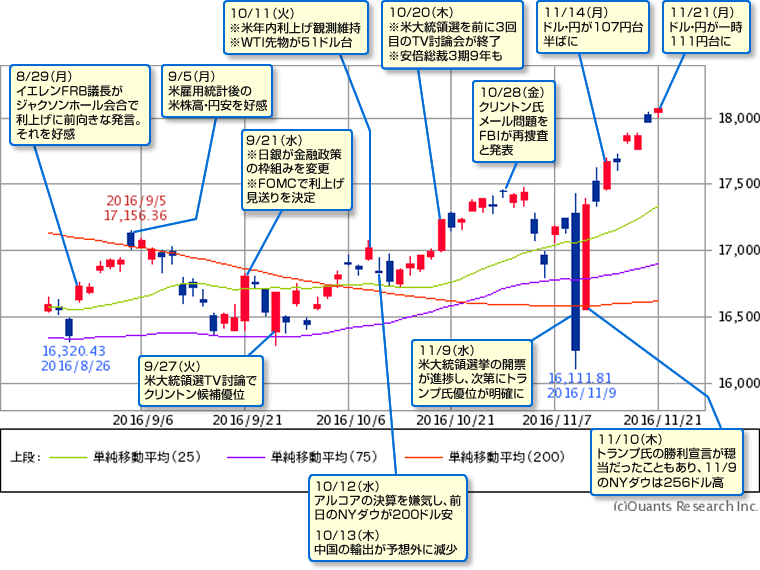
- ※当社チャートツールもとにSBI証券が作成。データは2016/11/21現在。
図2:ドル・円相場(日足)・過去1年

図3:米10年国債利回り(週足)・過去2年
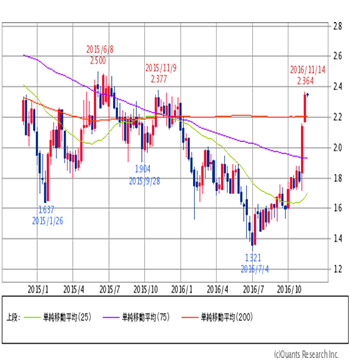
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2016/11/21現在。
当面のタイムスケジュール〜12/2(金)に米雇用統計が発表される予定 |
我が国の上場企業の決算発表は保険なども含めてすべて終了しました。決算発表のタイミングでは、利益を中心に実績がアナリスト予想や会社計画を上回ったのか、今期見通しは修正されたのか、またはそれがアナリスト予想と比べ強気なのか弱気なのか等がポイントになってきました。しかし、決算発表の時期が終わると、アナリストがその成長可能性を再評価すべく、企業訪問を本格化させる時期になります。これまで、米大統領選挙という重要イベントが日本株の物色方向にも影響してきましたが、ここからは、ファンダメンタルズの再評価を軸にした物色も増えてくると考えられます。
なお、当面発表予定の米経済指標については12/2(金)の11月雇用統計がもっとも重要であると考えられます。現在、金利先物市場が示す12/14(水)に実施が予定されているFOMC(米連邦公開市場委員会)での「利上げ確率」は100%になっています。無論、何が起こるかわからない金融市場であり、利上げが見送られる可能性はゼロではないと考えられますが、市場の予想はそこまで偏っているということです。それだけに、FOMC以前としては最後の雇用統計発表(12/2)で弱い数字が出ると衝撃も大きくなりやすいので、十分な注意が必要だと思われます。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜12/2(金)に米雇用統計が発表される予定
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 11/22(火) | 日本 | 10月全国百貨店売上高 | 2016/3〜9は前年同月比でマイナスが続く。9月は前年同月比-5% |
| 米国 | 10月中古住宅販売件数 | 市場コンセンサスは前月比±0% | |
| 米国 | 10月北米半導体製造装置BBレシオ | 受注/出荷を示す。2015/12以降1以上で推移。9月は1.05 | |
| 11/23(水) | 日本 | ◎東京市場は休場(勤労感謝の日) | |
| 米国 | 10月耐久財受注 | 市場コンセンサスは輸送用機器を除く部分で前月比+0.2% | |
| 米国 | 9月FHFA住宅価格指数 | 市場コンセンサスは前月比+0.5% | |
| 米国 | 10月新築住宅販売件数 | 市場コンセンサスは前月比-0.5% | |
| 米国 | FOMC議事録(11/1〜2開催分) | ||
| 11/24(木) | ドイツ | 11月Ifo景況感指数 | ドイツの7,000社を対象に現在と6ヵ月後の見通しをアンケート |
| 米国 | ◎米国市場は休場(感謝祭) | ||
| 11/25(金) | 日本 | 10月全国消費者物価指数 | 食品・エネルギーを除く部分で前年同月比+0.2% |
| 英国 | 7〜9月期GDP(改定値) | 暫定値は前年同期比+2.3% | |
| 米国 | ブラックフライデー | 米年末商戦がスタート | |
| 11/28(月) | ユネスコが日本の祭りを無形文化遺産に? | ||
| 11/29(火) | 日本 | 10月失業率・有効求人倍率 | 9月は失業率3.0%、有効求人倍率1.38倍 |
| 米国 | 7〜9月期GDP(改定値) | 市場コンセンサスは前期比(年率)+3.0% | |
| 米国 | 9月S&PコアロジックCS住宅価格指数 | 9月は前年同月比+5.1% | |
| 米国 | 11月CB消費者信頼感指数 | 市場コンセンサスは100 | |
| 11/30(水) | 日本 | 10月鉱工業生産 | 9月は前月比0.8% |
| 日本 | 臨時国会会期末(延長も?) | ||
| - | OPEC定例総会 | 原油価格の今後のトレンドを決定づける可能性も | |
| 米国 | ベージュブック | ||
| 米国 | ADP雇用統計 | 事前予想では前月比16万人増 | |
| 12/1(木) | 日本 | 7〜9月法人企業統計 | 設備投資動向に注目 |
| 中国 | 11月製造業PMI | 中国企業のマインドは? | |
| 米国 | 11月自動車販売台数 | ||
| 米国 | ISM製造業景況指数 | ||
| 12/2(金) | 米国 | 11月雇用統計 | 非農業部門雇用者数は17.3万人増の予想 |
表2:日米中央銀行会議の結果発表予定日
| 2016年 | 2017年 | |
|---|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 12/20(火) | 1/31(火)、3/16(木)、4/27(木)、6/16(金)、7/20(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 12/14(水) | 2/1(水)、3/15(水)、5/3(水)、6/14(水)、7/26(水) |
※各種報道等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは2016/11/22現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。
【ココがPOINT!】米長期金利、為替相場の先行きが日経平均を左右 |
「トランプ相場」の先行きを読む上でのポイントは米長期金利の動きであり、為替相場であると考えられます。現在、それらの動きにやや過熱感が強まっているのが現状であり、その意味ではそろそろ株価の反落に気を付けるべきであるとみられます。
図4はドル・円相場とその25日移動平均および25日移動平均からのかい離率をグラフ化したものです。ドル・円相場の日々線が25日移動平均から±5%かい離すると逆方向に行きやすくなっています。11/18(金)にこのかい離率は5.2%に達していますので、そろそろ要注意と言えるのかもしれません。同様に図5は米10年国債利回り(日足)とその25日移動平均および25日移動平均かい離率をグラフ化したものです。こちらは日々線が25日移動平均から±20%かい離すると逆方向に行きやすくなっています。
ただ、移動平均からのかい離率を使うときに注意すべきなのは、あくまでも短期的な売買タイミングの参考にすべきであるということです。図4のドル・円相場の日足チャートにおいて大きな丸印で囲んだ2014年秋の例をみてもご理解いただけるように、相場に大きな変化が生じる時は、移動平均かい離率が「過熱状態」のまま長期化するケースもあるということです。この時は米国の量的緩和が着実に縮小する中で日銀が追加緩和を実施したことで円安・ドル高が続きました。
25日移動平均からのかい離率でみると、ドル・円相場、米10年国債利回りともに、短期的には注意が必要と考えられます。したがってNY株、日経平均株価はともに短期的に波乱含みの局面と言えるかもしれません。しかし、このような短期的な過熱感は大きなトレンド転換を示している可能性があり、過度の懸念は不要であると考えられます。
図4:ドル・円相場(1ドル当たり円)と25日移動平均・同かい離率〜±5%が節目ではあるものの・・・
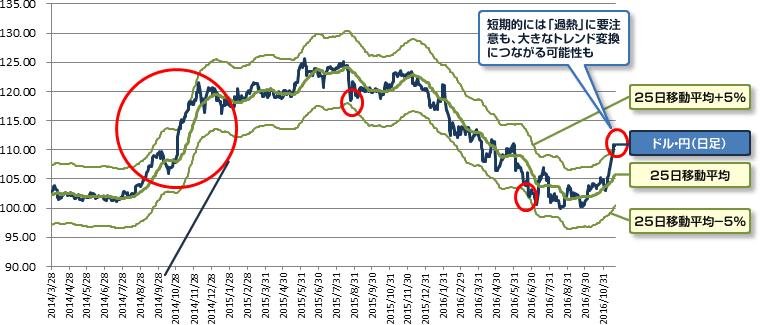
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
図5:米10年国債利回り(%)と25日移動平均・同かい離率〜±20%が節目ではあるものの・・・
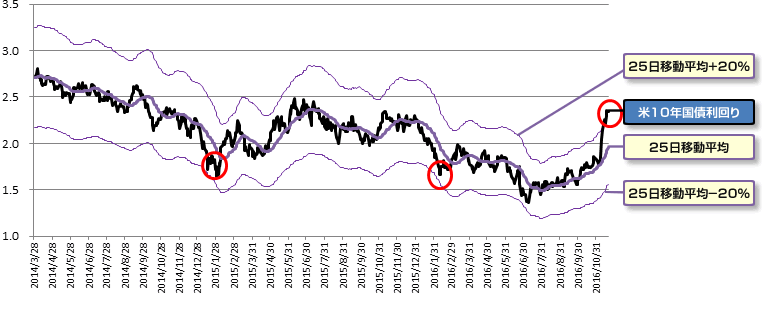
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
トランプラリーで18,000円回復!今後の見通しは?
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |