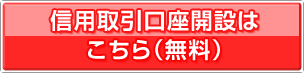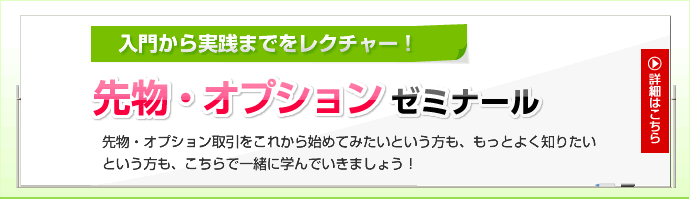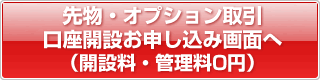9/21(水)に日銀金融政策決定会合の結果が発表され、金融政策の「新たな枠組み」が発表されました。日経平均株価はそれを好感する形で一時16,823円まで上昇し、ドル・円相場は102円台後半まで円安・ドル高となりました。しかしその後は、米国の政策金利引き上げが見送られたことや、米大統領選挙を控えたテレビ討論会への警戒感等を背景に円高・ドル安が進展し、日経平均株価も反落に転じました。
こうした中、東京株式市場は間もなく「10月相場」を迎えることになります。下旬には国内で上場企業の17/3期・第2四半期の決算発表が本格化し、海外では米大統領選挙(11/8が投票日)が終盤を迎えることになります。それまで国内外の株式市場はこう着感の強い状態が続きそうですが、そこがその後の保ち合い放れをにらんだ「仕込み場」になる可能性が大きそうです。さて、ポジションはどちらに取るべきでしょうか。「買い」でしょうか、「売り」でしょうか。
<今週のココがPOINT!>
「2大イベント」後もこう着状態が続く東京株式市場 |
9/21(水)に日銀金融政策決定会合の結果が発表され、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」という「新たな枠組み」の導入が決定されました。
(1)物価上昇率が2%以上で安定的に持続するまでマネタリーベースの拡大を継続(時間軸効果)
(2)国債保有残高はおおむね年80兆円増加させる(これまで「おおむね」の表現はなかった)
(3)イールドカーブを操作〜長期金利はおおむねゼロで推移するよう操作。また買入国債の残存年限廃止
(4)マイナス金利のさらなる拡大は見送り
(5)ETFの年間買入額5.7兆円のうち、TOPIXに連動するETFを対象とする部分を拡大
日銀の発表を受け、9/21の株式市場では株価が上昇し、円安・ドル高が進みました。業種的には銀行をはじめ、広義の金融株の上昇が目立っていましたが、円安で輸出株も堅調に推移し、ほぼ全面高になりました。
米国時間の同じ日(日本時間の9/22早朝)、米国では、FOMC(米連邦準備制度理事会)の結果が発表され、政策金利の引き上げ見送りが決定しました。おおよそ市場コンセンサス通りの結果でしたが、その後は一部ポジションの巻き戻しに加え、米大統領選挙を控えたテレビ討論会への警戒感等を背景に円高・ドル安が進展し、日経平均株価も反落に転じました。
こうした中、日本時間9/27(火)午前10時から11時30分にかけて実施された米大統領候補・テレビ討論会では、両候補とも決め手に欠けたものの、クリントン候補がやや有利との見方が多かった模様です。この日の東京株式市場では、テレビ討論会を控えた警戒感から、日経平均株価が一時8/5(金)以来の安値を付けていましたが、その後は持ち直す展開となりました。
図1:日経平均株価(日足)〜「2大イベント」後もこう着状態が続く日経平均株価
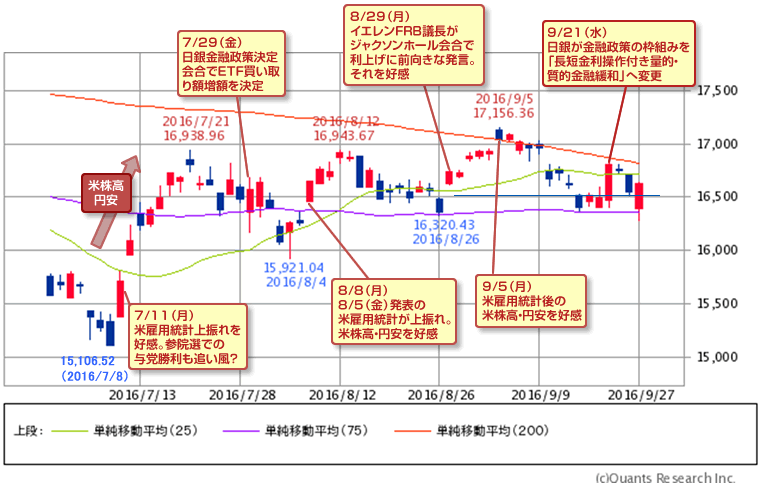
- ※当社チャートツールもとにSBI証券が作成。データは2016/9/27終値現在
図2はドル・円相場(日足)の動きです。日銀金融政策決定会合の結果を受け、9/21には一時102円台後半の円安・ドル高水準を付けましたが、FOMCで利上げが見送られた後は逆に、一時100円07銭の円高・ドル安水準に戻ってしまいました。FOMCで利上げが見送られることは「市場予想通り」でしたが、一部「利上げ」を期待していた向きの円買い戻しがあったとみられることや、テレビ討論に向けたポジション調整が影響したとみられます。テクニカル的には、三角保ち合いを円高・ドル安方向に放れた形となり、株式市場には要注意の材料となっています。
図3は外為相場に影響を与える米10年国債利回りの推移です。9/2(金)の雇用統計発表を経て、一時は保ち合い(直線2と3に囲まれた部分)を上放れた形になりましたが、直線1で跳ね返され、今度は直線3まで押し戻される展開になっています。広い意味では、大きな三角保ち合い(直線1と3に囲まれた部分)内での動きが続いているとみられます。
株式、為替、債券市場では非常にこう着感の強い状態が続いているといえそうです。
図2:ドル・円相場(日足)・過去3ヵ月
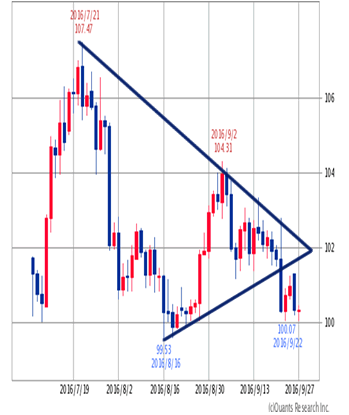
図3:米10年国債利回り・過去6ヵ月
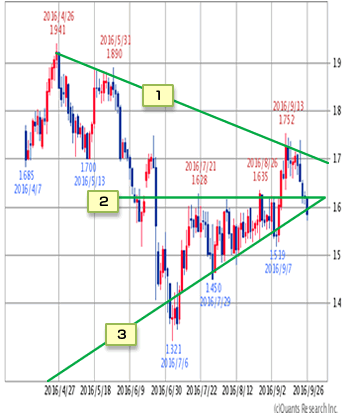
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2016/9/27(日本時間)取引時間中
当面のタイムスケジュール〜10月は「企業業績」に要注意 |
表1は、当面の重要なタイムスケジュールをご紹介したものです。10/3(月)には日銀短観(9月調査)、10/7(金)には9月の米雇用統計が発表を控えています。上半期を無事に通過しても、市場参加者に休む暇はなさそうです。
10月は日銀短観で企業業績のおおよその方向感をとらえ、上場企業の17/3期第2四半期決算で細かくチェックするという月になりそうです。昨年の7〜9月期は平均為替レートが1ドル122円台という円安・ドル高水準であったのに対し、本年は102円台半ば前後の円高・ドル安水準になりそうです。前年同期比でみた場合、4〜6月期は11%程度の円高・ドル安でしたが、7〜9月期は16%前後の円高・ドル安になると見込まれます。輸出企業を中心に業績予想の下方修正が増えると見込まれます。
ただ、10月に入ったあたりから、一部メディアの観測報道や、業績予想の修正(おもに下方修正)が増えるとみられます。株式市場もそれを警戒して、上値では売りが増える可能性が想定されます。
表1:当面の重要なタイムスケジュール〜10月は上場企業の業績をチェックする重要な月に
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
| 9/27(火) | 日本 | 日銀金融政策決定会合(7/28・29)議事録 | |
| 日本 | 東京市場9月末権利付最終日 | 9月末付の配当、株主優待の権利を確保したい投資家は注意 | |
| 米国 | 7月S&PコアロジックCS住宅価格指数 | 20都市では前年同月比+5.13% | |
| 米国 | 9月消費者信頼感指数 | 市場コンセンサスは98.7 | |
| 9/28(水) | 米国 | 8月耐久財受注 | 輸送用機器を除く受注の市場コンセンサスは前月比0.3%減 |
| 9/29(木) | 米国 | 4〜6月期GDP確報値 | 市場コンセンサスは前期比・年率+1.4% |
| 米国 | 8月中古住宅販売仮契約 | 仮契約は通常1〜2ヵ月以内に本契約となる。7月は過去2番目の高水準 | |
| 9/30(金) | 日本 | 日銀金融政策決定会合(9/20・21)主要意見 | 注目された日銀会合でメンバーの見方は? |
| 日本 | 8月消費者物価指数 | 7月のコアコア指数は前年同月比0.3%増 | |
| 日本 | 8月失業率/有効求人倍率 | ||
| 日本 | 8月鉱工業生産 | 8月は前月比0.4%減 | |
| 米国 | シカゴ購買部協会景気指数 | ||
| 10/1(土) | 中国 | 9月製造業PMI | 中国製造業のマインドは? |
| 10/3(月) | 日本 | 日銀短観(9月調査) | 大企業・製造業の業況判断指数は3月、6月ともに+6、9月のコンセンサスも+6 |
| 日本 | 9月自動車販売台数 | 前回は5.7%増 | |
| ドイツ | マークイット/BMEドイツ製造業PMI | ||
| 米国 | 9月ISM製造業指数 | もっとも重要な米経済指標のひとつ。米国企業のマインドは? | |
| 10/4(火) | 米国 | 米副大統領候補・討論会 | |
| 10/5(水) | 米国 | 9月ADP雇用統計 | 雇用統計(10/5)の前哨戦 |
| 米国 | 9月ISM非製造業指数 | 雇用指数などの詳細にも注意 | |
| 10/7(金) | 米国 | 9月雇用統計 | 非農業部門雇用者数の市場コンセンサス前月比17.5万人増 |
表2:日米中央銀行会議の結果発表予定日
| 2016年 | 2017年 | |
|---|---|---|
| 日銀金融政策決定会合 | 11/1(火)、12/20(火) | 1/31(火)、3/16(木)、4/27(木) |
| FOMC(米連邦公開市場委員会) | 11/2(水)、12/14(水) | 2/1(水)、3/15(水) |
※各種報道等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは2016/9/27現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。
【ココがPOINT!】金融機関に配慮した「新枠組み」が脱デフレに寄与する? |
日本銀行が9/21に決定した金融政策の「新しい枠組み」のポイントはどこにあるのでしょうか。最も重要なポイントのひとつは、金融機関への配慮を重視したことであると「225の『ココがPOINT!』」では考えています。
金融緩和は単純に、金利を下げたり、お金の量を増やしたりすれば、十分ということではありません。日本銀行から民間銀行にいくらお金が流れても、企業や家計に「貸出の増加」という形で十分にお金が回らなければ、その目的を達することはできないと考えられます。図4は金融機関による貸出増減をみたものですが、2013/4の「黒田バズーカ」以降は増えたものの、最近、特に2016年以降は頭打ちになっています。その意味で「マイナス金利」の効果が疑問視されることになります。
マイナス金利になっても金融機関による貸出増加ペースが加速しなかったのは、それが金融機関の収益を圧迫することが強く影響していると考えられます。それゆえ、金融庁や銀行などは総じてマイナス金利に異を唱えてきました。収益基盤が比較的広いメガバンクに比べ、地銀や信金・信組などの比較的小規模の金融機関ではより影響が厳しいと考えられます。
今回の新しい枠組みは以下の3点で金融機関に配慮していると考えられます。
(1)マイナス金利を「深堀り」しなかったこと
(2)「イールドカーブを立てる」ことにより金融機関に収益確保の道を残したこと
(3)ETFの買入額のうち、TOPIX連動部分を増やしたため、銀行の株価下支えが期待できること
「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」という「新たな枠組み」について、過小評価すべきではないと「225の『ココがPOINT!』」では考えています。企業業績や米大統領選挙を控え、上値が抑えられやすい10月相場は「仕込み場」であると考えられます。
図4:金融機関貸出残高(平残・前年同月比・%)
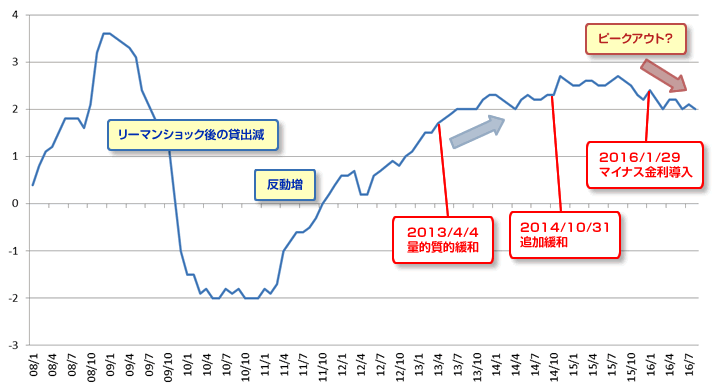
- ※日銀、BloombergデータをもとにSBI証券が作成。信金・信組を含む
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
株式市場は金融政策から財政政策に視点が移る
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |