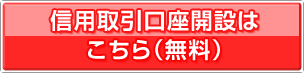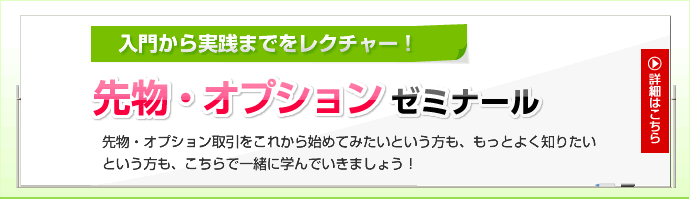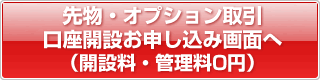9/29に底を入れた日経平均株価ですが、その後は上昇が続いています。11/9には8/21以来の高値水準を回復しました。さて、問題はここからです。日経平均株価はさらに上昇するでしょうか、逆に下落へ転じてしまうでしょうか。
「225の『ココがPOINT!』」では、日経平均の上昇はここからが「本番」だと考えています。今回は、ここまでの相場上昇の要因を整理するとともに、今後の方向感を占ってみたいと思います。
日経平均株価の上昇が継続 |
日経平均株価は9/29安値16,901円を起点にした上昇相場が続いています。10/30に終値で19,000円台を回復したのに続き、11/9には8/21以来の高値水準を回復する動きとなっています。
8/11の人民元切り下げ以降、中国経済への不透明感が強まり、世界の株式市場は波乱の様相を強めましたが、そうした波乱の動きは9/29まででいったん織り込まれたと考えられます。米国株、中国株、ドイツ株など、海外の主要株価指数は9/29を転換点として上昇しており、日本株もそれに沿った動きになったと考えられます。
テクニカル的には、10月中旬以降、日経平均株価が25日移動平均を上回る水準での推移が続いている上、同移動平均自体が上向きの傾向を強めるなど、形状が先行き強気を示唆し始めています。図1は日経平均株価の一目均衡表ですが、すでに「遅行スパンが日足チャートを下から上抜け」「転換線が基準線を下から上抜け」等の形状変化が起こっていますが、11/5には日足チャートが「クモ」の上限を上抜け、「三役好転」となりました。
こうした中、株式市場で「2015年最大のイベント」と考えられていた「郵政上場」は、関連3社すべてが売出価格を上回る初値を付けるという好調なスタートとなりました。「郵政上場」の成功は、これまで株式市場に参加していなかった新しい投資家層の市場参入を促し、市場に厚みを加えたと考えられます。「最大のイベント」を控えて動きにくかった面もあり、それを通過したこと自体も追い風になりそうです。
なお、米国ではイエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長から、2015年内に政策金利の引き上げの可能性が残っているとの示唆があり、米国では再び年内利上げに対する「警戒感」が再燃しました。そうした中、改めて注目されることになった米国10月の雇用統計が11/6に発表され、非農業部門雇用者数は前月比27.1万人増と市場コンセンサス(18.0万人増)を大きく上回りました。利上げに対する警戒感が残る中での強い雇用統計になった訳で、通常であれば米国株が下げても不思議ではない所です。しかし、11/6のNYダウは上昇し、外為市場では1ドル123円台まで円安・ドル高が進みました。どうやら、米国市場は「年内利上げ」を織り込んだように思われます。NYダウの上昇基調も続きそうです。
図1:「三役好転」となった日経平均・一目均衡表(日足)
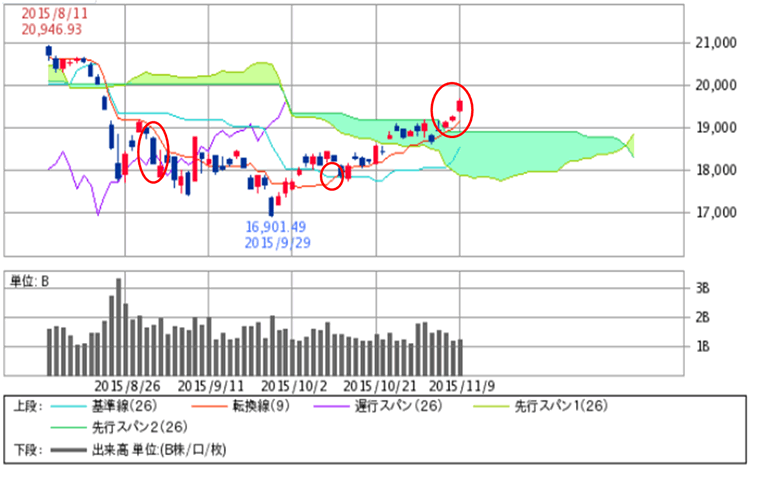
- ※当社WEBサイトを通じて、SBI証券が作成
重要日程を次々と通過 |
今後の日経平均株価の方向感を占う意味で、ここでは主要タイムスケジュール(表1)をチェックしておきたいと思います。雇用統計の発表後ですので、重要日程は少なめです。
11月第2週は、2015年7〜9月期決算発表の実質的な最終週になります。11/13に327社の決算発表が実施されますが、第一生命や3メガバンクの発表も予定されています。決算発表シーズンの間は積極的な売買を控える機関投資家も少なくないとみられ、「シーズン」終了後に一部の機関投資家の売買が積極化してくる可能性に注意したいと思います。その意味では、11/13にオプションSQを通過してくるというスケジュールも重要です。
11/16には2015年7〜9月期のGDP速報が発表の予定になっています。11/6現在では、前期比・年率-0.3%と、2四半期連続のマイナス成長が予想されています。
図2から読み取れるように、2015年3月期・本決算発表時(4月下旬〜5月半ば)に上昇した日経平均予想EPSは、その後伸び悩みとなっています。今回の7〜9月期決算発表の時期(10月下旬以降)になっても伸び悩んでいるということは、足元で企業の業績予想上方修正ペースが鈍っていることを反映しているとみられます。仮に7〜9月期のGDPが市場予想通り2四半期連続のマイナスとなるのであれば、景気・企業業績自体は、日経平均をさらに持ち上げる材料になりにくいと考えられます。
ただ、景気・企業業績が伸び悩む要因となったのは、中国等の新興国経済の減速とみられます。そのことはいったん株価に織り込まれつつあるうえ、追加金融緩和や「一人っ子政策の廃止」等、徐々に政策対応も行われています。過度の懸念は不要かと思われます。
表1:主要タイムスケジュール〜決算発表一巡へ
| 月日 | 曜日 | スケジュール | ポイント・注意点 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 火 | 10月の中国消費者物価指数 | |
| 11/11 | 水 | 中国の固定資産投資 11月の工作機械受注(速報) |
中国の設備投資の勢いは? |
| 11/12 | 木 | 9月の機械受注・10〜12月期同見通し 米新規失業保険申請件数 |
日本の設備投資の先行きを占う 米国経済の減速感を示す? |
| 11/13 | 金 | オプションSQ 決算発表が最後のヤマ場(327件)・発表一巡。 第一生命、3メガバンクなどが決算発表 |
機関投資家の姿勢に変化は? 日経平均の当面の予想EPSは? |
| 11/15 | 日 | G20首脳会議 | |
| 11/16 | 月 | 2015年7〜9月期GDP速報 | 2四半期連続のマイナスか? |
| 11/19 | 木 | 日銀金融政策決定会合結果発表 |
- ※各種報道等をもとにSBI証券が作成。
図2:日経平均株価(日足)と予想EPS
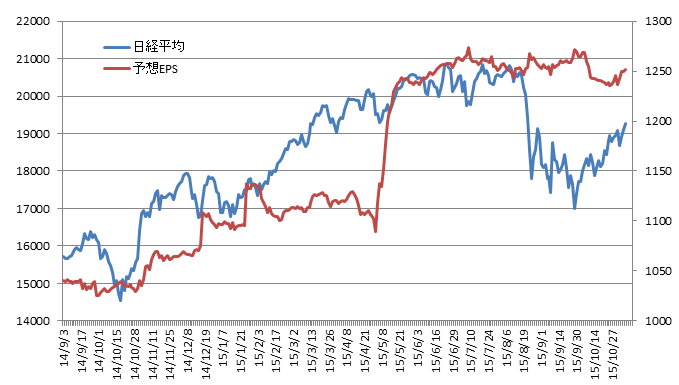
- ※日経平均公表データをもとに、SBI証券が作成(2015/11/6現在)。
【ココがPOINT!】年末に向け追い風強まり、日経平均株価は年初来高値トライも |
日経平均株価は今後も堅調に推移し、年末までに年初来高値20,868円(6/24)を更新しても不思議ではないとみられます。
これまでご説明してきたことを整理する形でその理由を羅列すると以下のようになります。
(1)中国など新興国経済への不透明感が一巡したため。
(2)テクニカル的に相場の好転を示唆する材料が多いため。(代表例として一目均衡表の「三役好転」)
(3)「2015年最大のイベント」とされてきた郵政上場が「成功」し、市場の厚みが増したとみられるため。
(4)株式市場が米国の年内利上げをおおむね織り込んだとみられるため。
(5)決算発表等重要スケジュールが一巡してくる運びとなっているため。
さらに、心強い材料となりそうなのが、日経平均の「月別平均騰落率」に関するアノマリーです。図3にあるように、日経平均株価は8〜10月には上昇しにくく、11〜12月には上昇しやすい傾向があります。海外投資家の決算等がこれに絡んでいるとみられますが、確固たる理由はないのが現実です。近年でも、ブラックマンデー(87/10)やリーマンショック(08/9)など、不思議と8〜10月は歴史的な相場波乱の多い月で、11月以降は安定し、12月は大きめに上昇する傾向があります。
2015年の月間騰落率は8月-8.2%、9月-8.0%と、まさにそこまではアノマリー通りでしたが、10月は9.7%と例年よりも早めの立ち直りとなりました。仮に11月、12月とアノマリー通りの強い相場が期待できるのであれば、日経平均株価が年初来高値を回復するための、ひとつの支援材料になると考えられます。
図3:日経平均株価の月別平均騰落率(過去30年間の平均)
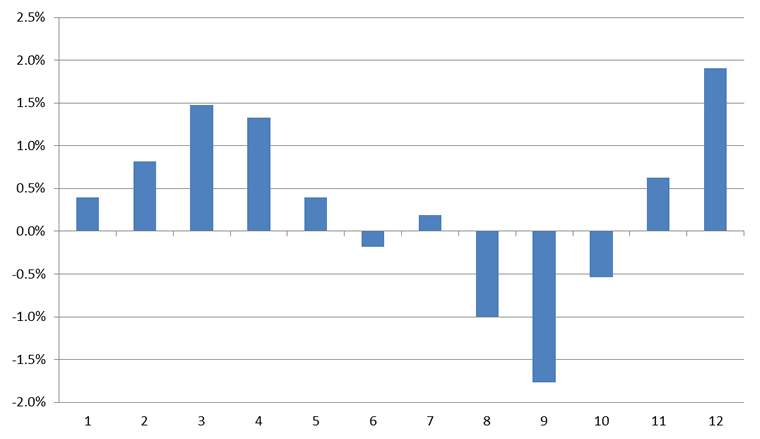
- ※Bloombergデータをもとに、SBI証券が作成(2015/11/9現在)
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
日経平均は20,000円を意識した展開になるか
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |