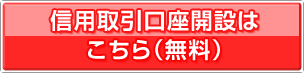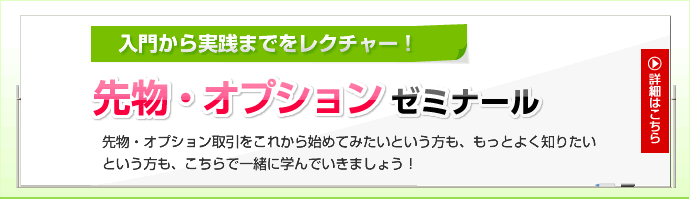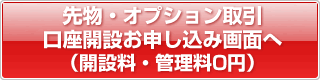東京株式市場は月末から来月はじめにかけ、重要日程が目白押しです。特に、日銀金融政策決定会合と決算発表のピークが重なる10/30は重要で、この日を境に株価が大きく変動する可能性があります。
日銀による追加緩和がなかった場合など、株価が下落する可能性もありますので注意が必要です。しかし、仮にそうした波乱があっても、株価の基調は崩れないと「225の『ココがPOINT!』」は考えています。なぜでしょうか。
日経平均が一時19,000円回復、そのワケは? |
日経平均株価は9/29安値16,901円を起点に上昇に転じ、10/26の取引時間中には8/31以来約2ヵ月ぶりに19,000円の大台を回復しました。
政策金利の年内引き上げ観測が後退した米国、次回のECB理事会で追加金融緩和を示唆した欧州、10/23に追加金融緩和を決めた中国と、世界的に緩和的金融政策の長期化につながるような動きが続いています。我が国でも10/30の金融政策決定会合で日銀による追加緩和が実施される可能性が指摘されています。
世界で緩和的金融政策が長期化すれば、投資環境として「リスクオン」の状態が継続すると期待されます。NYダウが9/29を「2番底」として反発に転じた他、10月に入ると世界の株式・為替市場の安定化が目立ってきました。それと月替り・期替り(下半期入り)でポジションを取りやすくなったことも手伝い、10月の日経平均株価は総じて堅調な動きとなりました。
それでも、一時は1万8千円台前半で保ち合っていた日経平均株価ですが、10/21には1万8千円台後半へと上放れ、冒頭の通り19,000円の大台を回復するに至りました。中国・新興国経済の減速を背景とする企業業績への懸念が後退し、好業績株が素直に買われる展開になってきたように思われます。
図1は、日経平均株価の日足チャートを主要移動平均とともに表示したものです。19,000円台への大台替りのみならず、75日移動平均(10/26現在19,147円)、200日移動平均(同19,173円)等も上値抵抗ラインとして機能しそうです。また図1には表示していませんが、現在、日経平均株価の「一目均衡表」では「クモの上限」が19,181円に位置しており、それも上値抵抗ラインとなりそうです。値幅的には、日経平均株価は下落幅(8/11〜9/29)の「2分の1戻し」が18,923円ですので、すでにそこを達成して短期的な達成感が強まりやすいタイミングでもあります。
テクニカル的には、日経平均株価はいつ反落しても不思議ではないタイミングと言えそうです。10/27の株価下落はその表れかもしれません。果たして、その通りに、株価下落は続いてしまうのでしょうか。それとも、切り返し、上値を追う展開になるのでしょうか。
図1:日経平均株価・日足〜75日移動・200日移動に接近
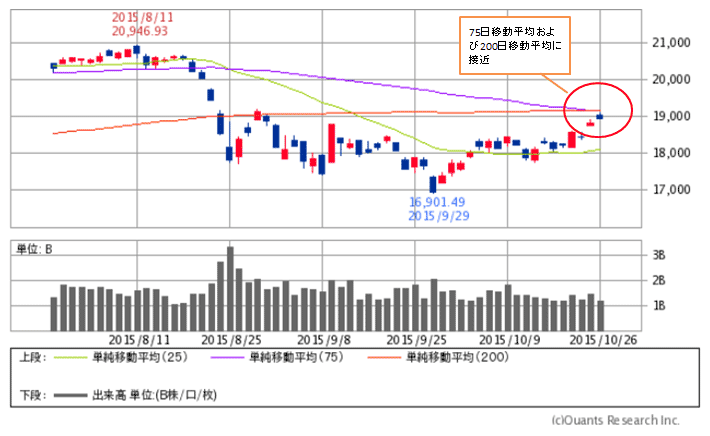
- ※当社チャートツールをもとに、SBI証券が作成(2015/10/26現在)。
月末にかけては相場の乱高下に注意 |
今後の日経平均株価の方向感を占う意味で、ここでは重要なタイムスケジュール(表1)をチェックしておきたいと思います。日米とも重要な日程が目白押しになっています。
米国については、まず10/29に金融政策を決定するFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表が予定されています。中央銀行に相当するFRB(米連邦準備制度理事会)がいつ政策金利を引き上げるのかが最大の焦点になっていますが、年内引き上げ観測が大きく後退している現状ですので、この会合では「現状維持」とする見方が大勢を占めています。また、市場の関心は、いったんは後退している年内利上げシナリオがそのまま後退するのか、再燃するのかにありますので、10/29の米GDP発表と11/6の雇用統計発表が改めて重要と言えます。
米国の7〜9月期GDP(前期比・年率)では、実質成長率が前四半期の+3.9%から+1.5%へ減速するというのが市場コンセンサス(Bloomberg・10/27現在)になっています。ドル高を背景とした輸出や設備投資の減速が響くとみられます。10月の雇用統計では非農業部門雇用者数が前月比17.9万人増と、8月(13.6万人増)・9月(14.2万人)に続き「20万人割れ」にとどまるというのが市場コンセンサス(同)になっています。緩和的金融政策の長期化が株価上昇につながってきた経緯を考えれば、これらの米経済指標については「予想通り」か「やや弱め」の数字がもっとも好感されやすい数字になると考えられます。
国内日程では10/30が非常に重要です。何か特別なスケジュールがなくとも、週末であり、月末でもあるため、ポジションが取りにくい日と考えられます。そこに加え、日銀の金融政策決定会合が予定されているうえ、決算発表についても500社超の発表が予定されていますので、十分注意が必要です。特に要注目の金融政策決定会合については、「追加緩和」予想と「現状維持」予想が拮抗(後者がやや多い程度)しているというのが市場コンセンサス(Bloomberg・10/27現在)になっています。いつものようにお昼頃の発表となりますが、「追加緩和」なら株価上昇、「現状維持」なら株価下落につながりやすいと考えられます。
さらに11/4には「郵政3社」の新規上場が予定されています。日本郵政(6178)、かんぽ生命(7181)、ゆうちょ銀行(7182)の株価が公開価格や初値を上回って推移できれば、株式市場に厚みが増すと期待されますので、その動向からは目が離せない展開となりそうです。
表1:主要タイムスケジュール〜10/30が特に重要か?
| 月日 | 曜日 | スケジュール | ポイント・注意点 |
|---|---|---|---|
| 10/27 | 火 | 東京市場10月相場・権利付最終日 米国9月の耐久財受注 |
米国の設備投資を占う重要指標 |
| 10/28 | 水 | 東京市場実質11月相場入り 決算発表(コマツ、日立、ANA他) |
|
| 10/29 | 木 | FOMC(連邦公開市場委員会)結果発表(日本時間未明) 決算発表(ソニー、パナソニック、新日鉄住金他) 米国7〜9月期GDP |
今回は「現状維持」の可能性 米国経済の減速感を示す? |
| 10/30 | 金 | 日銀金融政策決定会合結果発表 東京市場、決算発表が社数でピーク(504件) |
追加緩和はあるのか? |
| 11/1 | 日 | 中国10月の製造業PMI | |
| 11/3 | 火 | 東京株式市場は休場(文化の日) | |
| 11/4 | 水 | 東京市場に「郵政3社」が新規上場 米国10月のADP雇用統計 |
上場後の株価が市場の今後を左右 |
| 11/6 | 金 | 決算発表が後半のヤマ場(440件) 米国10月の雇用統計 |
米国経済の最新データ |
- ※報道等をもとに、SBI証券が作成(2015/10/26現在)
【ココがPOINT!】波乱の後、上昇相場「再始動」に備えよ!? |
前項でチェックした通り、当面は重要日程が目白押しになっていますが、10/30は最も重要であるといえるかもしれません。日本銀行の決定により、その日のうちに相場が大きく動く可能性があるためです。もし、追加緩和が実現されれば、内容にもよりますが、日経平均株価は一気に19,000円台を回復し、20,000円を目指す展開に転じる可能性もありそうです。
もし追加緩和がなく「現状維持」の場合は、株価下落の可能性があります。その場合、日経平均株価は18,000〜18,500円のレンジに押し戻される可能性があります。図3の一目均衡表で考えた場合、現在日経平均株価は「クモの中」にありますので、そこから押し戻された場合は、「クモの下限」を下回る可能性もありそうです。
このように、日銀の追加緩和がなかった場合、株式市場はネガティブな反応をみせそうですが、仮にそうなっても過度の懸念は不要であり、むしろ押し目買いチャンスになると「ココがPOINT!」では考えています。
理由は、前項でも触れたように、金融政策決定会合での「追加緩和」予想と「現状維持」予想は拮抗し、むしろ若干とはいえ「現状維持」派の方が多めなのが現実だからです。これらの市場参加者にとっては、「現状維持」という決定はネガティブなものに映らないため、株価下落はこれらの投資家の買い材料になる可能性があるためです。
日本は「脱デフレ」を実現しつつあるのか、「デフレ」に戻ろうとしているのか、物価の変動について考える場合、景気変動と関連性の薄い生鮮食品やエネルギー価格の動きを除いてみる見方が有力です。図2は、そうした見方に沿い消費者物価からエネルギーと生鮮食品の影響を除いたものです。これで見る限り「脱デフレ」は着実に進んでおり、追加緩和については慎重に考えるべきとの見方にも一理あることがわかります。
物価変動は賃金の変動と関係が深いと言われていますが、我が国では人手不足が深刻になり、賃金上昇圧力は強まる傾向にあるとみられます。その分、物価は下がりにくいと考えられます。
株式市場は、米国金融政策の端境期や、中国経済の体質転換(高成長から新常態へ)を織り込む過程で一時的に混乱したに過ぎず、その間、日本経済の「脱デフレ」は着実に進行していると考えられないでしょうか。日経平均はその分が過小評価されており、上昇トレンドは維持されている可能性が大きいと「ココがPOINT!」では考えています。
図2:全国消費者物価(食品・エネルギーを除く)
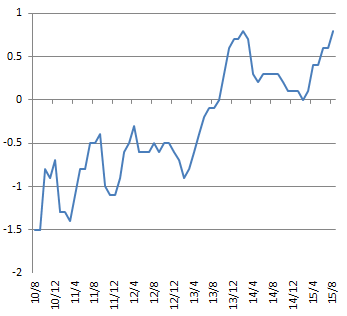
※Bloomberg、総務省データをもとにSBI証券が作成。
全国消費者物価の食品・エネルギーを除いた前年同月比増減率。消費税増税直後の2014/4からの1年間は、増税による物価押し上げ率を2%と仮定して差し引いた参考数値。
図3:日経平均株価・一目均衡表(日足)
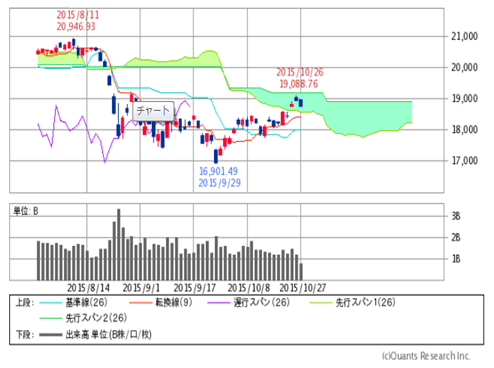
※当社チャート・ツールをもとにSBI証券が作成。
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
上昇は継続か?主要国政策の見極が必要
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |