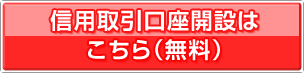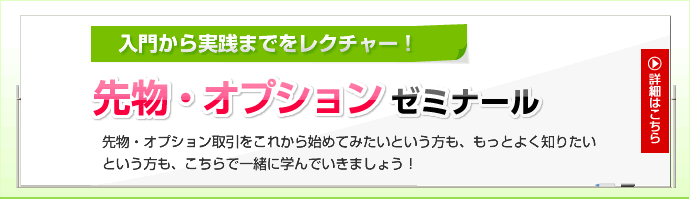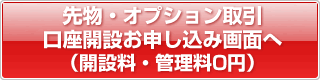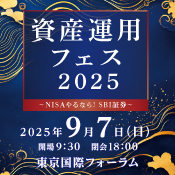9/29に一時17,000円を割り込んだ日経平均ですが、その後は反発に転じ、重要な節目である25日移動平均の水準を回復してきました。日経平均はここからさらに上昇するのでしょうか、戻り売りに押されてしまうのでしょうか。
今回の「225の『ココがPOINT!』」では、今後の日経平均株価の動きに大きな影響を与えるとみられる日米の金融政策を中心に、株価の刺激材料について考えてみたいと思います。市場で期待が高まっている日銀の追加緩和はあるのでしょうか。また、それがないと株価は再び下落してしまうでしょうか。
<目次>
9/29をボトムに反発に転じた日経平均 |
日経平均株価は8/11に高値20,946円を付けて以降9/29まで、下落基調となりました。この間の下落率は19.3%に達し、アベノミクス相場がはじまって以降では2013/5/23→同6/13の下落で記録したマイナス22.1%に次ぐ、大きな株価下落(図1)になりました。
しかし、日経平均株価は9/29が安値となり、その後は反発に転じました。理由は以下の3点であると考えられます。
(1)8月下旬以降下落基調にあったNY株が9/28を安値(終値ベース)に反発に転じたこと。
(2)日経平均の予想PERが下げ止まりやすい水準まで低下し、実際に下げ止まったこと。(図2)
(3)経済の先行きが心配される中国で、上海市場が10/1〜10/7に休場(国慶節)で、悪材料が出にくくなったこと。
このうち、(2)については図2にあるように、日経平均の予想PERが「アベノミクス相場」開始前夜の2012/11/13に付けた13.6倍の近辺に達すると下げ止まりやすいというパターンが形成されつつあるようです。
テクニカル的には、図1にもあるように日経平均株価が10/5終値段階で当面の株式相場の強弱感に影響する「25日移動平均」を上回ってきました。株価がこうした重要な節目を突破してきたことで、今後は短期筋の戻り売りが出やすくなると想定されます。また、10/8以降は中国・上海市場が取引再開となり、市場の関心がそちらに向く可能性もありそうです。しかし、この水準をある程度維持できれば、日経平均が19,000円や20,000円に向けて上昇していくシナリオも描きやすくなります。
そこで今回の「225の『ココがPOINT!』」では、今後の日経平均株価の動きに大きな影響を与えるとみられる日米の金融政策を中心に、株価の刺激材料について考えてみたいと思います。市場で期待が高まっている日銀の追加緩和はあるのでしょうか。また、それがないと株価は再び下落してしまうでしょうか。
図1:反発に転じた日経平均株価(日足)
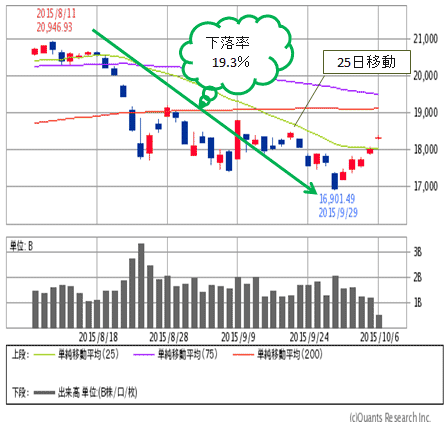
- ※当社チャートツールをもとに、SBI証券が作成(2015/10/6現在)
図2:PER13倍台前半で下げ止まった日経平均株価
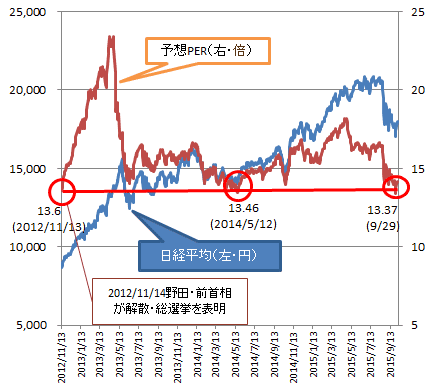
- ※日経平均データをもとに、SBI証券が作成(2015/10/6現在)。
FRBと市場の対話が続く米国市場〜「利上げ」は市場の納得したタイミングで? |
10/2に米労働省から、2015年9月の雇用統計が発表されました。非農業部門雇用者数が市場予想ほどに増えなかった上、過去データも下方修正され、労働市場からの退出も増えるなど、最近にしては悪い数字になりました。
しかし、発表後の10/2(現地時間)の米国市場では、ダウ平均が一時下落したものの、結局は前日比200ドル高と大幅高になりました。休み明けの10/5には304ドル高と続伸し、ダウ平均は一気に終値ベースで8/20以来の高値を回復してきました。雇用統計の結果に対するNY株式市場の反応は、市場がその時何を望んでいるのかにより異なるとみられます。世界的に景気に対する不透明感が強まる中では、雇用統計の結果が強く、FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げが確実になった方が株価は上昇すると考えていた向きも多かったはずです。それゆえ、10/2のNY株高はやや意外でした。
現地の空気を伝えるレポートなどを読むと、どうもウォール街はまだまだ、利上げ後の株式市場の方向性に自信を持てていないようです。過去最大の金融緩和をやめた後に起こる変化は、やはり相当大きなものになるという警戒心が強いようです。もし、そうであるならば、FRBはまだまだ市場と「対話」を続けなければならないと考えられます。市場参加者の多くが、利上げしても米国経済の基盤は動揺しないと思えるようになれば、FRBも利上げがしやすくなると考えられます。逆に、米国経済はまだ弱さを抱えており、今週からはじまる決算発表にも要注意であると考えられます。
NYダウは7/20の高値18,137ドルから8/24の安値15,370ドルまでの下落幅に対し、半値戻しの水準である16,753ドルを回復してきています(図3)。また、ザラ場ベースでは9/17の高値16,933ドルが上値抵抗ラインになります。NY市場についてはそろそろ、上昇速度が鈍化してくる可能性に注意したいところです。
図3:7/20以降の下落相場に対し「半値戻し」水準まで回復したNYダウ(日足)
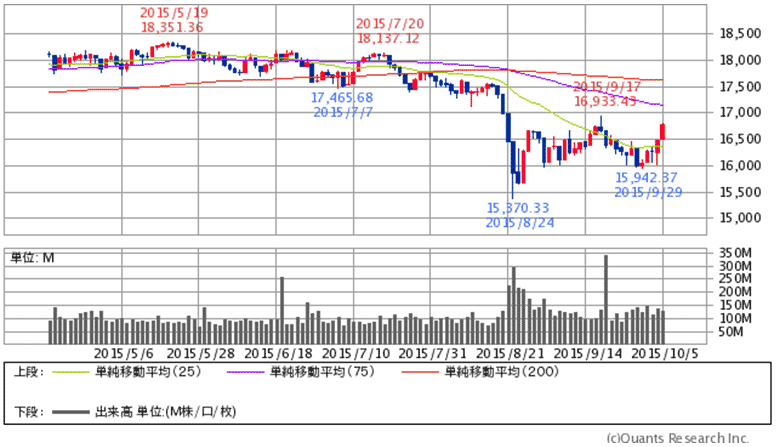
- ※当社チャートツールをもとに、SBI証券が作成(現地時間2015/10/5現在)。
【ココがPOINT!】日銀の追加緩和はあるのか?実現ならば短期に日経平均が2万円回復も |
(1)でご説明した通り、日経平均株価は重要な節目の株価まで回復してきました。今後、さらに上昇していくためには、中国株安に象徴される新興国経済への不透明感が緩和し、日本経済のさらなる回復に対し、市場参加者がさらに自信を持つ必要があると考えられます。
しかし、図4の鉱工業生産が示しているように、景気はやや踊り場の様相を呈しています。リーマンショック前の水準で頭打ちとなり、足元はむしろ低下傾向です。市場の一部では、前期比マイナス1.2%(年率)に終わった4〜6月期に続き、我が国の経済成長率は「2015年7〜9月期もマイナスになる可能性がある」との悲観論も台頭しています。図5にもあるように、中心的な物価指標である全国消費者物価指数(生鮮食品を除く)は、前年同期比でマイナスに転じています。安倍内閣や日銀が目指す「脱デフレ」には黄色信号が灯っていると言えるかもしれません。
こうした中、日銀による追加緩和の可能性が高まってきたと考えられます。購入額が残り少ないETF購入額の引き上げなどが有効との見方もあります。Bloomberg調べでは36人中、10/7に結果を発表する日銀金融政策決定会合で追加緩和を予想する市場参加者は2人とさすがに少数派です。しかし、10/30の会合では15人の市場参加者が追加緩和を予想しています。
仮に追加緩和が発表されれば、日経平均は一気に上昇する可能性もあるので注意が必要です。特に、10/7に追加緩和が実施された場合は意外感が伴うため、株価の上昇が急になる可能性があります。仮に10/7の追加緩和がなくても、市場の期待の中心は10/30の金融政策決定会合にあるため、大きな混乱はなさそうです。
そもそも、10/5に「TPP基本合意へ」と伝えられ、同じ日から「マイナンバー法」が施行されている点は重要です。TPP締結はアベノミクスの中でも重要事項で、我が国の中長期的な経済成長に貢献すると考えられています。また「マイナンバー」も、単純に財政の問題にとどまらず、相当なシステム更新需要を伴う景気対策の側面もあり、恩恵を受ける企業も多そうです。
9/29に底入れして以降の日経平均は、海外からの追い風こそあまり期待できないものの、国内には株価を刺激しやすい材料が多く、当面は株価の戻りが続くと考えてもよいのではないでしょうか。
図4:生産活動の伸び悩みを示す鉱工業生産
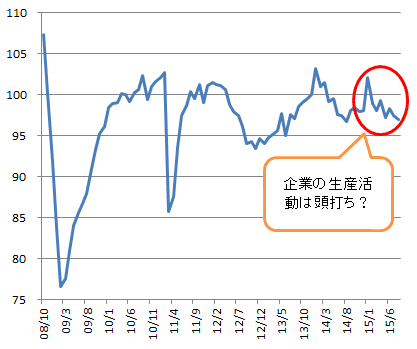
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。季節調整済み指数。
図5:コア指数ではマイナスに転じた消費者物価指数
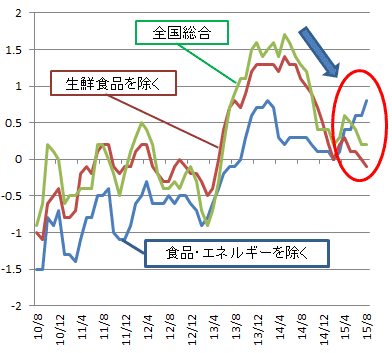
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。各指数の前年同月比増減率(%)。なお、2014/4〜2015/3は消費増税影響分を2%として差し引いている。
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
日経平均はサプライズ上昇に注意?