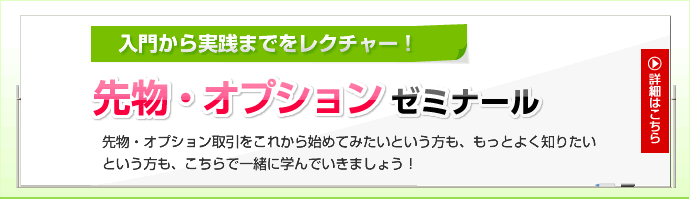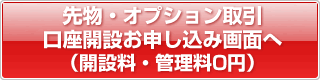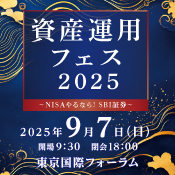日経平均株価は4月10日取引時間中に20,000円を付け、22日には終値でも大台を回復、23日には20,252円12銭の高値を実現しました。しかし、その後は下落に転じています。5月7日には19,257円まで下げ、日経平均の高値からの下落幅は、一時1,000円に迫る形となりました。
その後、米雇用統計の改善を受ける形で5月11日には大幅高となり、日経平均株価は落ち着きを取り戻しつつあるように見えます。ただ、チャートを見る限りでは、短期的な相場の強弱感を示すとみられる25日移動平均(11日現在19,718円)すら回復しておらず、引き続き「調整局面」のようにみえます。
ただ、それでも日経平均株価は早ければ5月中旬以降にも、本格的な反転に転じる可能性が十分あると考えられます。今回の「ココがポイント」では、その理由を考えてみたいと思います。
|
|
株価下落をもたらした要因を整理する |
冒頭でご説明したように、日経平均株価は一時、高値から1,000円近い下げとなりました。理由は大きく3つに分けられます。
(1)低調な米景気・企業業績。
(2)債券市場の波乱、ギリシャ問題の深刻化など、欧州発の不透明要因。
(3)決算発表本格化、大型連休シーズン到来など、投資タイミングの問題。
(1)については、3月の雇用統計で雇用者数が下振れた他、住宅、消費、設備投資など主要分野で経済指標の下振れが目立ち、米国経済への不透明感が強まりました。こうした中、4月中旬から発表が本格化した米1〜3月期企業業績では、国際企業等でドル高の悪影響が表面化し、市場の懸念を裏付ける形になりました。
(2)については、3月からECB(欧州中銀)による国債買い入れがスタートしたことを受け、主要国の国債に対する買い安心感が強まり、ドイツ10年国債利回りが一時年0.1%を下回るような場面が出現しました。こうした流れを背景に、円高・ユーロ安が進み、4月27日までは1ドル130円を下回るユーロ安・円高局面が続きました。しかし、その後はドイツ10年国債利回りは、0.6%台まで戻るという荒っぽい展開となり、為替もユーロ高・円安方向に戻りました。こうした中、上昇を続けてきた欧州株が下落に転じるなど、欧州債券、為替、株式市場は不安定な展開となりました。なお、ギリシャ問題については、5月11日のECB理事会で、同国が有効な対応策を打ち出せるか否か、注目されました。
(3)4月23日に高値を付けて以降、日経平均は4月30日に538円安、5月7日に239円安で取引を終え大きな波乱になりました。決算発表の本格化で様子見気分が強まったことが一因です。これに加え、4月30日は月末で、かつ大型連休直前という非常にポジションを取りにくいタイミングになったことも下げを加速させる要因になりました。5月7日も、決算発表ピーク及び米雇用統計発表、オプションSQ等の重要日程がすべて8日に集中していたことで、投資家の買い手控え姿勢を強めさせる要因になりました。
図表1:25日移動平均を割り込み、そこが逆に「上値抵抗ライン」に変わってしまった日経平均
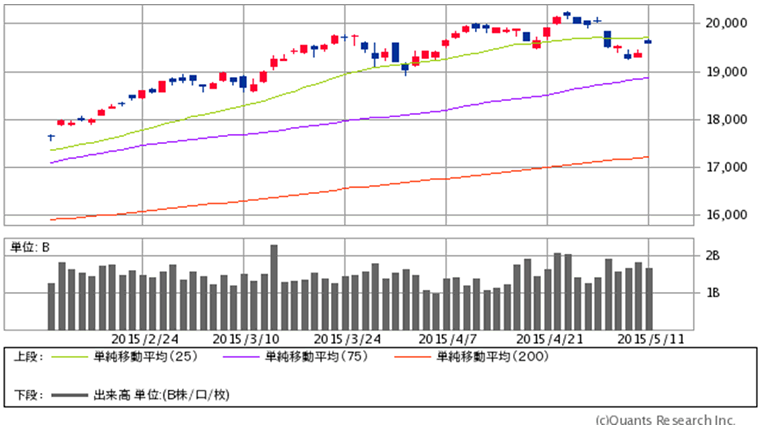
- ※弊社チャートツールもとにSBI証券が作成。
|
|
「日経平均株価の本格的反騰」を促す要因 |
前項で述べたように、日経平均株価は主に3つの要因を背景に下落しました。しかし、これだけ悪材料が並んだにもかかわらず、平均株価の下落率が5%にとどまっていることに、逆に相場の力強さを感じている市場参加者も多いのではないでしょうか。「ココがポイント」でも、日経平均株価は早ければ5月中旬以降、本格的反騰に転じる可能性があるとみています。
理由は、前項で述べた「悪材料」の多くが好転すると考えられるからです。
(1)で示した米国経済の問題については、早くも、8日に発表された雇用統計(4月分)で、非農業部門雇用者増加数が20万人台を回復しました。もともと、この冬は米国が歴史的な寒波に見舞われたという経緯があり、それが米国の各部門に多くの悪材料を及ぼしたという側面があります。厳しい冬が終われば、雇用や消費が回復してくる可能性が膨らんできます。また、企業業績については、市場の予想が悲観的過ぎた部分もあるようです。4月上旬の段階では、S&P500採用企業の同四半期純利益は前年同期比5%程度の減益になる見込み(市場コンセンサス)でしたが、現状では横ばいから微増益程度に上振れています。ドル高や原油安のメリット部分があまり織り込まれていなかったようです。なお、市場コンセンサス(Bloomberg)では、米国の実質GDP成長率(前期比・年率)は、1〜3月期+0.2%から、4〜6月は同+3.1%に回復する見通しです。
(2)欧州問題については、長期国債利回りの乱高下があったものの、同様の現象は、量的緩和導入後の日本でも見られたことを想起すべきとみられます。ECBによる国債買い入れは、2016年9月まで実施される予定であり、むしろまだ、実施が始まったばかりです。インフレの兆候が特に強まった訳ではなく、過度の懸念は不要ではないでしょうか。
(3)我が国の市場独自の要因については、既に連休が終わったことに加え、20日までには本決算の発表が終了しますので、買いポジションを取りにくくしている季節要因的な要素は次第に改善してくるとみられます。ちなみに、2014年のケースでは、日経平均株価は4月21日14,649円から5月21日13,964円まで、やはり5%弱下落した後に上昇しています。年金の株式組入れが進捗した現状と昨年を単純に比較することはできないですが、中長期的な視点で銘柄を選択する投資家が「決算発表終了」で、動き出してくる可能性は十分ありそうです。
なお、(2)の問題の中で、ギリシャ問題については、同国の短期的な資金繰り問題が12日のIMFへの返済でヒト山越すため、市場の不安は多少後退しそうです。ただ、同国の「自転車操業」が続いていることに変化はなく、追加支援策のとりまとめ交渉への市場の関心も続きそうです。ただ、本質的には、ユーロ圏(GDP13兆ドル)に占める規模は2%(2014年・IMF調べ)にも満たないことに加え、民間銀行による同国への融資額も限定的となっています。仮にギリシャがデフォルトした場合でも、「心理的連鎖の不安」を除けば、実質的な悪影響は限られた範囲内にとどまると考えられます。
|
|
【225のココがポイント!】「日経平均予想EPS」がピークを更新! |
株価は、基本的に企業業績の変化を織り込んで動いていると考えられます。日経平均株価は、採用銘柄225社の業績を織り込んで動いているとみられます。図表2は、日経平均株価とその予想EPS(一株利益)の推移を示したものですが、株価は予想EPSの増加とともに、上昇してきたことがわかります。
最初の項目では、日経平均の下落をもたらした3つの要因について触れました。前項では、それらの要因が回復に向かうことで、日経平均株価が上昇する可能性について触れました。これらのうち、投資タイミングの側面を除けば、米国株の件も、欧州経済の問題も、最終的には、日経平均予想EPSにどのような影響を与えるかという観点で整理し直すことができます。
こうした中、日経平均の予想EPSが1月下旬の水準(1,137円)を抜き、1,152円まで上昇してきました。アベノミクス相場では最も高い水準です。決算発表が進捗し、主力の3月決算企業では「予想」の対象が2015年3月期から2016年3月期に変わりつつありますが、トヨタの決算発表も終わり、予想EPSの大勢も2016年3月期に変わっています。即ち、予想EPSの上昇は、今期の企業業績の拡大見通しを織り込んでいると考えられます。
1月26日以降に、予想EPSが伸び悩んだ背景には、原油・エネルギー価格下落が企業業績に与える陰の部分が先行して織り込まれ、商社や石油元売り等で業績予想の下方修正が増えたことが大きく影響しています。しかし、原油価格は既に下げ止まりの様相を強め、今後は原油・エネルギー価格下落の陽の部分が影響してくるとみられます。また、消費増税から1年が経過し、個人消費への逆風も弱まりそうです。日経平均株価の予想EPSは今後も基本的には上昇基調を辿り、日経平均の上昇にとり、強い追い風になると予想されます。
図表2:1月下旬のピークを超してきた「日経平均予想EPS」
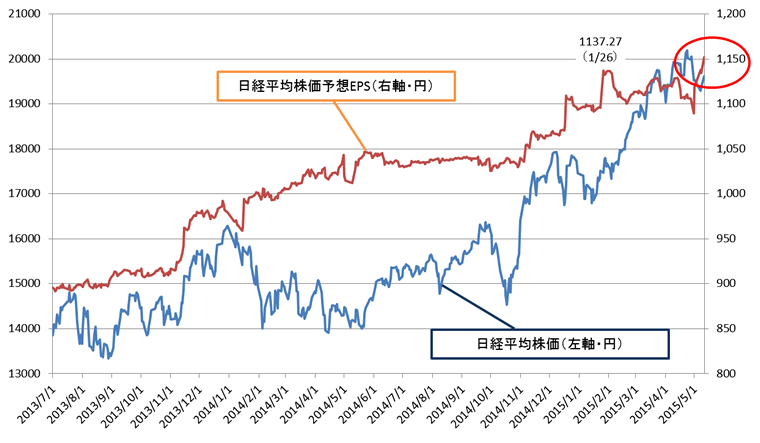
- ※日経平均株価データをもとにSBI証券が作成。
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
先物・オプションの関連コンテンツ
サキモノのココがPOINT!
![]() 日経平均は25日線を上回って推移できるかがポイント
日経平均は25日線を上回って推移できるかがポイント