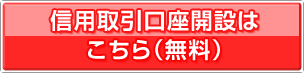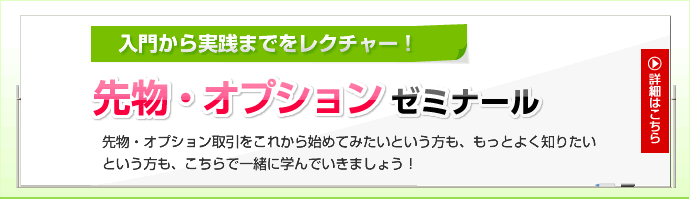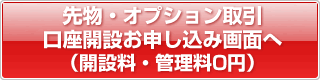日経平均株価は英国民投票でEU離脱派が勝利した6/24(金)の安値14,952円を起点に、8/12(金)には16,943円まで値を回復しました。6/1(水)以来の17,000円台回復はもう目前の位置にあります。ただ、日経平均株価の上昇は目先いったん小休止になるかもしれません。円高圧力が根強いことや仮に17,000円を超えても、数多くの上値抵抗ラインがあるためです。
しかし、やや中期的に考えると、株価の上昇余地はまだ大きいと考えられます。日米欧で債券市場のピークアウトが意識され始め、金利リスクを勘案した国際的な金融規制への対応が求められる中、株式市場への資金シフトが進む可能性が大きいためです。夏場の閑散相場は、実は投資家に買い場を提供しているのかもしれません。
目先いったん小休止になる可能性も |
日経平均株価は英国民投票でEU離脱派が勝利した6/24(金)の安値14,952円を起点に、8/12(金)には16,943円まで値を回復しました。日経平均株価は2015/6/24に20,954円の高値を付けていますので、ちょうど下落相場が1年続いた形になります。1年かけて6,087円(29%)下がり、そのうち1,991円(下げ幅の3分の1弱)分を回復した形になります。
テクニカル分析上の「3分の1戻し」をほぼ達成したことや、外為市場で円高圧力が根強いこと、17,000円を超えても、数多くの上値抵抗ライン(※)があること等を背景に、日経平均株価の上昇は目先いったん小休止になるかもしれません。図1はここ3ヵ月の日経平均株価の推移を示したものですが、7/21(木)の高値を抜け切れていない感じもします。
しかし、やや中期的に考えると、株価の上昇余地はまだ大きいと考えられます。日米欧で債券市場のピークアウトが意識され始め、金利リスクを勘案した国際的な金融規制への対応が求められる中、株式市場への資金シフトが進む可能性が大きいためです。夏場の閑散相場は、実は投資家に買い場を提供しているのかもしれません。
※17,000円台にある日経平均株価の各種抵抗ライン
(1)17,251円・・・・・5/31(火)に付けた当面の高値
(2)17,454円・・・・・日経平均の予想EPS1,205円83銭(8/15)に予想PER14.5倍をかけた水準
(3)17,613円・・・・・4/25(月)に付けた当面の高値
(4)17,905円・・・・・2/1(月)に付けた当面の高値
図1:日経平均株価(日足)〜7/21(木)高値を抜き切れていないが・・・
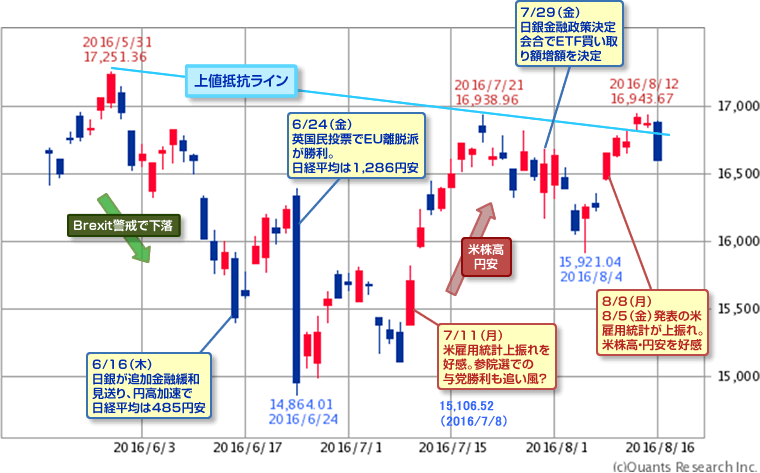
- ※当社チャートツールをもとにSBI証券が作成。データは2016/8/16終値。
図2はドル・円相場(日足)の動きです。引き続き円高圧力の強い状態が続いています。前回の「225の『ココがPOINT!』」でもご説明したように、日本の10年国債利回りは7/27(水)には-0.295%でしたが、8/2(火)に-0.025%となるなど長期金利が「急上昇」したことが大きな要因と考えられます。日本の長期金利の上昇は、日米金利差(米国の金利から日本の金利を差し引いた数値)の縮小要因になりますので、円高・ドル安要因になります。
ただ、大きな懸念は不要と考えられます。図3にもありますように、今後の株式相場の変動の大きさを示唆する日経平均VI指数(ここでは先物)が低下しているためです。市場は当面大きな波乱が起こる可能性は小さいと「予想」しているので「リスク回避の円高」の部分は想定しにくいためです。少なくとも、市場に大きなインパクトを与えるスケジュールは少なく、むしろ材料面での「夏枯れ」が心配されるくらいです。
図2:ドル・円相場(日足)・過去3ヵ月

図3:日経平均VI先物(週足)・過去2年
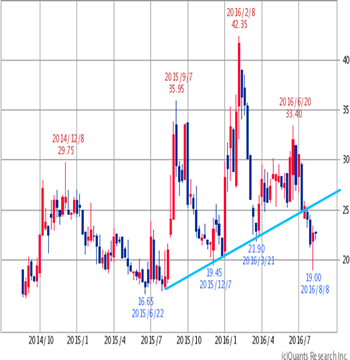
- ※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。データは2016/8/15現在。
当面のタイムスケジュール〜9月の日米中央銀行会議を意識 |
当面のタイムスケジュールについては表1でご紹介した通りです。日米とも4〜6月期の決算発表が一巡した後で特に重要な指標の発表は少ないといえます。上記したように材料面での「夏枯れ」になりやすい時期になっています。
なお、金融政策を決定する中央銀行会議について日米の予定(日銀金融政策決定会合、FOMC)を別途表示しております。もっとも近い会合は日米ともに9/21(水)になっています。我が国では金融政策の「総括的再検証」が実施される予定ですが、それと併せて追加金融緩和があるとの見方が有力です。また、米国では少数にとどまるもののエコノミストの何人かが政策金利の再引き上げを見込んでいます。どちらとも、金融政策の変更があり得るだけに、これらの会合が接近するにつれ、さまざまな思惑が市場で交錯してくる可能性が大きそうです。
当面は9/21(水)に向けて各種経済指標をひとつひとつチェックしていくことになりそうです。無論、米国については毎週木曜日(米国時間)に発表される週次の新規失業保険申請件数や、8/26(金)のジャクソンホールにおけるイエレンFRB議長の講演、9/2(金)の雇用統計(8月)等も見逃すことはできないスケジュールであると考えられます。
表1:当面の重要なタイムスケジュール/決算発表は8/12まででおおむね一巡
月日(曜日) |
国・地域 |
予定内容 |
ポイント |
|---|---|---|---|
8/16(火) |
独 |
8月ZEW景況感指数 |
アナリストや機関投資家、市場関係者など約350人を対象としたアンケート |
米国 |
7月消費者物価(食品・エネルギーを除く) |
6月0.2%(前月比)→7月予想0.2%(同) |
|
米国 |
7月鉱工業生産・設備稼働率 |
6月0.6%(前月比)→7月予想0.3%(同) |
|
米国 |
7月住宅着工 |
6月4.8%(前月比)→7月予想-0.8%(同) |
|
8/17(水) |
日本 |
7月訪日外客数 |
前年同月比増加率は4月18.6%、5月15.3%、6月は23.9%増で推移 |
日本 |
7月日本製半導体製造装置BBレシオ |
6月はBBレシオ(受注額/販売額)が1.33。受注は前年比11.5%と好調 |
|
米国 |
FOMC(7/26〜27)議事録 |
||
米国 |
◎決算 |
シスコシステムズ |
|
8/18(木) |
米国 |
8月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数 |
製造業の景況感についてコンセンサスを形成 |
米国 |
7月コンファレンスボード景気先行総合指数 |
||
米国 |
◎決算 |
ウォルマート・ストアーズ、アプライド・マテリアルズ |
|
8/22(月) |
日本 |
7月コンビニエンスストア売上高 |
|
8/23(火) |
米国 |
7月新築住宅販売件 |
6月3.5%(前月比)→7月予想-2.9%(同) |
米国 |
7月北米半導体BBレシオ |
||
8/24(水) |
米国 |
米6月FHFA住宅価格指数 |
FHFA(米国連邦住宅金融庁)から公表。信用力の高い物件で構成 |
米国 |
米7月中古住宅販売件数 |
6月0.1%(前月比)→7月予想1.1%(同) |
|
8/25(木) |
独 |
8月Ifo景況感指数 |
ドイツ企業7,000社にアンケート |
米国 |
7月耐久財受注 |
米設備投資の先行指標 |
|
8/26(金) |
日本 |
8月決算銘柄が権利付最終日 |
株主優待で投資家の関心が強い小売企業を多く含む |
英国 |
4〜6月期GDP改定値 |
||
米国 |
4〜6月期GDP改定値 |
前期比年率1.1%成長の予想 |
|
米国 |
ジャクソンホールでイエレンFRB議長講演 |
ワイオミング州ジャクソンホール(地名)で開かれる年次経済シンポジウム |
表2:日米中央銀行会議の結果発表予定日
|
2016年 |
2017年 |
|---|---|---|
日銀金融政策決定会合 |
9/21(水)、11/1(火)、12/20(火) |
1/31(火)、3/16(木)、4/27(木) |
FOMC(米連邦公開市場委員会) |
9/21(水)、11/2(水)、12/14(水) |
2/1(水)、3/15(水) |
各種報道等をもとにSBI証券が作成。「予想」は市場コンセンサス。データは2016/8/15現在。予定は予告なく変更される場合がありますので、あくまでもデータ作成段階のものです。
【ココがPOINT!】「債券から株式」への資金シフトも |
長期金利の代表的な「指標」である10年国債利回りは日米独という主要3国でボトムアウトの兆しが出てきています。マイナス金利に突っ込んだ日独については、ECB(欧州中銀)が追加利下げに否定的な見方を示し、日本では銀行が反対意見を表明するなど否定的な見方が広がっています。また、米国ではすでに2015/12から政策金利が引き上げの局面になっていますので、その時よりも下がっている長期金利は「異常値」と考えられ、先行き「修正」される可能性がありそうです。
こうした中、2018年より銀行の国債保有について国際的な規制が強化される方向になっています。これまで、銀行が保有する国債は基本的に「リスクフリー」でしたが、今後は金利変動による自己資本への影響に十分配慮することが求められることになりそうです。我が国では7/15(金)に、大手銀行が国債市場特別参加者制度(日本版プライマリー・ディーラー)への参加者資格を返上するという出来事がありましたが、その判断材料のひとつとして「金利変動リスク」が考慮された可能性があります。
3年ほど前に比べ国内銀行の国債保有額は4割ほど減少しましたが、それでも約100兆円あります。ゆうちょ銀行も同様に減らしたとはいえ80兆円弱の国債を抱えています。今後、国際的な規制の強化を控え、さらに国債保有額を減らす可能性がありそうです。我が国では日銀が金融機関から売却される国債を買い入れる形で緩和的金融政策を行っており、銀行の国債売りで相場が崩れる可能性は小さいとみられます。しかし、市場の流動性は低下していますので、何かのショックで金利が急上昇のリスクは逆に膨らんでいると考えられます。
こうした事情は米国やドイツなども似ていると考えられます。米国では債券市場から株式市場への資金シフトが起こりつつあるとの観測も出ています。世界的に債券市場から資金が流出し、その一部が株式市場に流入してくる可能性は十分あります。投資家としてもそろそろ、こうした動きに備えたいところです。
図5は米10年国債利回りと日経平均株価の動きを重ねたものです。一般的には、米10年国債利回りが下がると円高・ドル安になりやすく、日経平均株価も下がりやすくなります。ただ、2015年半ばごろまでは、日銀金融緩和への期待が強く、米国債利回りの低下を吸収してきた面があります。日銀の追加金融緩和について限界視する向きが増えてきた現在は、米国債利回りの低下が日経平均の下落に「直結」してしまっている形です。逆に、米金利が底打ちし、上昇に転じてくれば、日経平均株価の上昇も本格的になる可能性があります。
図4:日米欧の10年国債利回り(%)
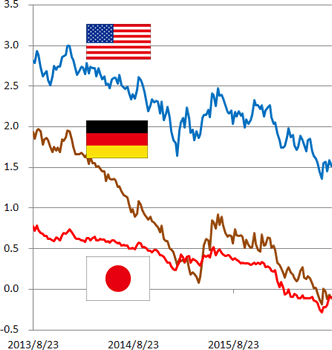
図5:米10年国債利回り(%)と日経平均株価(円)
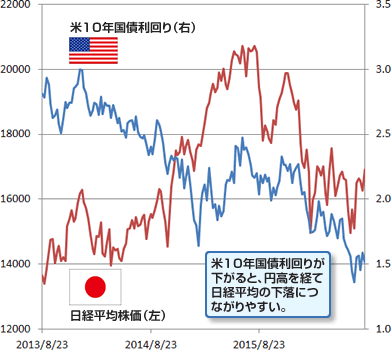
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
緩和期待高まれば17,000円台回復が視野に
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |