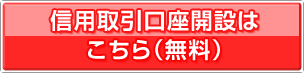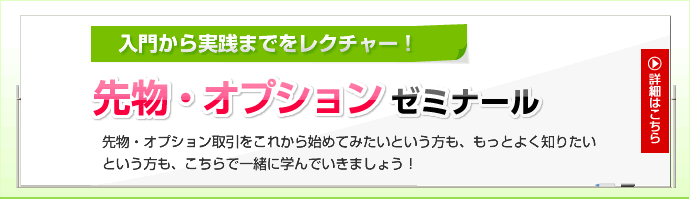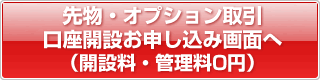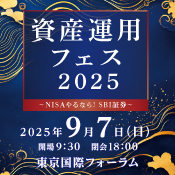中国経済への不安が後退したことや郵政上場の成功等を背景に、日経平均株価の上昇基調が続いています。テロへの不安は残りますが、本質的には、金融政策の変更を控えた米国経済の動向が今後の要注目点となりそうです。
こうした中、中間決算発表を経て、企業業績の拡大も維持されたことから、日経平均株価は再び高値トライの可能性が強まりそうです。短期的な過熱感を乗り越えることができれば、日経平均株価は再び21,000円近辺の株価水準を回復することができると考えられます。
徐々に上値を切り上げてきた日経平均株価 |
日経平均株価は徐々に上値を切り上げる展開になっています。
中国経済の減速感は強いものの、同国の株価は安定しており、投資家の不安感は後退しています。国内では、成功裏に終わった郵政上場が株式市場で投資家のリスクオン姿勢への回帰を後押ししているように見受けられます。そうした中、11/13にフランス・パリで起きた同時多発テロを警戒し、11/16の日経平均株価が最大350円下げるという波乱がありました。しかし、欧米市場が波乱にならなかったことを好感して11/17には大幅反発となり、前日の下げ分(203円)をすべて取り返す236円高になりました。11/19には、前日の米株高を受ける形で日経平均株価も再び大幅高し、一時20,000円大台にあと40円まで迫る場面もみられました。
なお、日経平均株価は11/5〜11/16に、終値が始値を上回る「陽線」が8営業日連続で続くという珍しい記録(終値が前日比で上昇する日が8営業日続く8営業日続伸とは異なる)を作りました。これは、取引開始後も断続的に買いが継続する日が続かないと達成できない記録であり、ある意味では「8営業日続伸」以上に地合い(相場の状況・雰囲気)の強さを印象付ける出来事となりました。海外投資家の買い越し(11/13終了の週まで4週連続)や、郵政上場成功による投資家心理の好転・需給の改善が、こうした現象の背景と考えられます。
ちなみに、11/13のパリにおけるテロ発生以降、テロの恐怖が隣国のベルギーに伝搬する兆しをみせるなど、今回のテロ不安が解消した訳ではありません。ただ、もともとテロの恐怖は日々絶えないのが現実で、株価への影響という意味では「忘れた時」の方がより怖いのかもしれません。2001年のNY同時多発テロの時同様、テロに屈しない愛国主義的な買いが入りやすいのも、こうした時の市場の特性で、今回も現状をみる限りでは、その通りとなり、株価を支えているように思われます。
図1:徐々に上値を切り上げてきた日経平均株価(日足)
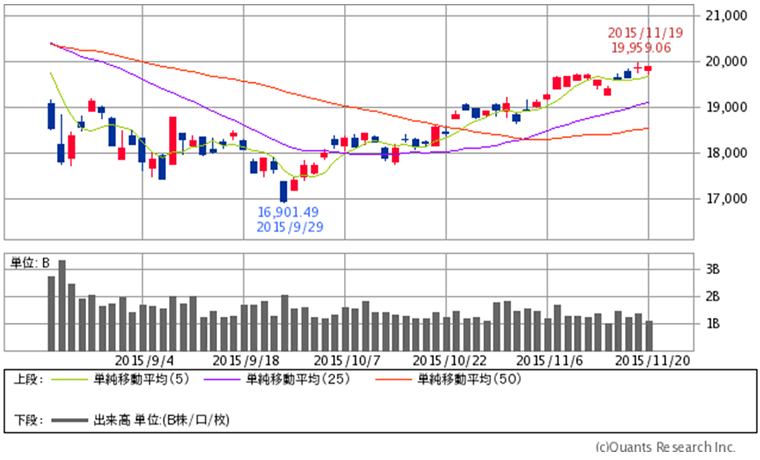
- ※当社WEBサイトを通じて、SBI証券が作成。2015/11/20現在。
12/4発表の米雇用統計に向け、米国経済をウォッチすべき期間に |
今後の日経平均株価の方向感を占う意味で、ここでは重要なタイムスケジュール(表1)をチェックしておきたいと思います。
もっとも重要なタイムスケジュールとしては、少々先になりますが12/4(金)の米雇用統計(11月)になると考えられます。株式市場では主要指標である非農業部門雇用者数について、前月比27万人程度の増加を見込んでいるようですが、その通りになれば、12/16までのFOMCで政策金利が引き上げられる可能性は「ほぼ確実」になるでしょう。また仮に、それを下回る数字になっても、20万人前後増加していれば、問題はないように思われます。
ただ、11/18に公表されたFOMC議事要旨が、12月の利上げを正当化する内容になっていたことがわかり、それを受けた同日の米株式市場が上昇したことから、米株式市場の「利上げ」に対する準備はかなり進んだとの印象を受けます。11/24以降の米国市場は、そうした市場の心理を、ひとつひとつの経済指標をチェックしながら確認していく期間になりそうです。11/24のGDP改定値発表に続き、11/25の耐久財受注、12/1のISM製造業指数、12/2のベージュブックなど、重要指標は少なくなく、注意を要する日が続きそうです。
なお、「金融政策に注目」という意味では、12/3のECB(欧州中銀)理事会が接近しているというスケジュールにも注意が必要です。追加金融緩和への観測からユーロ安・ドル高が加速すれば、ドル高を嫌気した米国株が波乱となる可能性も残るためです。また、11/27から米国で年末商戦が始まるため、そのスタートである11/27〜11/29の週末商戦が芳しくないと、米国株に波乱が生じる可能性もあり、その辺のスケジュールも注意を要しそうです。
表1:「日経平均株価」を考えるうえで当面重要とみられるタイムスケジュール
| 月日 | スケジュール | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 11/24(火) | 9月毎月勤労統計 | |
| 米GDP改定値(7〜9月) | 速報値1.5%から改善か? | |
| 11/25(水) | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | |
| TPP対応政策大綱 | ||
| 米耐久財受注(10月) | 米国設備投資の先行きを占う | |
| 11/26(木) | 11月決算企業「権利落ち」 | |
| ◎米国市場休場(感謝祭) | ||
| 11/27(金) | 失業率・有効求人倍率 | |
| 米国「ブラックフライデー」(年末商戦スタート) | ||
| 月末まで | 緊急対策(1億総活躍社会) | 大家族の同居促進策は? |
| 11/30(月) | 10月小売販売額 | |
| 10月鉱工業生産(速報) | ||
| 12/1(火) | 7〜9月法人企業統計 | |
| 米11月自動車販売台数 | ||
| 米11月ISM製造業指数 | ||
| 中11月製造業PMI | ||
| 12/2(水) | 11月ADP雇用統計 | 労働省雇用統計の前哨戦 |
| イエレンFRB議長講演 | ||
| 米地区連銀景況報告(ベージュブック) | 米金融政策の判断材料 | |
| 12/3(木) | イエレンFRB議長議会証言 | |
| 米11月ISM非製造業指数 | ||
| ECB(欧州中銀)理事会 | 追加金融緩和はあるのか? | |
| 12/4(金) | 米11月雇用統計 | 雇用者27万人増がコンセンサス |
- ※Bloomberg、各種報道をもとに、SBI証券が作成。予定は変更されることもあります。2015/11/23現在の情報で作成しました。
【ココがPOINT!】「企業業績」を評価すれば21,000円接近も!? |
主力の3月期決算企業の「中間決算」(2015/4〜2015/9期)発表が先週までで終了しました。日本経済新聞によると、3月決算企業の「中間」経常利益は前年同期比11%増となりました。通期(2016/3期)は同6.9%増益となり、過去最高益となる見込みです。
上場企業のうち、日経平均採用銘柄の企業業績の方向感は、日経平均の予想EPS(一株利益)の増減に反映されると考えられます。図2に示したように、日経平均の予想EPSは基本的には上昇傾向であり、日経平均の上昇はそれに下支えされたものと考えることも可能です。
その日経平均予想EPSの推移をみると、赤い矢印の所で急上昇しているのがわかります。これは、主力の3月決算企業の本決算発表時期と重なっています。この時期、3月決算企業の予想EPSの「予想」対象が2015/3期から2016/3期に替わるため、予想EPSが2016/3期の増益予想を織り込み、急上昇となっています。その後に、予想EPSが上昇するかどうかは、他の決算期の企業の業績、3月決算企業の業績修正等により変動することになります。
日経平均の予想EPSは7/9に一時1,273円台まで上昇し、10/6の1,268円台まで高原状態となりました。しかし、10/30に1,235円台まで一時的に急減。その後、11/20に1,263円まで回復するという経緯になっています。ご存知の通り日経平均株価は8月中旬から9月末にかけ青い矢印で示したように急落しましたが、それは、企業業績の観点からみれば、緑色で示された予想EPSの低下(企業業績の拡大鈍化)を織り込んだと理解することが可能です。無論、企業業績の拡大鈍化をもたらしたものが、中国や新興国の景気減速、それを背景とした商品市況悪化等であったことは想像に難くないと思います。
いったん低下した予想EPSが回復したことは、主力の3月決算企業の業績が懸念したほど悪くないことを示唆しています。9月末ボトム以降の日経平均株価の反発はそれを反映したと考えることができます。
図2:日経平均上昇を下支えしてきた予想EPS〜その変動が8月以降の株価下落も説明?
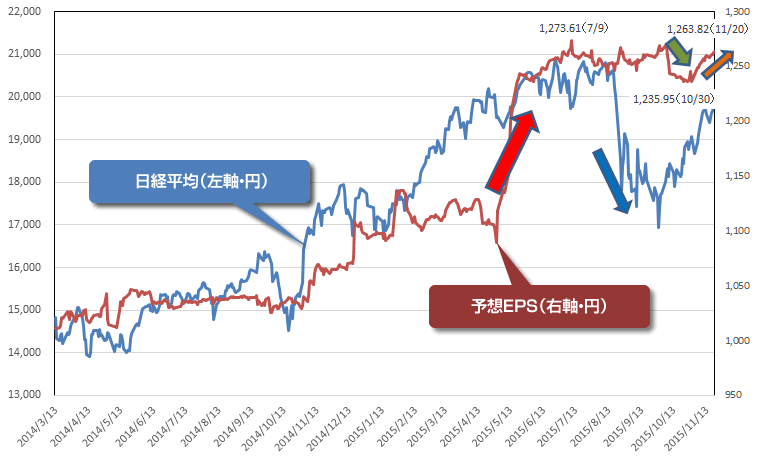
- ※日経平均データをもとにSBI証券が作成。「予想EPS」は、日経平均株価の予想EPS。2015/11/20現在。
図3では、日経平均の日々の予想EPSに、PER=13.5倍、PER=15.0倍、PER=16.5倍を乗じた線をグラフ化しています。またそれと日経平均日足チャートを重ねています。日経平均株価は、予想PER13.5倍〜16.5倍のレンジでおおむね動いていると見受けられます。ちなみに、13.5や16.5という数字は中途半端にみえますが、15.0±10%の水準と考えるときりの良い数字ということになります。
予想EPSに13.5、15.0、16.5といった「定数」を掛けるのですから、図3の緑・茶・青のラインは、図2の予想EPSのラインと同じ形になります。図3を見る限り、日経平均株価の上限という観点では、PER16.5倍相当ライン前後が妥当ということになりますが、予想PER16.5倍に相当する日経平均株価は、予想EPSが高いほど高くなります。図2のもっとも右側の部分で予想EPSは低下⇒反発と推移になっていますが、図3では予想「PER13.5相当」「PER15.0倍相当」「PER16.5倍相当」の日経平均水準も、もっとも右側の部分で低下⇒反発となっています。
11/20現在、日経平均株価は19,879.81円で、図2にもあるようにその予想EPSは1,263.82円です。
19,879.81÷1,263.82=15.73
ですので、予想PERは15.73円と計算されます。このため、図3では赤線の日経平均株価のラインの右端は予想PER15.0倍相当(茶)と16.5倍相当(緑)の間に入っています。仮に、予想PER16.5倍のラインまで日経平均が上昇する可能性があると考えるならば、
1,263.82×16.5=20,852円
ですので、日経平均株価は再び21,000円に接近することが可能になると考えられます。もっとも、短期的な過熱感が強まりつつある現状を勘案すると、なんらかの調整を間に入れてくる可能性は残りそうです。
図3:日経平均株価は予想PER13.5〜16.5倍が基本レンジか?
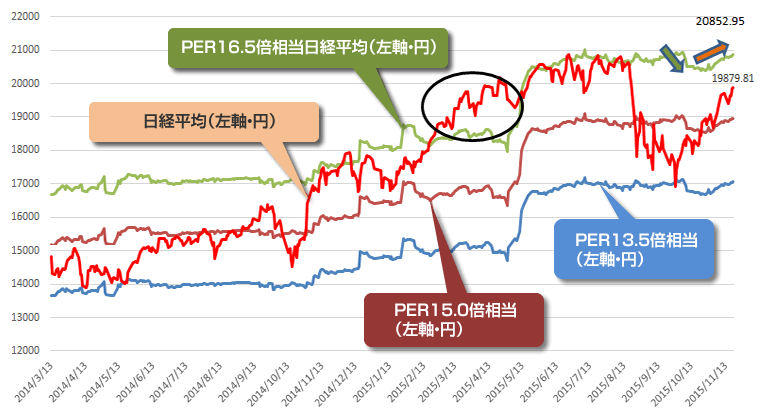
- ※日経平均データをもとにSBI証券が作成。日経平均の予想PER13.5倍相当ライン、同15倍相当ライン、同16.5倍相当ラインと日経平均株価日足チャートを1枚のグラフにしたもの。なお、「日経平均株価=予想EPS×予想PER」として計算されます。なお、黒丸の部分は、日経平均株価が予想PER16.5倍を超えた「異常値」になっています。これは、3月決算企業「本決算」で予想EPSが上昇することを先行して織り込んだためで、その後に予想EPSが上昇すると異常値は解消しています。2015/11/20現在。
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
11月の3連休明けは株高?
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
国内株式 日経平均レバレッジ・インデックス関連ETF
| 取引 | チャート | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
  |
 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
  |
 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス |
  |
 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
  |
 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
  |
 |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 |