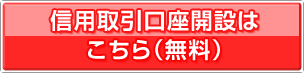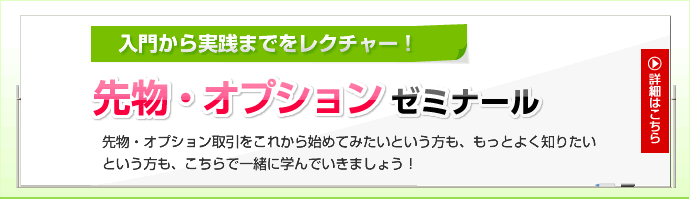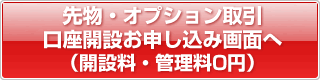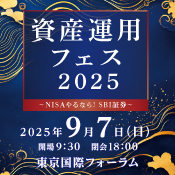9月第2週(9/7〜9/11)の東京株式市場はまさに激動の1週間となりました。値ごろ感の台頭により、いったんは下げ止まった日経平均ですが、週明け後も乱高下しており、目の離せない値動きが続いています。
しかし、こうした乱高下が一巡し、日経平均が反発に転じる契機になるのは、意外にも「米国の利上げ」になるのかもしれません。今回の「225の『ココがPOINT!』」では、米政策金利と外為相場や日経平均の動きを過去のデータから調べ、こうしたシナリオの妥当性を検証してみたいと思います。
続く乱高下〜いったん下げ止まりも波乱の芽は残る? |
9月第2週(9/7〜9/11)の東京株式市場はまさに激動の1週間となりました。日経平均株価は9/8に一時17,415円と、7ヵ月ぶりの安値を付けました。しかし、翌日の9/9には前日比1,343円高と、21年7ヵ月ぶりの上昇幅を記録し、終値で18,770円まで値を回復しました。しかし、9/10には再び売り優勢となり、日経平均は一時前日比814円下げ、再び1万8千円大台割れとなりました。その後は急速に下げ渋る展開となり、日経平均は何とか同大台を維持する形で1週間を終えました。
図1は、2014年1月以降の日経平均株価とその予想PERを同じ平面上に示したグラフです。これまでも時折ご紹介してきた通り日経平均は、予想PERが14倍を割り込むとその辺りが当面の底値になり、その後は反発する傾向があります。今回の下落相場では9/8に予想PERが13.98倍と14倍を割り込んでいました。また、9/8の日経平均終値17,415円は、2014年の年末終値17,450円をわずかに割り込む水準で、外国人投資家など投資成績を暦年でチェックする投資家には重要な節目になっています。大きく乱高下しながらも、日経平均が9/8を底に下げ止まった背景には、こうした値ごろ感の台頭もあるとみられます。
ちなみに、内外の政府や投資家が日程的に政策対応を取りやすくなったことも影響しているとみられます。まず、波乱相場の震源地となった中国では、政府がその開催に注力してきた抗日70周年式典が9/3に終わり、習政権が経済対策に集中しやすくなったと考えられます。米国では、雇用統計発表(9/4)や夏休みシーズンの出口となるレーバーディ(9/7)が終ったことで、投資家がポジションを取りやすくなってきたと考えられます。我が国では、安倍首相が無投票で自民党総裁への再任を決め、「アベノミクス第二幕」に向け、経済対策に集中できる体制が整ってきたと考えられます。
もっとも、9月第3週(9/14〜9/18)は日銀金融政策決定会合の結果発表(9/15)に続き、FOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表(米国時間9/17・日本時間では9/18未明)が予定されています。また、東京市場は9/19〜9/23にシルバーウィークで休場となるため、それまでにポジションを軽くしておきたいと考える投資家は多いとみられます。特に9/18の東京市場は、未明に上記したFOMCの結果が発表され、通常取引時間中は連休前のポジション調整を迫られるというスケジュールになる訳で、波乱が起きやすいタイミングであると言えます。
投資家は、まだまだ株式相場の乱高下と付き合わなければならないのかもしれません。週明け9/14に再び1万8千円割れまで下げた日経平均の動きはまさにそうした市場の懸念を示唆しているかのような相場でした。ただ、今週を境に、株式相場は明るさを増していく可能性がありそうです。なぜでしょうか?
図1:「12月末終値」「PER14倍割れ」水準で、いったん下げ止まった日経平均株価
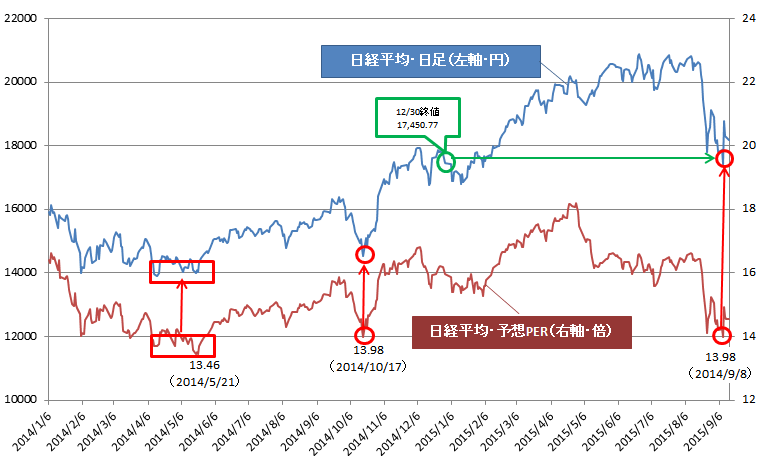
- ※日経平均株価データをもとに、SBI証券が作成(2015/9/11現在)。
「米利上げで新興国から資金が流出する」と考えることは正しいのか? |
東京市場のみならず、世界中の投資家が注目している材料がFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表であることは間違いないと思います。米国の政策金利は2008年12月に現在の0〜0.25%に引き下げられ、その後7年近く現状で推移していますので、実に久しぶりの利上げになるからです。一般的に、政策金利の引き上げはその国の通貨が外為相場で上昇する要因になると考えられています。そのため、多くの新興国では、米国で利上げが実施されると、ドルに対し自国通貨が下落すると予想され、資金が流出し、経済が混乱すると懸念されています。中国経済の減速でリスク回避的な動きが強まっている世界経済ですが、新興国を中心にさらに混乱が広がると懸念されています。
しかし、米国の利上げを契機に新興国の混乱が深まると言う考え方は必ずしも正しくはないかもしれません。図2は、米国金融政策の変更と新興国通貨の対ドル相場を同じグラフ上に示したものです。重要なのは以下の2点です。
(1)米国の金融引き締めへの準備は、2013年12月「量的緩和縮小開始」時点ですでにスタートしていること。
(2)過去5年間、新興国通貨は「中国人民元」以外、おおむねドルに対して下落してきたこと。
世界的な投資資金は、投資環境の変化を先取りして動くのが普通です。米国が、政策金利を7年ぶりに引き上げた後に、はじめて新興国から資金を逃がそうと考える投資資金があるとすれば、投資判断が遅すぎるように思われます。図2にあるように、世界の投資資金は徐々に新興国から資金を移しており、それを受けて新興国通貨は既に下落を続けてきたとは考えられないでしょうか。その動きは米国による「量的緩和縮小」や「量的緩和終了」で加速していたと考えられます。
米国の政策金利は仮に引き上げられても、今後の引き上げペースは緩やかというのが、市場の平均的な見方になっているようです。だとすれば、米政策金利の引き上げは、世界市場でむしろ「アク抜け」と捉えられる可能性があります。新興国の中央銀行の間には、米国がいつ政策金利を引き上げるのかを明確にしていないこと自体が、混乱を助長しているとの見方もあるようです。従って、米政策金利の引き上げは仮にあっても、むしろ「アク抜け」で株価上昇要因になるかもしれません。
図2:新興国通貨はすでに下落している〜主要新興国通貨の対米ドル相場(月足)
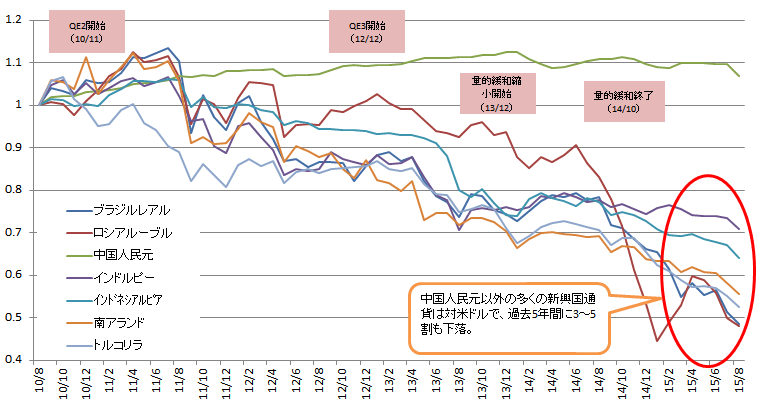
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
【ココがPOINT!】「米利上げ」で再開する!?日本株上昇相場 |
米国政策金利の引き上げは、上記したように新興国経済のさらなる混乱につながるとは限らないと思われます。さらに、過去のデータを見る限りでは、むしろ日本株に追い風になる可能性が大きいとすら考えられます。
図3は、米政策金利の動きと日経平均株価の動きを月足チャートとして、同じ平面上にグラフ化したものです。米政策金利が引き上げに転じてから最後の引き上げ実施月までを「政策金利引き上げ期間」とした場合、過去30年ではおもに4つの期間があげられます。そして、グラフからもご理解いただけるように、米政策金利が引き上げられている期間には、日経平均が上昇しやすいことがわかります。
米国を主要輸出先にする日本にとって、米国が利上げを迫られるほどに好景気な時は、輸出も増加しやすく、株価も追い風を受けやすいと考えられます。また、米国が利上げをする局面では、日米金利差(米金利から日本の金利を引いた数値)が拡大し、円安・ドル高になりやすいこともプラス材料と言えます。
過去30年間のデータでは、米政策金利の引き上げ時期における日経平均の月次リターンは平均で+1.2%と上昇する傾向にあります。米政策金利が引き上げられた場合、短期的にはショック安を挟む可能性は残りますが、次第に日経平均株価は上昇に転じる可能性が大きそうです。
なお、市場の多数派の予想通り、米利上げが見送られた場合、株価は逆に短期的に上昇するかもしれません。しかし、その後は円高・ドル安が進み、反落する可能性があります。もっとも最悪のシナリオはむしろ、米利上げがいつになるかわからない印象を受けている時かもしれません。仮に、米利上げが見送られた場合でも、年内利上げの可能性が維持されれば、株価はあまり下げないと予想されます。
図3:米国の政策金利引き上げ期間に上昇しやすい日経平均株価
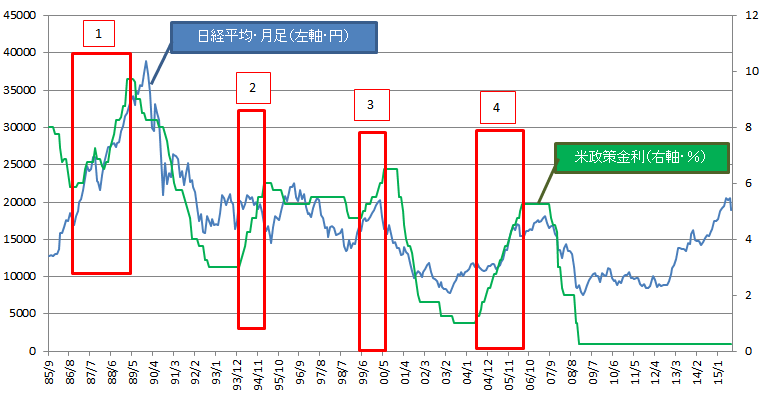
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?
先物・オプションの関連コンテンツ
【サキモノのココがPOINT!】
日経平均は、米金利引上げの有無を見極めへ