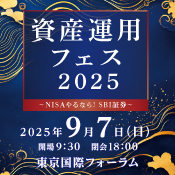前営業日トピックス
東京市場では、序盤から日経平均株価が大幅下落となったことから、リスク回避の動きが強まり、ドル円・クロス円は軟調な動きとなった。さらに、午後には日経平均株価が一段の下落となり、前週末比4400円超下落したことからストップを巻き込みドル円・クロス円は一段の下落となった。
米国市場では、7月の米ISM非製造業景況指数が市場予想を上回ると、米金利上昇とともにドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。ただ、その後は米主要株価指数が軒並み軟調な動きとなったこともあり、終盤まではクロス円とともに上値の重い動きが続いた。
米株式市場では、日本や欧州などの主要株価指数が軒並み大幅下落となったことや、米景気の先行き懸念を背景に投資家のリスク回避姿勢が鮮明となり、主要株価指数は序盤から大幅下落となった。 ダウ平均は、序盤に一時前日比1237ドル安まで下落して6/17以来の安値を付けた。その後は下げ幅を縮小したものの、戻りは限定的となり、1033.99ドル安(-2.60%)で終了、下げ幅は2022年9月以来、約2年ぶりの大きさとなった。一方、ハイテク株中心のナスダックは、576.08ポイント安(3.43%)で終了した。
米ドル/円

※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)東京市場では、前週末の海外市場の流れを引き継ぎ、ドル円・クロス円は序盤から軟調な動きとなった。さらに、日経平均株価が序盤から大幅下落となり、前週末比2500円超下落したことから、投資家のリスク回避の動きが強まり、ドル円・クロス円は急速な下げとなった。ドル/円は、序盤の146.56から144.76まで下落したものの、下げ一服後は値を戻す動きとなり、145.55まで値を戻した。
(2)午後に入り、日経平均株価が下げ幅を拡大し、一時前週末比4753円安まで下落したことから、ドル円・クロス円はストップを巻き込んで一段の下落となった。ドル/円は、141.68まで下落し、1/2以来の安値となった。一方、ユーロ/円は154.41まで下落して昨年12/15以来、ポンド/円は180.08まで下落して1/3以来の安値を付けた。
(3)米国市場では、アジア時間からの軟調な流れが一服し、ドル円・クロス円は序盤から底固い動きとなった。その後に発表された7月の米ISM非製造業景況指数が市場予想の51.0を上回る51.4となると、一時昨年6月以来の低水準を付けていた米10年債利回りが上昇に転じたことから、ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。ドル/円は、序盤の141.83から144.89まで上昇したものの、米主要株価指数が軒並み軟調な動きとなったこともあり、終盤まではクロス円とともに上値の重い動きが続いた。
本日のトピックス
前日の米国市場では、ISM非製造業景況指数が市場予想を上回る結果となったことを受けて、米金利上昇とともにドルは主要通貨に対して上昇した。このところ、米経済指標の冴えない結果が続いたことで、FRBの早期の利下げ観測が強まっていたことや、世界的な株価下落を受けて円買いが優勢となっていたが、経済指標の改善が見られたことで金利の低下やドルの下げが一服している。
ここからどの程度値を戻す動きとなるのか注目されるが、マーケットでは年内の利下げの折り込み度合いが拡大していることから、上値は限定的と考えられる。年内の利下げの折り込み度合いは、7/1時点は0.25%の利下げを1.8回分織り込まれていたが、米雇用統計前には3.4回分、米雇用統計後には一時4.7回分を織り込んでいる。このこともあり、一部では9月のFOMCを前に緊急利下げとも見方も出ている。そこまで米経済が減速しているわけではないことから、あっても年内2回の利下げ、うち1回は0.50%の利下げとの見方もある。金利先物市場では、年内の利下げを1.175%織り込んでいる。今後の政策を見極める上で、来週のCPIなど米国の経済指標の結果がより注目されるだろう。
本日の米国市場では、6月の米貿易収支の発表が予定されており、ここまで2ヵ月連続で赤字額拡大となっており、GDPへの影響が懸念されている。今回、市場予想では改善が予定されており、どこまで改善されるのか注目される。また、下落が続いた株価の反発や低下が続いた米金利の持ち直しがどこまで見られるのかにも注目したい。
8/6の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 米国 |
6月貿易収支 
貿易収支は、米国から輸出された金額と米国へ輸入された金額の差額。米国では、輸出、輸入ともモノだけではなくサービス(運賃や保険、観光など)も含まれる。
|
-725億USD | -751億USD |
| 前回は、市場予想を上回ったものの赤字額は拡大となり、2022年6月以来の高水準となった。財の輸出が輸入より大きく減少したことか影響した。赤字額の拡大はGDPにマイナス寄与となる見通し。今回は、赤字額の縮小が予想されているが、どこまで改善するのか注目されている。 | ||||