前営業日トピックス
東京市場では、日経平均株価が下落したことから、ドル円・クロス円も軟調な動きとなった。一方、NZ中銀が今年の政策金利予想を下方修正したことから、主要通貨に対して大きく下落した。午後には、日経平均株価がプラス圏まで持ち直したこともあり、ドル円・クロス円は底固い動きとなった。ただ、欧州時間では、米長期金利の低下もあり、ドルは上値の重い動きとなった。
米国市場では、第4四半期の米GDPが市場予想を下回ったことから、ドルは主要通貨に対して下落したものの、個人消費が予想を上回ったことや、低下していた米長期金利が上昇に転じたしたことから、ドルは持ち直した。ただ、終盤にかけて米長期金利が再び低下に転じたことから、ドルは上値の重い動きとなった。
米株式市場では、米GDPの結果を受けて、FRBが高水準の政策金利を維持するとの見方が強まったことから、主要株価指数は売りが優勢となった。ただ、PCEデフレーターの発表を翌日に控えていることから、様子見ムード強まっており、下値は限定的だった。ダウ平均は、序盤から軟調な動きとなり、一時前日比230ドル安まで下落した。その後は徐々に下げ幅を縮小し、23.39ドル安(-0.06%)で終了。一方、ナスダックは87.56ポイント安(-0.55%)で終了した。
米ドル/円
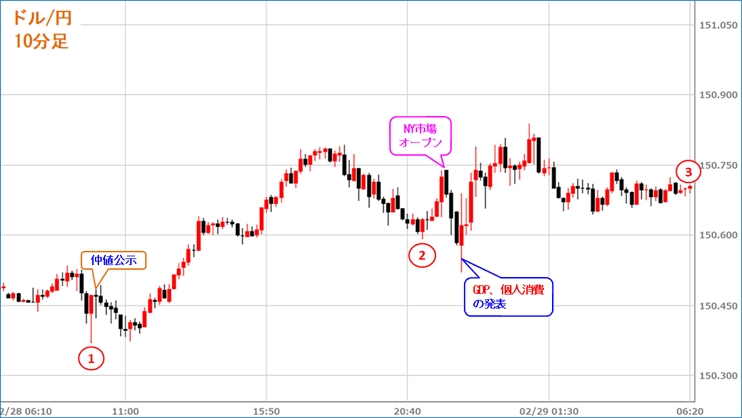
※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)日経平均株価が一時前日比164円安まで下落したことから、ドル円・クロス円は軟調な動きとなり、ドル/円は序盤の150.53から150.37まで下落した。また、NZ中銀が政策金利の据え置きを決定したものの、今年の政策金利の予想値を引き下げたことから、ニュージーランドの金利が低下したことから、NZドルは主要通貨に対して下落した。NZドル/円は、発表直前の92.94から91.82まで下落した。
(2)午後に入ると、日経平均株価がプラスを改善したことや、低下していた米長期金利が底固い動きとなったことから、ドル円・クロス円は底固い動きとなった。ただ、欧州時間に入り上昇が一服すると上値の重い動きとなり、さらに米長期金利の低下も加わりドルは上値の重い動きが続いた。
(3)米国市場では、序盤に発表された第4四半期の米GDP改定値が市場予想の3.3%を下回る3.2%となったことを受けて、ドルは主要通貨に対して下落したものの、同時に発表された個人消費が予想の2.7%を上回る3.0%となったことや、低下していた米長期金利が上昇に転じたことから、ドルは持ち直した。ドル/円は、序盤の150.74から150.53まで下落したものの、その後は150.84まで反発した。ただ、終盤にかけて米長期金利が再び低下に転じたことから、ドルは上値の重い動きとなった。
本日のトピックス
昨晩発表された第4四半期の米GDPは、市場予想を下回ったこと受けてドルは一時下振れとなったものの、米長期金利の上昇などもあり、ドルは堅調な動きとなった。引き続き、米長期金利の指標となる米10年債利回りが4%を上回る高水準を維持していることがドルの下支え要因となっている。そのため、米長期金利が高水準を維持している間は、ドルの底固い動きが続く可能性も考えられる。
本日の米国時間では、複数の主要な経済指標の発表が予定されているが、なかでも1月のPCEデフレーターの発表が注目されている。特に前年比ベースのPCEコア・デフレーターはここまで11ヵ月連続の低下となっており、引き続きインフレの低下が続いていることが示されるのか注目したい。特に、物価関連の指標結果には米金利も敏感に反応することから、金利の動きとともに注目したい。
2/29の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 米国 |
1月個人支出(前月比) 
1ヶ月間に、耐久財(自動車や家電製品など)や、非耐久財(食品や衣料など)、サービス支出(外食・旅行など)において、実際に個人が消費支出した金額について集計した経済指標。
|
0.2% | 0.7% |
| 前回は市場予想を上回り、2ヵ月連続の上昇で9月以来の高値伸びとなった。好調な消費にもかかわらず、コア・デフレーターが鈍化してインフレの加速には繋がらなかった。今回は、前回から低下が予想されているが、デフレーターも鈍化が予想されており、結果を受けたマーケットの反応が注目される。 | ||||
| 0:00 | 米国 |
1月中古住宅販売仮契約(前月比) 
中古住宅販売仮契約は、全米不動産業者協会が発表する中古住宅販売の仮契約を指数化したもの。2001年を100として表す。仮契約は通常1-2ヵ月以内に本契約に移行するため、仮契約指数は中古住宅市場の先行指数とされる。
|
1.1% | 8.3% |
| 前回は市場予想を大幅に上回り、2020年6月以来の高い伸びとなった。住宅ローン金利の低下が寄与していることが示された。今回は、前回の反動で伸び幅の縮小が予想されているものの、2ヵ月連続のプラスが予想されており、底固さが維持されると見られている。 | ||||







