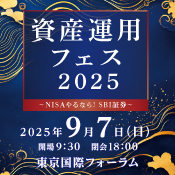前営業日トピックス
東京市場では、日経平均株価が序盤から300円超上昇したことから、ドル円・クロス円は堅調な動きとなった。さらに、実需のドル買いが観測されたことや、米長期金利の上昇がドル/円の押し上げ要因となった。さらに、15時15分に黒田日銀総裁が「現在の強力な金融緩和を粘り強く続ける」と発言したことから円売りが優勢となり、ドル/円は一時126.32まで上昇し、2002年5月以来の高値となった。ただ、その後は高値を警戒する動きが強まり、ドル/円は上値の重い動きとなり、クロス円も軟調な動きとなった。
米国市場では、序盤に発表された3月生産者物価指数が市場予想を上回ったことを受けて、米長期金利が上昇したことから、ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。しかし、インフレがピークアウトしたとの見方も根強く、上昇した米長期金利が低下したことや、アジア時間に126円台を回復したことで高値警戒感が広がっていたこともあり、ドルは主要通貨に対して軟調な動きとなった。一方、対ドルで上昇したことや、米主要株価指数が軒並み反発したことから、クロス円は終盤に向けて堅調な動きとなった。
米株式市場では、業績の回復の見通しを発表した航空大手の決算発表を好感し、本格化する米企業の決算発表への期待感が高まったことから、主要株価指数は堅調な動きとなった。さらに、前日まで続落していたことで値頃感の買いが出たことも押し上げ要因となった。ダウ平均株価は、序盤から堅調な動きとなり、終盤には前日比378ドル高まで上昇した。引けにかけて高値圏を維持したまま、344.23ドル高(+1.01%)で終了した。一方、ハイテク株中心のナスダックは、272.02ポイント高(+2.03%)で終了した。
米ドル/円
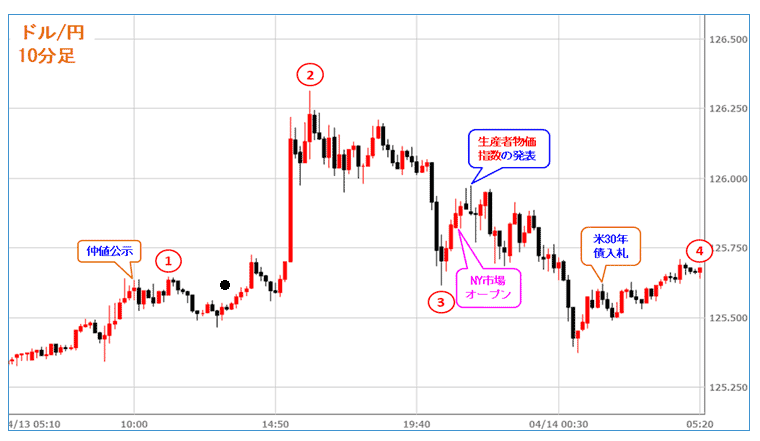
※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)東京市場では、前日の海外市場で米消費者物価指数が40年ぶりの高水準となったことから、FRBの大幅利上げが意識され、ドルは序盤から堅調な動きとなった。さらに、日経平均株価が序盤から堅調な動きとなり、300円超上昇したことから、クロス円も堅調な動きとなった。
(2)午後に入り、日経平均株価が上げ幅を拡大し、523円高まで上昇したことや、時間外取引で米長期金利が上昇したことから、ドル円・クロス円は堅調な動きとなった。その後、黒田日銀総裁が「現在の強力な金融緩和を粘り強く続ける」と発言したことで、改めて日米金融政策の方向性の違いが意識されたことから円売りが加速し、ドル/円は一時126.32まで上昇し、2002年5月以来約20年ぶりの高値となった。
(3)上昇一服後は、急速な円安に対する警戒感の高まりに加え、時間外取引で米長期金利が低下したことから、ドル/円は上値の重い動きとなり、ドル/円の動きにクロス円も軟調な動きとなった。
(4)米国市場では、序盤に発表された3月米生産者物価指数が、前年比ベースで2010年11月以来の高水準となったことを受けて、米長期金利が上昇したことからドルは主要通貨に対して堅調な動きとなり、ドル/円は堅調な動きとなった。しかし、前日に発表された米消費者物価指数の結果を受けてインフレがピークアウトしたとの見方も根強い中、上昇した米長期金利が低下したことや、アジア時間に2002年5月以来の高値を付けた後に高値警戒感が広がっていたこともあり、ドルは主要通貨に対して下落となり、ドル/円も125.37まで下落した。一方、対ドルで上昇したことや、米主要株価指数が軒並み反発したことから、ユーロ/円やポンド/円などのクロス円は終盤に向けて堅調な動きとなった。
本日のトピックス
米国をはじめとした主要国は、金融引き締め策に舵を切っている中、昨日黒田日銀総裁が「強力な金融緩和を粘り強く続ける」と発言したことから、日本と米国など主要国との金融政策の方向性の違いが意識されて円売りが加速、ドル/円は一時126.32まで上昇し、2002年5月以来約20年ぶりの高値となった。 マーケットで注目されていた黒田シーリング(2015年6月に「これ以上の円安はありそうにない」と発言して以降、125円台がドル/円の上値抵抗ラインとされてきた)を超える展開となった。
マーケットでは、急速な円安を受けて、黒田日銀総裁がどのような見解を示すのか注目されている。ただ、急速な円安にもかかわらず、コメントを発していないことや、先日の円安容認と受け取れる発言から、一定の円安を容認しているのではとの思惑も出ている。そのため、ここからの金融当局者の発言に注目が集まっている。
本日の海外市場では、ECB理事会の結果発表と、ラガルドECB総裁の会見が予定されている。政策金利の変更はないと予想されているが、日本と同様に金融政策の遅れが指摘されているものの、このところ当局者のタカ派的な見解も見られていることから、声明や会見での総裁の発言がタカ派的となるのか注目されている。タカ派的となるようなら、日銀の金融政策の遅れ、主要国との金利差拡大がさらに意識される可能性も考えられる。一方、米国市場では、小売売上高、ミシガン大学消費者信頼感指数の発表が予定されており、こちらの結果にも注目したい。
4/14の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数(4/9までの週) 
新規失業保険申請件数は、労働省が失業保険を申請した人(失業者)の数を毎週発表する経済指標。毎週(木曜日)発表されるため、雇用情勢の速報性に優れており、雇用統計の先行指標として注目されている。ただ、米国の祝祭日や天候などの影響を受けやすいという点もある。
|
17.3万件 | 16.6万件 |
| 前回は市場予想を下回る改善となり、3/18までの週に付けた1969年以来の低水準に並び、経済活動再開が進んだことによる労働市場の改善が続いていることが示された。ただ、労働省は前回の発表から集計方法を変更したことで、前週までの結果が大幅に修正された。今回は、前回から増加が予想されているものの、依然として低水準が維持され、雇用の改善が進んでいることが示されると見られている。 | ||||
| 21:30 | 米国 |
3月小売売上高(前月比) 
小売売上高は、米国商務省が百貨店やスーパーの売上調査を基にして発表している指標である。個人消費はGDPの約70%を占めており、小売売上高は個人消費の動向を見る上で重要な経済指標の一つであり、米国経済に与える影響も大きいため注目されている。
|
0.6% | 0.3% |
| 前回は市場予想を下回り、大幅な伸びとなった1月の結果から伸び幅が鈍化した。インフレ高進により、消費者が支出を抑えたとの見方もあった。ガソリンスタンド、飲食店、自動車などで増加した。今回は、前回から伸び幅が拡大すると見られているが、伸び幅は小幅に留まると見られている。 | ||||
| 23:00 | 米国 |
4月ミシガン大学消費者信頼感指数 
ミシガン大消費者信頼感指数は、ミシガン大学が消費者にアンケート調査を行い、現況指数(現在)、期待指数(将来)など消費者マインドを指数化した経済指標である。速報は300人、確報は500人を対象に調査を実施し、1964年の指数を100として算出する。コンファレンス・ボード(CB)が発表する消費者信頼感指数と共に消費者マインドを見る上で重要な経済指標である。
|
59.0 | 59.4 |
| 前回は市場予想を下回り、2011年8月以来の低水準となった。インフレ高進に加え、ロシアのウクライナ侵攻を巡る不確実性が消費者のマインドを引き下げた。特に、1年先のインフレ期待が1981年11月以来の高水準となったことが圧迫要因となった。今回は、さらに低下が予想されており、消費者のマインドの改善には時間を要すると見られている。 | ||||