前営業日トピックス
東京市場では、ドル/円が序盤に前日高値の110.59に迫る110.58まで上昇したものの、連休明けで実需のドル売りが観測されたことや、時間外取引の米国債利回りが低下したことから、ドルは主要通貨に対して軟調な動きとなり、対円では一時110.26まで下落した。一方、ドル/円の下落に加え、日経平均株価が序盤に480円超上昇したものの、その後200円以上上げ幅を縮小したことから、クロス円も軟調な動きとなった。さらに米長期金利の低下も加わり、ドル/円は110.12まで下落したものの、下げ一服後は再び底固い動きとなった。
米国市場では、欧州時間の流れを受けて、ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなり、対円では一時110.42まで上昇した。しかし、6月の新築住宅販売件数が1年2ヵ月ぶりの低水準となったことなどが影響し、ドルは主要通貨に対して下落となり、ドル/円は一時110.16まで下落した。ただ、欧州時間に1.219%まで低下していた米10年債利回りが1.294%まで上昇した流れに合わせ、ドルは底固い動きとなり、対円では110.41まで回復した。一方、序盤に下落した米主要株価指数が軒並み上昇に転じ、史上最高値を更新したことから、クロス円も底固い動きとなった。
米株式市場では、中国株の大幅下落を受けて、米主要株価指数は序盤から軟調な動きとなった。しかし、米主要企業の好調な決算発表が続いていることから、引き続き米景気の先行きに対する楽観的な見方が根強く、その後は堅調な動きが続き、主要3指数は史上最高値を連日更新した。ダウ平均株価は、序盤から軟調な動きとなり、一時前週末比111ドル安まで下落した。その後は上昇に転じ、終盤には88ドル高まで上昇して史上最高値を更新、82.76ドル安(+0.24%)の35144.31で終了し、終値ベースの最高値も更新した。
米ドル/円
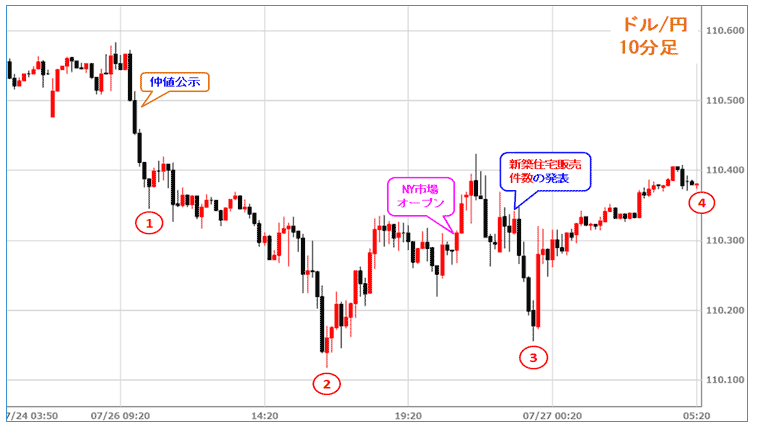
※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)前週末の海外市場の株高を背景に、日経平均株価が序盤から400円超上昇したことから、ドル円・クロス円は序盤から底固い動きとなった。ドル/円は一時110.58まで上昇したものの、前日高値の110.59には届かなかった。その後、時間外取引で米長期金利が低下したことや、連休明けの実需のドル売りも観測され、ドル/円は軟調な動きとなった。一方、クロス円はドル/円の下落に連れて軟調な動きとなった。
(2)午後に入り、中国株が大幅下落となったことを受けて、日経平均株価は上げ幅を縮小する動きとなったことや、米株価先物が下落したこと、さらに前週末の米国市場で1.31%台まで回復していた米長期金利の指標となる米10年債利回りが1.219%まで低下したことからドル売り・円買いが優勢となり、ドル円・クロス円は軟調な動きが続き、ドル/円は一時110.22まで下落した。
(3)その後は米長期金利が下げ一服となり、1.26%台まで回復したことから、ドル/円も堅調な動きとなり、米国市場序盤には110.42まで回復した。しかし、6月の新築住宅販売件数が予想外の大幅低下となり、2020年4月以来1年2ヵ月ぶりの低水準となったことや、その後に発表された7月のダラス連銀製造業活動指数が冴えない結果となったことが影響し、ドルは主要通貨に対して下落となり、ドル/円は一時110.16まで下落した。
(4)欧州時間に1.219%まで低下していた米10年債利回りの上昇が続き、終盤に1.294%まで上昇した流れに合わせ、ドルは底固い動きとなり、対円では110.41まで回復した。一方、序盤に下落した米主要株価指数が軒並み上昇に転じ、史上最高値を更新したことや英国での新規感染者数の減少が続いていることからポンドが対ドルで上昇したほか、ユーロも1.18ドル台前半へ反発したことも好感され、クロス円も底固い動きとなったこともドル円の堅調を支援する要因となった。
本日のトピックス
ドル/円は、110.50台では上値の重い動きが続いているものの、110.00台前半では底固い動きが続いている。米国のFOMCを控えて様子見ムードも強まっていることから、発表まではレンジ内の動きが続くとの見方もある。ただ、指標結果や企業の決算発表を受けて、思惑が交錯する可能性もあることから、レンジを抜ける場合には抜けた方向に動きが出る可能性も考えられることから、注意したい。
米国市場では、6月の米耐久財受注、7月の米消費者信頼感指数の発表が予定されているものの、FOMCの結果発表を控えて反応は限定的と見られている。ただ、マーケットでは、変異株の感染拡大を背景に景気回復の先行き期待が後退しているとの見方もあり、量的緩和の段階的縮小時期が後退する可能性も指摘されている。そのため、良好な結果が示されれば楽観的な見方が広がる可能性も考えられるが、冴えない結果ならドルを圧迫する展開となる可能性もあるだろう。
7/27の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 米国 |
6月耐久財受注(前月比) 
耐久財受注(Durable Goods Manufacture's Orders)は、米国の耐久財(耐久年数3年以上)の新規受注額を集計した指標であり、設備投資の先行指標として注目されている。特に、変動の大きい輸送用機器などを除いた受注額が民間の設備投資の先行指標として注目されている。
|
2.0% | 2.3% |
| 前回は市場予想と一致し、1月以来の大幅な伸びとなった。航空機や自動車の受注が増加したことが全体を押し上げた。なお、輸送機器を除く受注は+0.3%に留まった。今回は、前月から伸び幅の低下が予想されているものの、比較的高い伸びが維持されると見られているが、特に輸送機器を除く受注が伸びているのかどうかが注目される。 | ||||
| 23:00 | 米国 |
7月消費者信頼感指数 
消費者信頼感指数は、米国のCB(Conference-Board=コンファレンスボード「全米産業審議委員会」)という民間の調査機関が発表する消費者マインドを指数化したもの。5,000人の消費者にアンケート調査を行い、現在と半年後の景況感、雇用、所得の項目で回答した結果を指数化している。
|
124.0 | 127.3 |
| 前回は市場予想を上回り、昨年2月以来の高水準まで改善し、コロナ感染拡大後の最高となった。景気や雇用に対する消費者の楽観的な見方が強まったことが示された。特に、雇用に関しては、職が豊富との回答が2000年以来の高水準となった。今回は、前回から低下が予想されているものの、依然として高い水準を維持すると見られている。 | ||||
| 23:00 | 米国 |
7月リッチモンド連銀製造業指数 
リッチモンド連銀製造業指数は、米国の12連邦準備銀行の1つであるリッチモンド地区連銀が発表している製造業指数。1993年から算出が開始されており、NY連銀、フィラデルフィア連銀が発表する指数と合わせて製造業の景況を確認できる。管轄はウェストバージニア州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、バージニア州、メリーランド州、ワシントンDCなど。管轄地域は米国内生産の9.1%を占める。
|
20 | 22 |
| 前回は市場予想に反して上昇となり、昨年10月以来の高水準となった。5ヵ月ぶりの高水準となった新規受注や雇用が伸びたことが影響した。今回は、前回からの低下が予想されているが、小幅低下に留まり、高水準を維持すると見られている。 | ||||







