前営業日トピックス
東京市場では、海外市場の軟調な流れが一服し、序盤から底固い動きとなった。しかし、上昇して始まった日経平均株価がマイナス圏まで下落したこともあり、ドル円・クロス円は上値の重い動きとなった。その後は、株価が下げ幅を縮小したことや、米国債利回りの上昇を受けて底固い動きとなった。
米国市場では、トランプ米大統領がメキシコからの輸入品に来週から追加関税を課すと発言したことや、パウエルFRB議長が利下げの可能性を示唆する発言をしたこともあり、ドルは軟調な動きとなった。
ただ、米主要株価が軒並み大幅上昇したことや、米10年債利回りが上昇したことも加わり、ドルは再び上昇した。その後、ドルは上値の重い動きとなったが、ドル/円は108円台を維持した。
米ドル/円
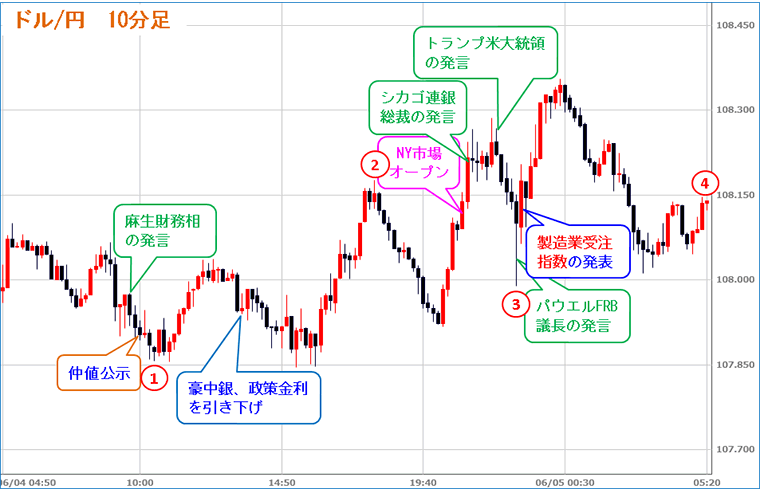
※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)海外市場の軟調な流れが一服し、序盤から底固い動きとなった。そして、上昇して始まった日経平均株価がマイナス圏まで下落し、下げ幅を拡大したことから、ドル円・クロス円は軟調な動きとなった。
(2)午後に入り、日経平均株価が再びプラス圏まで上昇したことや、米10年債利回りが2.0814%から2.1072%まで上昇したことを受けて、ドル円・クロス円は堅調な動きとなったが、上値は限定的だった。一方、豪中銀は、2016年8月以来2年9ヵ月ぶりに政策金利であるオフィシャルキャッシュレートを1.50%から1.25%に引き下げたが、すでに織り込み済みだったことや、追加利下げに言及がなかったことから豪ドルが買われたが、その上昇は一時的だった。
(3)ハト派で知られているエバンス・シカゴ連銀総裁が、金利は適切な水準にあるとの認識を示したことを受けて、前日のセントルイス連銀総裁の発言を受けて高まっていた利下げ圧力がやや後退したことで、ドルは底固い動きとなった。しかし、トランプ米大統領が、「来週、メキシコからの輸入品に5%の追加関税を課すだろう」と発言したことや、パウエルFRB議長が「景気拡大を維持するため、適切な行動を取る」と発言したことが、利下げの可能性を示唆したと受け止められたこともあり、ドルは上値の重い動きとなった。
(4)米中通商交渉を巡り、中国政府が米国との対話を求めているとの報道に加え、FRB議長が利下げの可能性をほのめかしたことを好感して、米主要株価が軒並み2%を超える大幅上昇となった。これを受けて、ドル円・クロス円は底固い動きとなった。さらに、米10年債利回りが2.1003%から2.1435%まで上昇したことも下支え要因となった。終盤にかけては、ドルはやや上値の重い動きとなったが、ドル/円は108円台を維持するなど、底固い動きが続いた。
本日のトピックス
欧州市場では、ドイツやユーロ圏の5月の非製造業PMIの発表が予定されており、結果が注目される。先に発表された製造業PMIは予想通りの結果となったことから、マーケットの反応は限定的だった。一方、米国市場では、5月の米ADP雇用統計、ISM非製造業景況指数の発表が予定されており、週末の米雇用統計を予想する上で比較的参考にされる経済指標であることから、こちらの結果も注目されている。また、本日も複数の米当局者の発言が予定されており、昨日もFRB議長などの当局者の発言がマーケットに若干影響したこともあったことから、引き続き注目したい。本日はアトランタ連銀総裁、クラリダFRB副議長の発言や、ボウマンFRB理事の議会証言が予定されている。
6/5の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 米国 |
5月ADP雇用統計 
ADP雇用統計は、民間の給与計算代行サービス会社であるADP(Automatic Data Processing)社のデータを用いて、マクロエコノミック・アドバイザーズ社が発表している雇用統計。2200万人の支払い給与の動向に基づき算出、通常米国雇用統計が発表される2営業日前に発表されるため、米国雇用統計の結果を予想する上でよく参考にされる。
|
+18.8万人 | +27.5万人 |
| 前回は市場予想を上回る結果となり、2018年7月以来の高水準となった。今回は低下が予想されているが、このところ市場予想との乖離するケースが多くなっており、過去1年間の平均乖離幅は5.68万人となっており、予想が参考にならないケースが続いている。2008年以降で、+25万人以上となった翌月は低下するケースが続いており、その平均は+20.4万人、前月からの減少平均は6.5万人となる。統計データと市場予想どちらに近い結果となるのか注目する。 | ||||
| 23:00 | 米国 |
5月ISM非製造業景況指数 
ISM非製造業景気指数は、全米供給管理協会(Institute for Supply Management=ISM)が発表する米国の非製造業(サービス業)の景況感を示す指数。管理責任者に対するアンケートを集計した指数であり、50が景気の拡大・後退の判断基準であり、50を上回れば景気拡大、下回れば景気後退と判断する。
|
55.4 | 55.5 |
| 前回は、市場予想を下回る結果となり、2017年8月以来の低水準となった。雇用が2年ぶりの低水準となり、新規受注も落ち込んだことが影響した。今回は、前回から若干の低下が予想されており、ここまで2ヵ月連続の低下で、2ヵ月連続で市場予想も下回っていることから、予想を下回る結果となる場合には、サービス業の鈍化が意識される可能性も考えられる。 | ||||
本日のトレードポイント
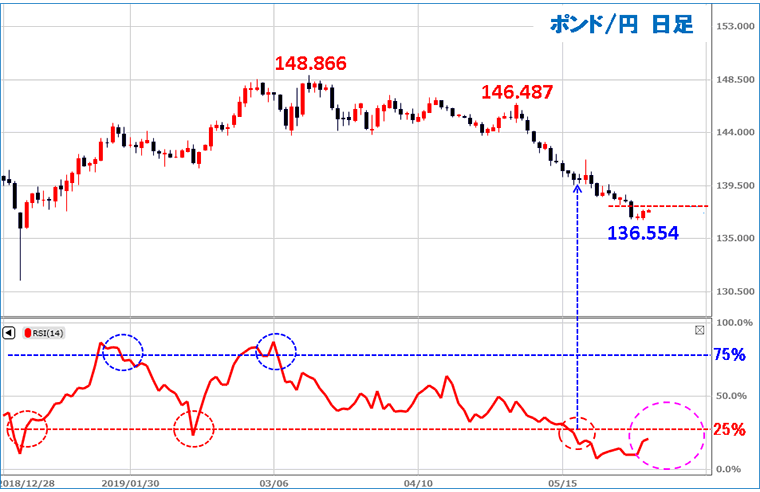
※出所:FX総合分析チャート 日足
ポンド/円は、5月前半から軟調な動きが続いており、10円幅近い下落となっています。オシレーターのRSIでは25%以下に低下(現在20%台)しており、売られ過ぎを示すゾーンに入り込んでいます。チャート的には、ここからの転換のタイミングが注目されています。RSIにおける注目のポイントは、売られ過ぎゾーンとされる25%から30%を抜けた時となります。
今回、RSIは6.9%まで低下しましたが、最近10%を下回ったのは2018年8月の7.5%、2017年8月の7.2%となっており、2018年時はその後140円台から149円台まで上昇、2017年時は140円台から152円台まで上昇しています。
気まぐれ投資コラム
テクニカル分析 RSI(Relative Strength Index) その1
RSI(Relative Strength Index)は、オシレーター系のテクニカル分析の代表的な指標です。相場の買われすぎ、売られすぎを示すテクニカル指標で、オシレーター分析の中では最も活用されている分析方法で、考案者のW・ワイルダー氏は、14日間の指数が最適であるとしています。基本的には、70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断すべきとしていますが、よりシビアなシグナルを追及するため、パラメーターを14日に設定の場合には75%以上〜25%以下、振れ幅のやや大きい9日に設定の場合80%以上〜20%以下がよく使われています。
【売買のタイミングのヒント】
売られ過ぎとされる30%(25%)、買われ過ぎとされる70%(75%)に到達したものの、価格や指数の下落や上昇が続く場合もあることから、「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」のゾーンに到達した時点でなく、指数がゾーンから抜け出す時点の方が有効と考えられます。
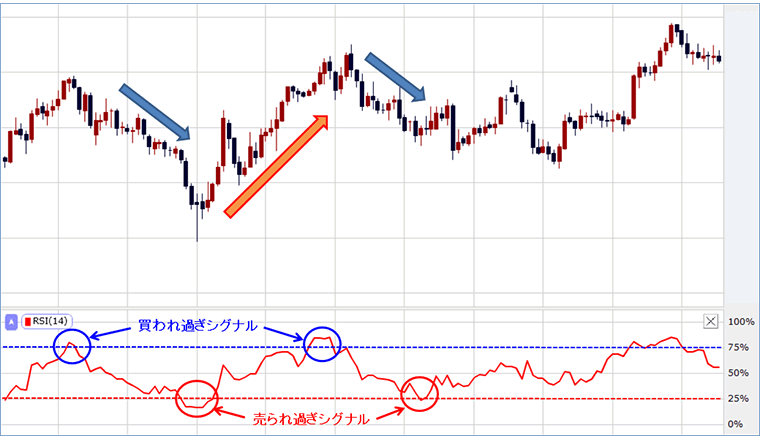
※出所:FX総合分析チャート







