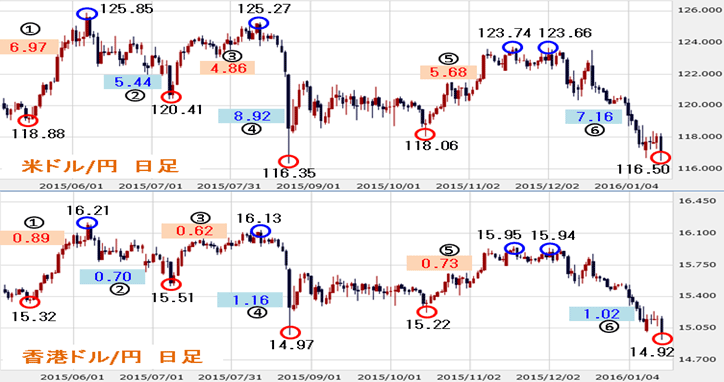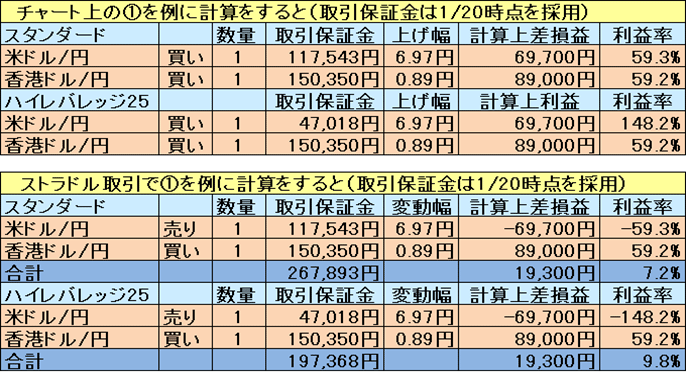前営業日トピックス
前日の米国市場で、原油相場が下落したことで、投資家の消極姿勢が強まり、比較的安全な資産とされる円を買う動きが先行した。また、中国経済の先行きに対する懸念や、日経平均株価が大きく下落する動きとなったことも材料視された。そして、日経平均株価が660円以上の下落となったことや、欧州株が大きく下落して始まったことから、一段の円買いとなり、ドル/円は2015年1月以来の安値を付ける動きとなった。その後は、下落が続いた反動から値を戻す動きも見られたが、原油価格が再び下落に転じたことや、米株価が大幅下落となったことから、再び軟調な動きとなった。ただ、終盤には株価が下げ幅を縮小して、ドル円・クロス円も値を戻す動きとなった。
米ドル/円
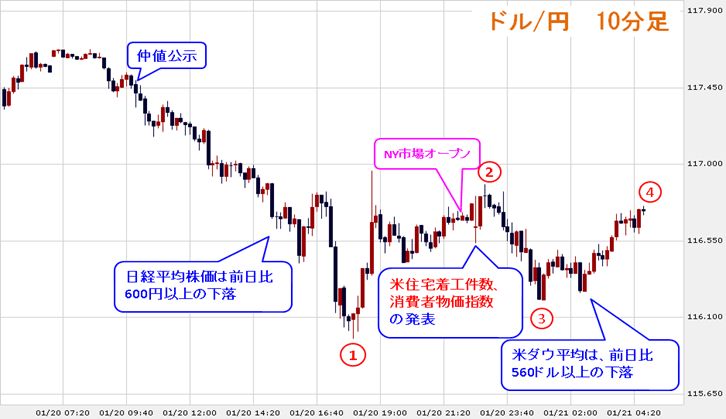
※出所:FX総合分析チャート10分足
(1)海外市場で原油価格が下落したことや、日経平均株価が序盤から軟調な動きとなったことで、安全資産とされる円を買う動きが優勢となった。その後、日経平均株価が660円以上の下落となったことや、中国株の下落を受けて、一段の円買いとなり、ドル/円は2015/1/16以来の安値を付けた。
(2)海外市場では、下落の反動や原油価格が値を戻したことなどから、ドル円・クロス円も堅調な動きとなった。
(3)原油価格が下落に転じ、2003年9月以来の26ドル台まで落ち込んだことに合わせて、株価も下落幅を拡大し、リスク回避の円買いが優勢となった。
(4)一時565ドル安まで下落したダウ平均株価が、下げ幅を縮小する動きとなったことから、ドル円・クロス円もやや上昇となった。
本日のトピックス
昨晩の米国市場では、引き続き原油価格や株価が大きく下落したこともあり、本日のアジア市場への影響も懸念されている。また、下落後の反動も大きかったことから、値動きの変化には注意したい。また、海外市場では、ECB理事会の政策発表が予定されており、政策の変更は無いと予想されているが、総裁が会見で更なる追加緩和を示唆する可能性も考えられることから、発言内容には注意したい。特に、ユーロは過敏に反応する可能性が考えられることから注意したい。また、米国市場では、主要な経済指標の発表が予定されているが、限定的な反応が予想される。ただ予想より悪化する場合には、やや過敏に反応する可能性もあるだろう。
1/21の注目材料
| 時間 | 国・地域 | 経済指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | 欧州 |
ECB理事会 ユーロ圏政策金利 
ユーロ圏の統一的な金融政策を担う最高意思決定機関。理事会は、総裁・副総裁を含む幹部6名と、ユーロ圏各国の中銀総裁で構成され、原則として月に2回、ドイツのフランクフルトのECB本部で定例会合を開く。会合終了後は、ECB総裁が会見を実施する(議事録は公開していない)。
|
0.05% | 0.05% |
| 先月追加緩和を打ち出していることから、当面は効果を見極めるために現状維持が予想されている。ただ、理事会後のドラギ総裁の会見では、更なる追加緩和を示唆する可能性も考えられることから、会見での発言には注意したい。(ドラギ総裁の会見は22:30頃の予定) | ||||
| 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 
労働省が失業保険を申請した人(失業者)の数を毎週発表する経済指標。毎週(木曜日)発表されるため、雇用情勢の速報性に優れており、雇用統計の先行指標として注目されている。ただ、米国の祝祭日や天候などの影響を受けやすいという点もある。
|
27.8万件 | 28.4万件 |
| 前回は、予想外の増加となり、昨年7月以来2番目に高い水準となった。今回は、前回からの改善が予想されているものの、年始や連休などもあり、この時期は変動しやすいという特徴もあることから、注意したい。 | ||||
| 22:30 | 米国 |
1月フィラデルフィア連銀景況指数 |
-5.9 | -5.9 |
| 前回は、市場予想に反してマイナスとなり、2ヵ月ぶりのマイナスに落ち込んだ。雇用関連の指数が改善しているものの、新規受注が3ヵ月連続のマイナスとなっていることが影響した。今回もマイナスが予想されており、前回の修正なども含め、実質的な結果に注目したい。 | ||||
本日のトレードポイント
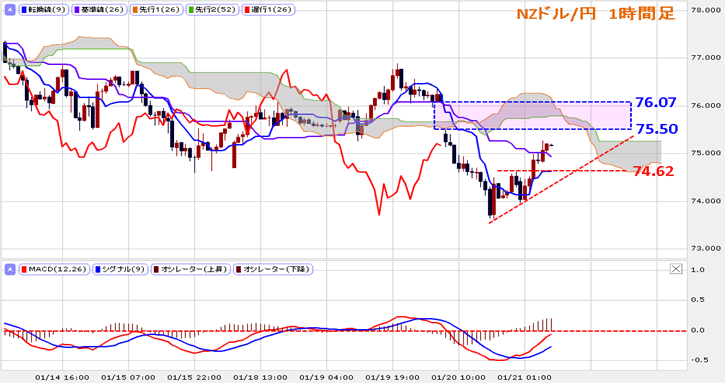
※出所:FX総合分析チャート1時間足
NZドル/円は、安値からほぼ半値戻しとなっている。オシレーターのMACDでは、両線上向きで乖離幅が拡大傾向となっているものの、やや失速気味でもある。ここから乖離幅の拡大が続き、堅調な動きが続くのか注目したい。ただ、この上には前日に明けたギャップ(窓)があることや、一目均衡表の雲があることから、上値の重い動きも考えられる。そして、上値のポイントを突破する場合には一段の上昇も考えられる。一方、上値の重い動きとなり、反落する場合には、トレンドラインや、サポートの下抜けに注目したい。
気まぐれ投資コラム
米ドル/円と香港ドル/円 3
米ドル/円と香港ドル/円の売買をシミュレーションすると、スタンダードコース※での取引では計算上の利益率はほとんど変わりませんが、計算上の利益には差が生じます。一方、ハイレバレッジ25コース※では、ドル/円の取引保証金の違いから、計算上の利益率に大きく違いが生じます(計算上の差損益は変わらない)。
そして、両通貨ペアの特徴を生かして、2通貨をセットとして売買(ストラドル取引※2)した場合を例にすると、現状で計算上の利益率の大きくなる香港ドル/円をメインに考え、今後相場が上昇すると予想した場合、香港ドル/円を「買い」、ドル/円を「売り」のポジションを取ります。その場合、トータルの利益率は低下しますが、相場が思惑と逆に動いた場合のリスクもある程度軽減できます。
そして、自身の投資スタイルや相場分析に応じて、取引数量の比率を変化させることで、効率を上げることも可能でしょう。また、現状のような荒っぽい動きの場合には、参加しないのも一つの方法ですが、このような場合にはリスクを軽減しながら利益を追及することにも妙味があります。また、注意としては、同時に2通貨を成立させることができないことから、新規や決済時において多少の誤差が生じる可能性があることも考慮する必要があります。
※取引コースの詳細はこちら
※2 ストラドル取引とは、同じ特性を持った二つの銘柄をセットにし、同時に売りと買いを両建てする取引であり、通常の取引よりも安全性を重視して利益を追求する取引です。そのため、トータル利益率は落ちますが、思惑と逆方向に相場が動いた場合の損失率はやや軽減できます。