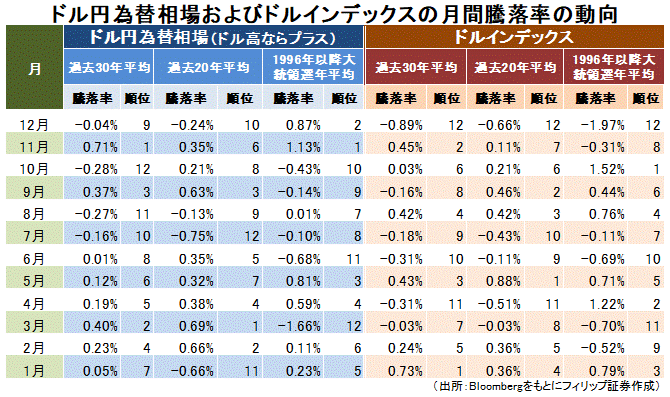23年11月「銘柄ピックアップ」振り返る
- 昨年11月分の米国ウィークリー「銘柄ピックアップ」について掲載直前週末終値から2/26終値までの騰落率上位6銘柄を見ると、半導体関連が他セクターを圧倒。サーバーでエヌビディア(NVDA)を支えるスーパー・マイクロ・コンピューター(SMCI)が約3倍の上昇。先端AI(人工知能)半導体でエヌビディアと競合するアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)、世界最大の半導体ファウンドリの台湾積体電路製造(TSM)、AIをデバイスに組み込む半導体に強いクアルコム(QCOM)が堅調。中華圏中心に強い旅行需要を背景にマリオット・インターナショナル(MAR)も好調。
23年11月「銘柄ピックアップ」振り返る〜半導体関連が他セクターを圧倒
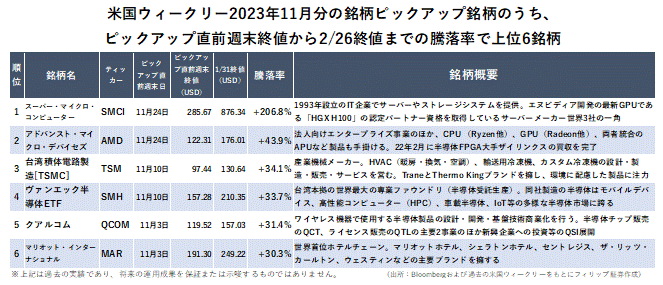
米国株相場に変調シグナル2点灯る?
- 米国株の主要株価指数は昨年10月下旬から堅調に推移。その背景に利下げ観測の台頭、生成AI(人工知能)普及に伴う半導体関連および主要大型ハイテク銘柄への資金流入があるとみられるなか、米国株相場に2つの変調シグナルが灯った。
第1に、半導体大手エヌビディア(NVDA)の最新半導体「HGX H100」の認定パートナーの1社であるサーバーメーカーのスーパーマイクロ・コンピューター(SMCI)の株価だ。同社株価は、相場過熱感を見るテクニカル指標のRSI(相対力指数)14日間が2/15に97%の異常な買われ過ぎだった反動から2/16-21に下落も、その後はレンジ相場へ移行の兆し。時価総額米企業2位アップル(AAPL)の終値は、2/16以降200日移動平均を下回ってきている。米国株全体に与える影響としては軽視できまい。
米国株相場に変調シグナル2点灯る?〜エヌビディア関連とアップル株
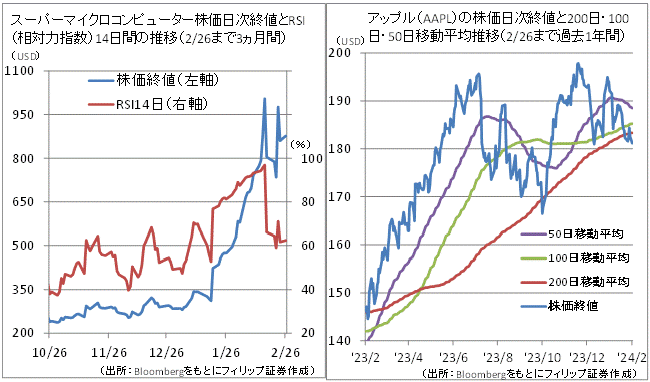
逆襲の低PBR・高配当利回り米国株
- 機関投資家の株式エクスポージャーを表す「NAAIMエクスポージャー指数」を見ると2/21が74.70と前週比20.9ポイント下落。それに対して米主要株価指数は一部の半導体関連や超大型ハイテク銘柄に牽引されて引き続き堅調に推移。仮に相場調整があるならば、相場上昇の恩恵に与れなかった銘柄は逆に資金シフトの可能性が高まり好機となることも考えられる。
S&P500指数構成銘柄の内、2/26終値で直近実績および当期予想PERが10倍未満の高配当利回りでは、大手タバコ会社や大手通信キャリア会社など常連バリュー銘柄のほか、石油株やガソリン車主体の自動車メーカーなど脱炭素からの揺り戻し恩恵を受ける銘柄が挙げられる。トランプ前大統領復権(もしトラ)まで見据えると脱炭素揺り戻し相場が長く続く可能性もあろう。
逆襲の低PER・高配当利回り米国株〜定番銘柄のほか脱炭素揺り戻しも
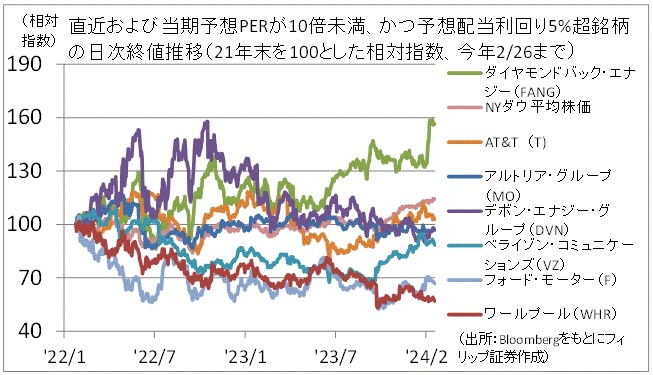
メタ・プラットフォームズとアマゾン・ドット・コム
- メタ・プラットフォームズ(META)とアマゾン・ドット・コム(AMZN)が2/1に10-12月期決算を発表。好内容を受けて翌2日の株価終値はメタが前日比20.3%上昇で時価総額を1日で約30兆円相当額、アマゾンが前日比7.9%上昇で時価総額を1日で約20兆円相当額増加させた。
両社に共通するのは売上高総費用比率が2022年10-12月までは上昇悪化傾向にあったなかで23年以降に反転低下して利益率が改善していった点である。その中には従業員削減も含まれる。メタの場合は仮想空間(メタバース)への投資を抑制したこと、アマゾンは物流網再構築に取り組んだことが実を結んだ。そして収益面の改善とそれに伴うキャッシュフローも大幅に良化。AI(人工知能)活用で更なる利益率向上が期待されよう。
メタ・プラットフォームズとアマゾン・ドット・コム〜決算発表後に株価大幅上昇の要因
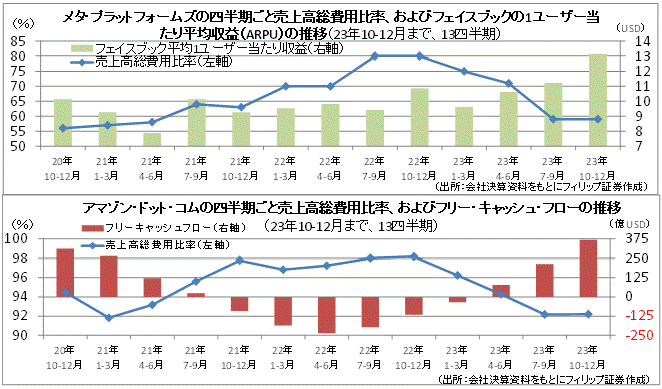
パソコンとスマホの世界出荷台数
- 市場調査会社IDCは四半期ごとのスマートフォンとパソコンの世界出荷台数を公表している。IDCによる昨年10-12月は、世界パソコン出荷台数が前年同期比2.7%減の6710万台と8四半期連続減少も減少率が縮小。買替えサイクルやWindows10サポート終了に向けて本格的に伸びるのは24年後半以降とみられるものの、販売価格が引き上げられた生成AI(人工知能)搭載「AIパソコン」の展開が示唆される。HP(HPQ)やデル・テクノロジーズ(DELL)が注目されよう。
同様にスマホは前年同期比8.5%増の3億2610万台。IDCの事前予想(7.3%増)を上回り、10四半期ぶりの前年同期比プラスとなった。2023年通年で前年比3.2%減のなかアップル(AAPL)は出荷台数の世界シェア20.1%で首位となった。
パソコンとスマホの世界出荷台数〜スマホはいち早く前年同期比プラス圏
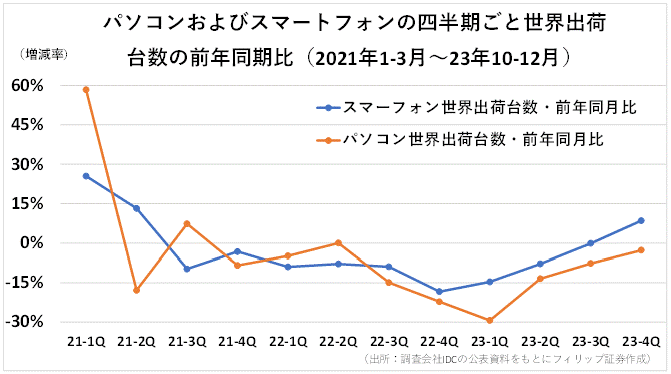
ドル円相場とドル指数の季節性
- ドル円為替相場およびドルインデックス(複数の主要国通貨に対する米ドルの価値を指数化したもの)について2023年12月までの過去20年間および30年間の平均月間騰落率を月毎に算出すると、ドル円相場は2〜6月、9・11月は相対的にドル高円安に振れていた。それ以外の月は相対的に円高ドル安傾向だった。
4年毎の米大統領選の年(1996年から7回分)を見ると「スーパーチューズ・デー」の3月、および6月、選挙直前の9・10月は円高ドル安傾向となり、選挙終了直後11・12月に明確なドル高円安傾向を示している。複数主要通貨に対する米ドル為替レートを指数化した「ドルインデックス」はドル円相場との相関性が必ずしも高くないなか、大統領選年は特に10月以降、逆相関といえる動きを示している。
ドル円相場とドル指数の季節性〜大統領選年は過去平均と異なる面も